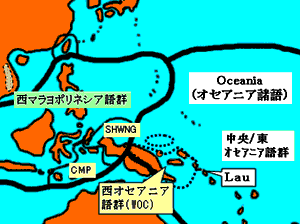4. 語末子音の残存・消失プロセスの推定 前ページの結果を再掲する。
蛇足であるが、名詞については
に示すように、語末の両唇音が残存した形跡はない。子音の消失がアクセントにも影響を与えなかった事は前にも述べた通りである。(参照ページ) 以上の結果から、以下のようなプロセスが生じたものと推定される。
このように図式化してしまうと、かえって分かり難いかもしれない。書いた本人でもこれでは分からんなーと思う次第である。 本稿の冒頭に挙げた、*at'at (浅い事)と、gənəp (揃う・無欠)を例にとって説明する。 祖語の段階においては、語幹の asat とその接尾辞形 asati が存在した。上には -i を他動詞形成接尾としたが、或いは受動態形成の接辞と考えた方が良いのかもしれない。ここらは祖語を対格言語と見るか、それとも能格言語とみるかで異なってくる。難しい所である注)。 注) おそらく読者のほとんどは、「能格言語」などという用語には馴染みがないと思う。専門家には笑われる説明かもしれないが、我々が他動詞として扱うものが、あたかも受動態動詞であるかのように振舞う言語である。この世にはそういう言語が相当の割合で存在する。 次の段階を「Pre-日本祖語」と呼ぶ事にする。或いは村山の表現に合わせて「倭の言語 I 」と呼んでもいいかもしれない。キャッチフレーズ的に「縄文語」と言っても良いのだが、なんだか、軽薄な感じがするので、この呼び名は筆者の好む所ではない。 「倭の言語 I」は、全般的に極めてAN語に近いものだったと想像する。音韻的には、語末の k/ŋ/t/d/s が消失した他、語頭有声音の無声化や、それに伴うアクセントの声調化(HH、LL)も生じていたと思われる。(音韻構造が単純化した代償にアクセントパターンが増えた。) この結果、*asat は asa になり、祖語の段階からの asati と、新しい語形 asa から派生した asa-i の3つの語形がしばらく(恐らく短い間)、共存する事になった。 一方、*gənəp は、この段階では、kənəp に姿を変え、接辞の付いた、kənəpi が存在した。両者がどのように使い分けされていたかについては、よく分からない。AN祖語からの類推だと前者が、形容詞的・状態記述的、後者が動詞的と思われる。例えば、
というような用法である。「見てきたようなウソを書くな!」と思われるかもしれないが、モチロン、上は(現時点での)筆者の「遊び」である。 しかし、これは真面目な話しだが、主語を明示せずに動詞(部)の形で暗黙に主語が決定されるという現代日本語に脈々と受け継がれているシステム注)は、既にこの時期に生じたのではないかと、筆者は想像している。 注) 野田尚史 「見えない主語を捉える」 (月刊「言語」 2004 Vol.33 No.2 p.24-31)の例を引用する。
動詞に人称接辞が接続せず、なおかつ、動詞が文中に現れる名詞(句)の格を支配するというのは、フィリピン諸語のフォーカスシテム(AN祖語起源と推定される)に近いような気がする。 (フォーカスシステムについては「接頭辞は本当にAN語起源か?」参照) ちと脱線しかかっているので話しを元に戻す。 asa を含めた、祖語段階からの asati 、新しい語形 asa-i からなる3語体系は、gənəp 起源の、kənəp /kənəpi の2語体系と比べると非対称かつ重複しているので、このような無駄は排除されるベキである。かくして言語変化を司る「見えざる手」によって、asati は廃棄され、 asa / asa-i kənəp /kənəpi のペアが生き残ったのではないかと想像される。 以上が、筆者のイメージする「倭の言語 I」の「素描イメージ」である。現段階では非常に素朴なものに過ぎないが、今まで論じてきたことをまとめると、「倭の言語 I」は、 1. 場所(Locus)強調接辞 i < *Si- 2. 手段フォーカス機能接頭辞 i- < *i- 3. アクセント後方移動による形容詞・形容動詞派生システム 4. 接尾辞 -i による動詞派生システム を備えていたと推定される。更に、今回の検討結果から、接尾辞 -i によるAN祖語語末子音(但し両唇音のみ)の保存が確認された。これは、AN祖語からの一貫した連続的な音韻変化で、古代日本語の動詞が形成された事を示唆する。 筆者は、「倭の言語 I」が発生した場所を、朝鮮半島ではなく日本列島内に想定する。かつて筆者も「倭の言語 I」の成立を朝鮮半島内と考えたが、(「日本語混合起源説に関する覚書」)ここ半年ばかりの検討結果を踏まえて考えが変わった。 朝鮮半島からの人的移動あるいは言語接触によって、「倭の言語 I」は劇的な変化を遂げたものと思われる。おそらく、一番大きいのは統語構造(要するに語順)の変化であろう。それに伴い、接尾辞や格助詞、代名詞が取り入れられた。 おそらくこの段階で、最終的に、p が消えて asa / asa-i kənə /kənəpi となり、次ぎの日本祖語成立の段階で、 asa / asa-i > ase2 kənə /kənə-i > kanai > kane2 kənəpi > kənə+ pi と、接辞「ひ」(終止形「ふ」)が動詞接尾辞として析出されることになる。 この段階で asa に、形容詞接辞 si が付いて形態的に固定化されたワケであるが、もし、kənə にも同じ変化が生じたとすれば、「悲し」(kana-si ;HHF) になる。以前、形容詞のアクセントについて論じた際に、ニ段動詞が形成された語については、アクセントが後方に移動しなかった(参照ページ)と述べたが、まさに、「悲し」についても、同じ規則が適用できる事になる注)。 ちなみに、「岩波古語辞典」も「悲し」と「兼ぬ」の同源説を提示している。 注) 村山説では、AN祖語の kat'ih (「同情」・「共感」)に、接中辞 əN が挿入された語形、**kəNat'ih を「悲し」の語源とするが、əNは接中辞ではなく接頭辞である。<*in>という接中辞はあるが、これの機能は、完了態形成接辞である。村山の論に(残念ながら)しばしば見受けられる、文法機能を無視した「接辞付加による語呂合わせ」的議論である。 かなり先走りしてしまったが、本稿が対象とする範囲の論旨で、問題というか飛躍があるのは、 asa を含めた、祖語段階からの asati 、 asa-i の3語体系は重複しているので、「見えざる手」によって、asati は廃棄され、asa / asa-i のペアが形成された。 という箇所であろう。 このようなプロセスが実際に生じたかどうかは、オセアニア諸語の状況が参考になる。なぜかと言うと、オセアニア諸語の分岐の果てには、すべての語末子音がキレイサッパリと消失したポリネシア諸語があるワケであるが、そこに行き着く途中段階の適当なオセアニア語を観察すれば、pre-日本祖語で語末子音が消えていった過程が検証できるのではないかと期待される。 5. オセアニア諸語における動詞語末子音の消失過程について と言っても、素人の筆者ゆえ、豊富な資料を持ち合わせるワケではない。ここで取り上げるのは、南ソロモン諸島の一角に位置する、Lau語という言語である。いい加減な説明図であるが、以下に簡単にLau語について説明しておく。Lau語が本当に適例であるかは検討不足である。次回はフィジー語を取り上げようかと思っている。
自動詞形で語末子音が消えているのに、他動詞形で、-si/-fi となっているのは、祖語の-*sや、-*p が接辞 -i の接続で保存されたためと考えられる。(*p > f は規則変化) ところが、
では、他動詞の語末に -si が現れる。これは、LAU語では *t が消失したたために、規則変化だと mate-i > **maei になるハズが3重母音の発生を嫌って、子音 s が挿入されたためと思われる。(「春雨」で、「アメ」が「サメ」になるのと似ている。) 面白いのは、
である。規則変化では、maquiripi > mauirifi > mouri-fi になるハズなのに、mouri-si となっているのは、この語形が、自動詞の mouri に -i を接続して、*mourii になるハズの所が、同じ母音の連続を嫌って、mae-si と同様に、s が挿入されて、mouri-si になったと考えられる。 即ち、mouri-si は、祖語の *maquiripi からの一貫した音韻変化で生じた語形ではなく、語末子音が脱落した自動詞 mouri から他の語との類推プロセスで形成されたものという事になる。 実は、ここに述べた語形解釈は、前掲書に記載されているのでなく、筆者自身のものであり、合っているかどうかは分からない。 そもそも、オセアニア諸語の他動詞あるいは受動態形の語末に現れる接尾辞モドキの語形は、一括して Cia 形(a は人称接辞とされる)と呼ばれているが、子音 C がどのような起源を有するのかについては、(少なくともフィジー語に関しては)、なんと150年間の議論の歴史がある。実は定説が未だに確立してない(下記の論文参照)。オーストロネシア比較言語学と言えば、もうほとんどの事が判明しているかと言うと、実はこんな基本的な事でもまだ不明な点が多く残っている。 「フィジー語他動詞の語末(子音)は何処から来たのか?」 ("Whence the Fijian Tansitive Endings ?") という表題のけっこう長い論文(50ページ余り)があるのだが(D. Arms; OCL Vol12 No.1-2 1973) 、実は本稿の「語末子音は何処へ消えた?」は、この論文の表題のパクリでもある。 という事から分かるように、多くのオセアニア諸語では、
というパターンが一般的で、筆者がPre-日本祖語に想定したような、CVCV-i という語形は基本的には現れない。(残念!) ピッタリ語形が合う例が発見できないのは残念であるが、前掲論文によれば、他動詞のあるものは、明らかに、語末子音が消失した自動詞から形成されている。即ち、
6.結論 長〜い論証過程を経てきたので、そもそも本稿の目的が何であったか、そして本稿で何が言えたかを整理する。 問題は、at'at (「浅い事」)を例に採ると、 I. *at'at の語末子音 t が脱落して at'a > asa になった。 II. そこに -i が接続して、ase2 という下ニ段動詞が形成された。 というプロセスが仮定されているが、接尾辞 -i がAN祖語起源であるとすれば、「浅くなる」(褪せ)という動詞は、*at'at-i > *asati にならないとおかしいのではないか? AN祖語からの規則変化からは、ase2 という語形は生じないではないか、という事だった。 この矛盾というか疑問をスッキリサッパリと解消するには、「縄文語」=「Pre-日本祖語」が開音節言語だったと仮定し、その言語エックスが、AN祖語を借用したと仮定するのがよろしい。では、その言語エックスとは何か? ・・・ という方向で日本語起源論を論じても良いかどうかが、本稿で検討した問題である。 本稿で得られた結論は、
第二の問題は、「AN祖語では、接尾辞 -i の接続の有無で自動詞と他動詞が形成されたのに、日本語ではそうなっていない。無接続形が名詞だったりして、接尾辞 -iの文法機能がAN祖語と異なるではないか」という事である。 しかし、オセアニア諸語の例を見ると、上に挙げたLau語近くの Are'are語では、-i の無接続形が名詞だったり、他の言語では無接続形が他動詞だったりして、けっこうバラエティに富んでいる。 それになんと言っても心強いのは、四段動詞=自動詞/対応する下ニ段動詞=他動詞というかなり明確なパターンが上代日本語に存在する事である。木田章義氏によれば(「古代日本語の再構成」 #JP-36)、
などのように、-i 接続形が他動詞となるものが53例あるのに対し、その逆、
などは12例である。これは、-i のAN語起源説に有利ではある。しかし、木田氏が指摘するように、また筆者自身が今まで挙げてきた多くの例が示すように、下ニ段が自動詞となる例は数多くあり、問題は単純ではない。この問題については、漠然としたアイデアはあるが、まだ未整理で後日の課題としたい。 7.補足: 重複形による動詞派生形式について 前ページでは説明の都合で述べなかった、両唇音以外の語末子音が残存したと思われる例について述べる。それは以下のようなケースである。
どちらも、祖語がCVCCVCの重複形になっている。bakba'k については、k に両唇音が後続するために、 -k の「聞こえ」が補強されて、日本語に子音が残存したのかもしれない。 「突く」については、AN語に t'ukt'uku と、t'akt'ak という母音の異なる類似語形があって紛らわしいが、筆者はチト大胆に「突く」と「刺す」が共に、t'akt'ak から派生した可能性がある事に注目したい。 この説の根拠は、前ページで述べた、
が、オセアニア祖語(POC)における重複形による動詞派生形式
と関係があるのではないかという推定に基づく。この仮定が正しいとすれば、「突く」と「刺す」は、 t'akt'ak > sasa' (未然形) > suki > tu'ki (連用形) というオセアニア諸語の派生形式に対応する。 上に挙げた例だけでは、この仮説は説得力に欠けるかもしれないが、オセアニア祖語(POC)的な重複形から生じたのではないかと疑われる語が他にも存在する。 築き(つき) tuki HL 槌(つち) tuti LH は、語形・アクセントからすれば同源とは到底見なしえないが、POC的派生法を仮定すれば、*tuktu'k を元に、 *tuktu'k > tutu' > tuti (名詞形 LH) 元は動詞? > tu'ki (未然形 HL) のように生じたのではないかと解釈できる。実際、*tuktuk : 「搗く」(pound/knock/hammer) が再構されている(CAND再構形)。セブアノ語では、tuktu'k (ノックする。つつく。)である。 「掻く」(kaku; LF)にしても、筆者は、
から単に -t'k- > k と t' が脱落して kaka (未然形)になったと当初は考えていたのだが、POC的な派生で生じたとする方が、スッキリする。但し、ペアとなるべき kasi/kati に対応する動詞が見つからない。辞書を引くと、「かせ」(下ニ段; やせ衰える)や、「かし」(四段: 米を研ぐ)という語があるのだが、前者の文献初出は13世紀で、後者は原義が「濡らす」だったらしく「掻く」の同源語とするのはチト無理がある。 この他、重複形によって派生されたと疑われる動詞として「懸け」(kakai)、「聞く」(kika)がある。 例えば、「鉤」のAN祖語のヒトツ、*kahit (ダイエンによる。DMP形は *kawit/*kavit ;Tagは ka'wit)の(部分)重複形を想定すれば、kaka'hit > kaka'i と、謎だった「鉤」と「懸け」(下ニ段; LF)との関係を説明できる・・・。 重複形で派生した語がそれなりの数存在するかもしれない事は、日本祖語とオセアニア祖語との関連をどう考えるかという問題に発展するが、筆者の気力が尽きた。初稿の段階での検討はここまでとする。思いついた事は随時、追記するか、後日まとめて論じる事にしたい。 8. 今後の予定 今までは、AN語と言っても、主にフィリピン諸語との比較を参考にして考察する事が多かった。それは、語彙比較が主要テーマで、アクセントを有用なツールと考えた事が理由のヒトツである。(モチロン、日本語がAN語の中でも特にフィリピン諸語との関係が深いと判断しているからでもある。) 今後は、「倭の言語 I 」から日本祖語に至るプロセスの再構を試みることにしたい。この場合には、語彙ではなく、統語論や形態論が主要テーマとなる。すると、本稿でも論じたように、オセアニア諸語が参考になる。 オセアニア諸語のシステムは、いわばAN祖語からの(音韻的・形態的な)「崩れ」あるいは「簡略化」で生じた。これには日本語の成立過程と類似した側面があるに違いない。従ってオセアニア諸語における、「崩れ方」の挙動を見れば、「倭の言語 I 」から日本祖語に至るプロセスで起きた事の手掛かりが得られるという期待を筆者は抱いている。 本稿の第5節はその試みの「手始め」のつもりだったのだが、あまりうまくいかなかったようである。一方、重複による派生法については、筆者はいささかとまどっている。 特に、「築き」(HL)と「槌」(LH)が、オセアニア語的派生法から導出されるいうのは話しがウマスギる。予想に反してPOCとの関係が深いのだろうか・・・。 現在考えている表題は、本稿の続編(?)、「接頭辞は何処へ消えた?」というものである(笑) 2006/10/22 初稿UP 2006/10/23-24 ミス修正。 前の地図は大間違い。 Lau語がソロモン諸島でなくニューカレドニア諸島に位置してた!お恥ずかしい・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||