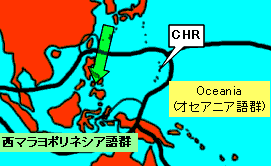|
日本語の接頭辞はAN語起源か? (page1/5) |
||||||||||||||||||||
| 要約: AN諸語では、接頭辞の形態が、態・相の決定のみならず、語を統合する機能を演じているが、上代日本語における接頭辞にそのような機能を見出すことはできない。従って、上代日本語とAN諸語との形態論的比較は本質的に不可能である。 しかし、「イ行く」「イ隠る」などに現れる接頭辞「イ」は、動詞のみに接続するという特徴を有する。そこで「イ」が、どのような動詞に接続するかを分析してそのパターンを抽出し、フィリピン諸語(タガログ語・イロカノ語・セブアノ語)の接頭辞 " i " における事例と比較した。結論は、「最後のお楽しみ」である。 1.日本語の接頭辞は本当にAN語起源なのか? 日本語-AN(オーストロネシア)語起源説の根拠のヒトツに接頭辞がある。「い隠る」「か黒き」「さ衣」「ま白に」などである。アルタイ系諸語にはこのような接頭辞は見られない。 しかし、AN諸語における接頭辞が、日本語の助動詞にも匹敵する多用・多彩な機能を演じるのに対し、上代日本語における接頭辞は、せいぜい「強調」くらいの周辺的な機能しか持たず、両者の類似は語形と「頭に付く」という出現位置に過ぎない。しかも「語形」と言っても僅か一音節で、これでは両者が同一の起源を有する証拠としては全く不充分であるとされてきた。 接頭辞の比較には、形態論に踏み込まないと全く意味がない。「形態論的比較」というのは、具体的には以下のような事である。 ポリワーノフ説 日本語混合起源説の提唱者である E.ポリワーノフは、日本語の「真っ黒」(makkuuro < *makukuro ) を、タガログ語における、複数名詞に対する形容詞形 mababait (語幹:bait 「善良なこと」)と似ていると指摘した。 即ち、タガログ語では、名詞である bait (善良であること)に形容詞形成接辞である ma が前接して mabait (良い)が形成され、それが複数名詞を修飾する時に、語幹が不完全反復された ma-ba-bait になる。大雑把に言えば、このような語の「活用」の仕方が「形態論」である。 タガログ語と日本語では語の並べ方(統語論)が異なるので、両者の起源を同じくするかどうかを論じるには、形態論の比較が決定的に重要になる。統語論的な要素は形態に比べると変化の自由度が高く、原則的には系統問題を論じる際にはほとんど役に立たない。 上の例における「形態論的比較」とは、日本祖語において、 1. 「黒」(kuro) が名詞であったかどうか? 2. 「真黒」(makuro) が形容詞であったか? 3. 「真っ黒」が複数名詞を形容する形容詞であったか? を問うことである。3が言えれば決定的なのだが、モチロン、そのような証拠はない。そもそも makuro が、古い時代に形容詞であったという証拠すらない。(「真白」も同じ。) mababait と makukuro の語形が単純に似ているというだけではせいぜい「興味深い」というだけで、そこから更に進んで両者の同源関係を論じるのは不可能である。 村山説 ポリワーノフの日本語混合起源説を継承した村山は、AN語の接頭辞やそれによって生じる前鼻音化現象が日本語にも見られると主張したのであるが、AN祖語に接頭辞が付いた語形と比較できる語が日本語にも見られると主張した「だけ」で、形態論まで立ち入った比較とは言えない。 例えば有名な、「む抱く」を例に取る。日本語には、「抱く」を意味する、 i(u)daku と mudaku があったが、これらは、AN祖語「抱く」を意味する dakəp とその前接辞形 məndakəp と「語形」が対応すると主張した。 しかし、AN祖語において、dakəp と məndakəp はどのような意味の違いがあって、それが日本語でどのような違いとして反映されているかについては、一切論じられていない。(というか論じることができなかった。) おそらく国語学者の、というか「常識的な見解」においては、mudaku は、「身」+「抱く」という合成語と解釈するのが自然であろう(「岩波古語辞典」)。日本語の範囲で説明できるなら、なにもAN語を持ち出す必然性はないのである。やはり、mudaku という語形が、文法的にどういう機能を果たしていたかが分からないと、語形がいくら類似していても、説得力は著しく低下してしまうのである。 もちろん村山が行なった語形比較が無意味というワケではない。そもそもAN比較言語学の創立者であるデンプウォルフは、語形比較オンリーで学説を構成したのであって注)、形態論の比較がなければ比較言語学とは言えないというのは極論である。 注) AN比較言語学の基礎となったデンプウォルフの著書名は、"Vergleichende Lautlehre des Austronesischen Wortschatzes" (「オーストロネシア語彙の比較音韻論」)であり、形態論的比較らしきものは、ほとんど行なっていない。 崎山説 AN語と日本語の系統論的な関係を論じる場合には、上述したように形態論の比較が絶対不可欠である。レギュラーな音韻対応を示す語彙の絶対数が足りないために、語形の比較だけでは、借用か同源かを判定することができない。 語形比較を越えて形態論の比較に踏み込むためには、なんとしても、上代日本語において、なんらかの文法的機能の痕跡を残す接頭辞を探し出さなくてはならない。なぜなら、AN語の形態論は接頭辞に集約されるからである。 接頭辞の意味機能まで立ち入った比較を試みたのが、崎山理である。「か」「さ」「た」などについてAN語との比較を試みた。筆者の見解ではこれらの接頭辞から説得力ある結果を得るのは非常に困難と思われる。 A.ボビンの以下の論評を、少し長いが引用する。(「日本語系統論の現在」(2003)p. 17-18) 「崎山理は、基礎語彙だけでなく、マライ・ポリネシア祖語と日本祖語の文法要素の比較も試みている。崎山の比較はだいたい上代日本語の動詞と形容詞の接頭語と代名詞である。(中略) たとえば、崎山は上代日本語の ta- が『偶発性』で ka- が『被災的』で、 sa- が『類似概念の派生』だと指摘している。しかし、この崎山があげている文法的な意味が何に基づくものなのかが全く示されていない。(中略) 例えば、『時代別国語大辞典』には次のように定義されている。 ta- には『広く名詞・副詞・動詞・形容詞に冠して用いられる』として定義がなく、ka- は『主として形容詞に接続してその意味に一種の色調を添える』で、sa- は『ほとんど実質的な意味ない』。(中略) このような、ある言語には存在しても、ある言語では存在しない接頭辞の文法的意味の比較は、何も証明することはできない。崎山がこれらの上代日本語の接頭辞の『文法的意味』を、その比較の対象であるマライ・ポリネシア語の接頭辞に対応させるために作り上げたということは明白である。 いうまでもなくこのような方法は比較言語学の方法に反している。崎山は上代日本語の代名詞の分析も試みているが、その分析法も比較言語学の方法に反している。」 なかなか手厳しい。筆者も、接頭辞の「か」「さ」「た」の分析から何らかの結論を導くのは非常に難しいと考える。 一方、崎山は本稿で取り上げる接頭辞 「イ」 についても論じている。オセアニア諸語との比較を行い、「イ」に関しては、「機能の残存がまだかすかに認められる」と結論した。(「日本語の形成」(1991年)p. 105-108) 筆者の検討でも、唯一の可能性がある接頭辞は、やはり「イ」であり、崎山氏の見解に同意する。しかし後述するように、筆者はオセアニア諸語とよりも、フィリピン諸語との比較の方が、より実りの多い結果が得られると考える。 本稿では、上代日本語における接頭辞「イ」と、フィリピン諸語における接頭辞 ”i” の詳細な比較を試みた。 2.戦略の策定 上代日本語に現われる接辞「イ」はこれまで多くの国語学者、言語学者に取り上げられてきた。 特に、上で紹介したように崎山は、これらの「イ」を分類・整理し、それらをすべて「これ」を意味する指示詞起源であるとし、オセアニア諸語に広汎に現われる "i" の諸機能と比較した。オセアニア諸語というのは、フィリピン群島の東から南米ペルー沖のイースター島に至る広大な領域に分布するAN語族内の巨大ファミリーである。(下図参照) (CHRはチャモロ語の略。 筆者は、チャモロ語をフィリピン諸語とオセアニア語群を連結する重要拠点と考えるが、これについては別稿で論じる予定である。)
筆者が崎山の指摘で最も重要だと考えるのは、指示詞の「必ずしも自明ではない用法」が、上代日本語とAN諸語で一致することである。 ここで簡単に、崎山説を紹介する。上代日本語における「イ」の用法は、以下のように分類される。(筆者の考えで重複していると思われるものを、一部省略した。) 1.代名詞 「イが作り仕へ奉れる大殿の内には・・・」 2.助詞 (1)強調機能 「毛野の若子イ笛吹き上る」 (2)場所表示機能 「この国土イ 経を弘むるに頼る故に・・・」 3.接尾辞(強調?) 「・・・久米の子等が頭椎イ石椎イもち撃ちてし止まむ」 など 4.接頭辞 動詞の語調を整える注) 5.動詞連用形の形成機能 「開け」= ake2 < aka-i などの二段活用動詞に現れる接尾辞 "-i " 注) 別の箇所で「外部にあって動作のおよぶ場所ないし対象(「そこ」)が『イ』によって指示されている」と述べている。 上に挙げたすべての用法がオセアニア諸語にも見られるとするのであるが、筆者が、「必ずしも自明ではない指示詞の用法」と考えるのは、下線で示した、助詞の場所表示機能、動詞接頭辞における場所指示的な機能(上記の注参照)、および連用形の形成機能である。 崎山自身も、アルタイ諸語に見られる三人称単数代名詞 "i" (おそらく指示詞起源)には、このような場所表示機能(所格機能)がないことを論拠にして、上代日本語「イ」との関連を否定している。 オセアニア諸語と日本語の関係を重視する崎山の主張には賛同できる点とできない点がある。私が見るところ、崎山の比較方法は広大な太平洋領域に装備の手薄な部隊をばら撒くようなもので、これでは太平洋戦争時の日本軍の愚を繰り返すようなものである。例えば、AN諸語における接頭辞の用例として崎山が挙げたのは、 1.名詞化機能: kau (鉤で掛ける) → i-kau (鉤) bini (積む)→ i-binibini (堆積) 2.受益者フォーカス機能: sulat (書く) → i-sulat (〜のために書く) 3.場所・道具: i-Vatan (バタン人・島) lil.ai (揺する)→ i-lul.ai (揺り篭) などであるが、1番目の、「イ」が接頭して名詞が形成される事例は、上代日本語にはない。2番目と3番目は、オセアニア諸語ではなく西マラヨポリネシア語群に属するタガログ語とヤミ語の例であって、論旨の一貫性に欠けるし、筆者にはあまり印象的な比較とは思えない。(「受益者フォーカス」という用語については後で解説する。) これに対し、筆者は、崎山氏とは異なる戦略を採用する。即ち、西マラヨ・ポリネシア方面軍、特にフィリピン戦線における縦深突破である。(上図参照)日本語とAN諸語との関係を論じる際の本筋は、グアム・サイパンのマリアナ諸島からフィリピン諸島を結ぶラインで、この戦線に主力を集中するべきと筆者は判断する。このラインは、太平洋戦争後半において日本軍が設定した「絶対国防ライン」に当たる。ここが突破されれば琉球・日本本土はすぐ目前なのである。 そして比較対象を動詞に絞る。 上に述べたように、指示詞の用法(転用)は言語に依存しない普遍的な要素が強い。一方、動詞の用法は個別言語の個性を反映している。もし上代日本語における動詞接頭辞「イ」を分析して、特化された用法や意味を抽出でき、それが他の言語と顕著な一致を示すならば、その証明力は指示詞に比べると遥かに大きい。指示詞を機関銃とすれば、動詞は戦車砲くらいの突破力があると筆者は考える。 具体的な手順は以下の通りである。
例によって長々と能書き・前書きを述べてきたが、ようやくここからが本論である。 3.タガログ語における接辞の機能 (タガログ語文法超入門) まずは、AN諸語における接頭辞がどのような機能を演じているかについて解説するところから始める。例によって「基礎は必要最小限に、脱線は過剰に」をモットーとする。 ここでは、筆者に一番馴染みの深いタガログ語を例に取って説明する。フィリピン諸語では、接(頭)辞がAN祖語の段階に比べ高度に複雑化注)したが、タガログ語でもインドネシア語でも基本システムは同じである。 注) どれくらい「複雑」か、以下の例を挙げる。 makapakipagpakapa-bayu 「自ら参加できるように改めさせる事ができる。」 bayu が「新しい」という意味の語幹で、それ以外はすべて接頭辞である。これは英語の論文に載っていた例で、"monstrous"(怪物のような)と形容されているのだが、日本語の膠着システムも負けていない。 「御心使い せさせ給ひつべからむ 夜」 (「源氏物語」からの文例) だって相当複雑であるし、 現代語で、「改めさせれないかもしれない」(arata-me-sase-re-nai-kamo-sire-nai)と言えば相当に複雑で、もし私が米国人であれば、やはり、"monstrous"(怪物のような)と形容すると思われる。 AN諸語の語順は、(動詞 V)(主語 S)(目的語 O)と言われているが、なかなかどうしてそう簡単なものではない。「フォーカス」(焦点)と呼ばれる、独特のシステムが稼動している。 まずは二つの文章から。 単語: kain (名詞:「食べること」) isda 「魚」 bata 「子供」 ng と ang は取り敢えず前接の助詞みたいなものだと思って頂きたい。 例文:
um と in は接中辞と呼ばれ、語幹「食べる」の中に割って入るように接続される。「接頭辞についての解説」と前置きしながら接中辞を出すのは、いかがなものかと思われるかもしれないが、それは解説の都合というものがあるのである。 一番目の文章を見ると、ang 以下の名詞 bata (子供)が主語だが、2番目の文では、bata は目的語である。ang を主格表示の助詞と考えると、2番目の文章は受動態(「その子供はその魚に食べられた。」)ということになる。しかし、タガログ語文法では、この文を「受動態」とは言わない。 1の文は「行為者フォーカス」、2は「対象フォーカス」と呼ばれる。筆者が知る限りでは、「フォーカス(焦点)とはなにか」という事を素人に分り易く解説してくれるテキストがない。「フィリピン語文法入門」と題した初学者向け教科書でも説明が不親切で、「これでは全然分らん!」と、ここで不満を述べておきたい。 「フォーカス」というのは、多分、こういう事であろうと筆者は理解している。 2は、やはり受動態で、「その子供はその魚に食べられた。」と訳すのが、より「適切」と思われる。 (「適切」の定義は何かと言われると困るのだが。) 日本語や英語では、受動態を構成する時には、"食べ-られ-" とか " be eaten" というように、受身の助動詞とか過去分詞といった「特別な道具立て」を必要とする。 それに対し、タガログ語では(他のAN諸語でも)、能動態も受動態も、「動詞に接辞を付ける」という同じ枠組みの中での別形態として扱われている。これは明らかに、英語や日本語と異なるシステムなので、「フォーカス」という特別な名前で呼ぼう、という事である。 「フォーカス・システム」においては、文中の特定の語の格(主格とか目的格とか)が、動詞によって決定される。タガログ語においては 以下のような手順で統語関係が決まっている。 第一の例: (AF=Actor Focus は行為者フォーカスの略) K-um-ain ng isda ang bata. 食べる(AF) 魚 その子供
第二の例: (GF = Goal Focus 或いは 対象フォーカス→目的語がフォーカスされる) K-in-ain ng isda ang bata. 食べる(GF) 魚 その子供
それでは以下の文はどうか? Ipinang-bukas ni Fe ng pinto ang susi. 開ける (事) フェ(人名) ドア その鍵 今度は、ang 以下の名詞が susi (鍵)になっている。 Ipinang は「手段フォーカス」と呼ばれる接辞で、かつ行為が完了した事を示す。 上に説明した手順を実行すると、
では、この文章は受動態なのか能動態なのか?上の文を敢えて逐語訳すると 「その鍵で フェの ドアの 開かれ。」 となるのだろうが、行為者であるフェがトピックでない以上は、おそらく受動態の一種と言えるのだと思われる。自信はあまり無いが、上の文は 「その鍵によって フェにより ドアが開いた状態になった。」 と訳すのが最も正しくニュアンスを伝えているような気がする。(日本語としては不自然だが。) 最初聞いた時は、「日本語とは全く異質な文法だ。こんなものが日本語と関係あるハズがない。」という感想を抱くのであるが、それは日本語がSOVで統語されていると「ウソ」を教え込まれているからである。 「わたしはメンバーから除いてくれ。」 「わたしはメンバーから除くつもりだ。」 (どちらとも取れるか・・・) という場合、「わたし」が主格か目的格かどうかを決めているのは助詞「は」ではなく、動詞に接続される「形態要素」であると言える。(2番目は動詞文ではないので、この例はちょっとインチキだが。) 日本語の「は」は、主格表示の助詞などではなく、「〜なんだけどー」に置換え可能な事から分るように、主格というよりトピック表示機能を演じている。 本職の言語学者がなんと言うかは知らないが、動詞に活用形のようなものがベタベタ引っ付いて中央集権的に情報を一括管理するのという点で、タガログ語も類型的には膠着語と言える。 筆者は日本語がトピック表示言語で主語・目的語の表示や、受動と能動の区別が曖昧だったりするのは、日本語がAN語起源である事と関係があると思っているのだが、これは、今のところは妄想的な与太話しである。 古代日本語に接中辞は存在したか? 接中辞が出てきたので、ここで脱線して補足しておく。上でも述べた村山説における語形比較と形態論的比較についてである。 村山説によれば、「米」(ko2me2)は、「食べ物」の古語「ケ」 ke2 < *kai に接中辞 -əm- を付けた派生語である。 「ケ」: ke2 < *kain 「米」: ko2me2 < *k-əm-ain 確かに語形としてはキレイに対応する。しかし語形比較に留まらず形態論的な考察を村山に代わって行なうと、論理的には以下のような主張が導かれる。 村山説が正しとすれば、-əm- は行為者フォーカスの動詞形成接辞なので、「米」は元来は「食べる」を意味する動詞のハズであり、「米」は、それが名詞化されたものという事になる。ではどのような動詞だったのかと言うと、 未然形: ko2mai こめ(ず) 連用形: ko2mai こめ(て) 終止形: ko2mu こむ のような下二段活用形が想定されるが、同一語幹中に o2/a は原則的に共存できない(有坂の結合則)ので、語幹 ko2ma は、kama か、ko2mo2 に変化すると予想される。前者であればその終止形は、kamu となる。 これが「噛む」と同じものなのかどうかであるが、声調は、「米」がLL、「噛む」がLFで、一応は矛盾しない。「噛む(kamu)」と「食べる」では意味が違うが、琉球語では「噛む」は「食べる」を意味する。 もし「噛む」の原義が「食べる」であるならば、AN語と同源と考えられる名詞「食(ケ)」から、接中辞によって動詞の「噛む」〜「食べる」とその名詞形「米」が派生された事になる。 「ケ」、「米」、「噛む」という全く別と思われる3つの単語の関係を説明できるという意味で、上に挙げた「ム抱く」の場合よりも遥かに、日本語AN語起源説の根拠としては説得力があり、このような対応がニ十個ばかりも見つかれば決定的なのであるが、残念ながら、このような対応例はこの一例しか知られていない注)。 注) なぜか、ko2me2 という語は上代では日本書紀に 1回現われるだけの希少語彙で、松本克己は「歴史の浅い語」としている。ko2mai は、不安定で、もしかしたら 「神に供える聖なる米」を意味する kuma-s-ine における、kuma の形に変化したのかもしれない。それでも使用が非常に孤立的で、kamu のように非常にメジャーな動詞が派生したのに、なぜその名詞形の使用頻度が希少なのかが、分らない。 話しを戻す。 タガログ語で一番難しいのは、動詞によって、接続される接辞に制限があることである。感覚的には、不規則活用動詞みたいなものが一杯あるようなもので、動詞にどういう接辞が付くかをいちいち記憶しないといけない注)。 注) ここで「動詞」と書いたが、正確には動詞化が可能な名詞というべきである。タガログ語では動詞は(基本的には)名詞から派生される。接辞なしで動詞化される名詞もあり、なかなか複雑である。 但し、「この接辞には、こういう意味の動詞が接続されるという一定の傾向」のようなものがあり、動詞の意味が接辞の機能と密接に関連しているのである。即ち、フィリピン諸語における接辞は、完全に無色な文法的機能のみを演じるのではなく、ある程度、意味論の領域にも入り込んだ機能を有している。 前置きでは、形態論的な比較の重要性を力説したが、上代日本語にAN諸語のようなフォーカスシステムが稼動していたことを示すのは、まず不可能なので、純粋な意味での形態論的比較を行なうことはそもそも「無理」なのである。比較の可能性が生じるのは、この意味論的な領域においてである注)。 つまり、日本語における接頭辞が、 (1)意味論的にどのような機能を演じていたか? (2)それがどのような動詞に接続したか? を調べ、それがAN諸語における状況と一致するかどうかを比較するという、比較言語学の常道からは外れた、いわば綱渡り的な作業でしか両者を比較することができない。 注) 上でタガログ語が膠着語的と書いたが、膠着語というより、derivational (日本語で何と訳すか知らない。導出的?)に近いと表現する論者もいる。 (M. Ross) 更新記録: 2006年7月17日 初稿作成 2006年7月19日 注)を追加 2006年8月26日 論旨変更 |
||||||||||||||||||||