|
日本語形容詞アクセントの謎 (page1/3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要約: 平安代日本語の形容詞、或いは形容動詞のアクセントは、語頭低声調を示すものが圧倒的に多い。また、「暮る」(HL)「黒し」(LLF)のように、語頭声調の高低で「動詞」と「形容詞」のペアが形成される語例が存在する。これらは、アクセントを後方移動させて形容詞を派生するシステムが、日本祖語に存在した痕跡と解釈される。このようなアクセント移動による形容詞(形容動詞)の派生法は、AN祖語にも存在したと推定されている。日本祖語とAN祖語が、語彙だけでなく、同じ語形成システムをも共有していたとするなら、推定し得る最古の日本語は、形態論的に、AN祖語に限りなく近いものであったかもしれない。即ち、プロト日本祖語は、AN語を大量借用した「アルタイ的言語」ではなく、アルタイ的統語構造を借用した「AN的言語」である可能性の方が高いと考えられる。 1.はじめに 前回は、接頭辞「イ」がAN語起源と考え得るかどうかの検討を行なった。結構「いい線」まで迫る事ができたと筆者は思うのであるが、所詮、日本語における接頭辞は化石的要素でしかない。日本語とAN語の接頭辞の比較には本質的な困難が伴う。 ここで再度、筆者の意図をしつこいようだが、再確認しておく。 以前、「日本語-AN語 基礎100語比較」でやったような、AN祖語と同源とみなせる語彙をこのまま収集して行っても、それらが借用によるものか、系統関係を示唆するものなのか、結論を得ることは難しい。村山の手法の単なる改良だけでは、日本語起源問題の解答が得られる見込みはないと筆者は考える。 確かに、デンプウォルフは、語形の比較からAN祖語の再構に成功したのであるが、それは、元々、誰が見ても(或いは見る人が見れば)明かな、広範な語形の類似がAN諸語間にあり、そこに厳密な音韻対応を設定できたからこそ可能だったワケである。(数詞における音韻対応の具体例については、「『十(トヲ)』は高句麗語と同源か?」参照。) 一般的には、系統問題における「決め手」は形態論(日本語の場合には用言の活用形態という事になる)だが、AN語の形態論は接頭辞(接中・接尾辞もあるが)に集約されるのに対し、上代日本語における接頭辞は、「語調を整える」「強調」程度の役割しか演じていない。AN語と日本語間の形態論的比較は不可能、よって両者の関係も不明、という結論に至ってしまう。 この論理の壁を打破するには、「接頭辞以外のAN語起源の形態論的(文法的)要素」を発見するしかない。 2.形容詞アクセントに見られる「偏り」について 「接頭辞以外のAN語の形態論的要素」というが、果たしてそのような都合の良いものを発見することができるのだろうか? 筆者は、意外かもしれないが、「アクセント」にその可能性があると考える。 以前、筆者は、同源と推定される語どうしで、AN祖語(或いは祖語のアクセント体系を継承すると見られるフィリピン諸語)のアクセントと、平安時代の日本語アクセント(正確には第一音節の高低アクセント)が、偶然とは考え得ない頻度で一致する事を示した。(参考:「徹底検証! 村山説」) では、アクセントが一致しない事例は、どのように解釈されるだろうか? 基礎語彙100語に対し、約60語をAN語と関係ありそうだと判定したのであるが、その内、語頭アクセントが一致しなかったものは、以下の14語である。(一致率〜75%)
この中で、最後の2語は形容詞である。数詞の「ヒト(ツ)」も、「等し」という形容詞の語幹と考えられる。そこで改めて基礎100語に挙げられた形容詞のアクセントを見ると、いささか愕然とするのである。
なんと、9語すべてで、アクセントが語末にある。 約1000ほどの語について平安代の声調パターンを集計すると注)、語頭低声調の語は55%、高声調の語は45%である。やや語頭低声調のものが多い傾向があるものの、9語を取り出して、そのすべてが語頭低声調というのは偶然では有り得ない(あくまで「統計学的に」という意味でだが)。 「形容詞は語頭低声調」(或いは語末アクセント)という明確な傾向がある。 注) アクセント資料が豊富に揃っているのは平安代からである。奈良と平安時代では大きなアクセント変化はなかったものと推定される事は、既に別稿で述べた通りである。 取り上げる形容詞の語数を増やすと、上のような極端な偏りは小さくなるが、形容動詞(ナリが付いて活用することになった語をここでは便宜的に形容動詞と呼ぶことにする)も含めた、使用頻度が高そうな「形容詞的用言」を100語ほど集めてアクセントを見ても、約80%が語頭低声調だった。 国語学でどのように解釈されているか筆者は知らないが、これには説明されるべき理由があるに違いないと筆者は考える。 さて。 AN祖語ではアクセントを最終音節に移動させて形容詞を形成していたという説がある。 以下に、AN祖語のアクセント体系を論じた、Wolff の論文を、要約して引用する。 (John Wolff : "Proto-Austronesian stress" "Tonality in Austronesian Languages" 1993 OCL-No.24 所収 p.1-3) 西インドネシア諸語では、ストレス弁別の要素は、ほとんど残っていないが、Toba-Batak 語には、いくらかの痕跡が残存する。 Toba-Batak語における、ほとんどの語幹は、他のインドネシア諸語と同じように、ペナルト(後ろから2番目の音節)にアクセントが来るが、使用頻度の高い基礎的語彙のうち、形容詞に分類される語彙では、最終音節にアクセントが来る。 これは、フィリピン諸語と同じであり、状態形容詞のグループでは、最終音節にアクセントが来る。この現象が、Toba-Batak語にも痕跡的に残存しているものと考えられる。フィリピン諸語のあるもの(例えばセブ語)においては、このような語末アクセントを形容詞の標識とするシステムは崩壊したが、タガログ語にはかなり完全な形で残っており、接辞が付いた時のアクセント位置の挙動は、最終音節におけるストレスが、言語の古い段階における形容詞の標識である事をはっきりと示している。このストレスによる形容詞の標識は、祖語から継承されたものと考えられる。 Toba-Batak 語というのは、下の地図でTBで表示した、スマトラ島北西部の、タガログ語はフィリピン中部の言語である。上では、「ペナルト」という専門用語が出てきたが、2音節の語であれば、「ペナルト」というのは、要するに、第一音節という事である。 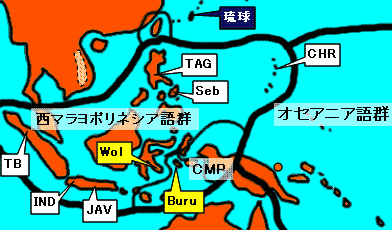 日本語との関連で更に興味を引くのは以下の記述である。 Toba-Batak 語で、(フィリピン諸語における ma- のような)形容詞を標識する接辞が失われた際に、語末にアクセントが移動させるプロセスが、すべての形容詞において拡大されたと考えられる。 筆者は、この文章を読んだ時には、 「遂に、これこそ、今度こそ、AN祖語で機能していた形態論的要素を発見したゾ!」 と考えたのであるが、問題はそう簡単ではない・・・ようである。 3. 議論の前提 アクセント位置の移動で品詞が変更される言語は、それほど珍しいワケではない。英語にしても、 extra'ct (抽出する) は動詞で e'xtract (抽出物) は名詞 だったりする。英語は強勢アクセント言語だが、声調的な言語では、高低アクセントの変化が文法上重要な機能を果たしている例が多く見られる。 E.サピーアによれば (「言語 ことばの研究」: LN-30)、アフリカのスーダンにおける諸言語には、アクセントの高低が文法機能の表示に使用されるものが多く見られる。例えば、ユー語(Ewe)では、subo (仕える)から語形重複により、subosubo が派生されるが、 前半が低声調で、 LLHH の場合は、「仕える」(不定詞)であり、 すべて高声調で、 HHHHの場合は、「仕えている」(形容詞) となる。ナイル河流域のシルク語(Shiluk)では、声調の高低で、名詞の単数・複数が表示される。また、アラスカ南部海岸のインディアンの言語、トリンギット語(Tlingit)では、声調の高低で動詞の過去形と未来形を表わす。 これらの例から、サピーアは、 「要するに、高低アクセントが、強弱アクセントや母音または子音の変更と同様に、われわれ自身の言語習慣から推して信じられるよりも遥かに多く、文法的手順として用いられているのは、明白である。」 (前掲書 p.75) と結論している。 サピーアは例に挙げてないが、印欧祖語でもアクセントの移動が形態論的な機能を有していたと考えられる注)。 注) 印欧祖語の母音間の *k は、ゲルマン語においては、直前の母音にアクセントがある場合には、 -V' k V- > -V' h V と、 h に変化したが、アクセントのある母音の前では、-V k V'- > -V γ V' と有声音に変化した。(ヴェルナーの法則) ドイツ語の ziehen (引く)の過去分詞は、ge-zogen であるが、一見不規則に見える h と g の交替は、ヴェルナーの法則を適用すれば、過去分詞でアクセントが後方移動したためと解釈される。(現代語ではアクセントは現在形・過去分詞ともに、後ろから2番目の音節にある) ziehen に対応するラテン語は、 du:c-o (私は導く) であるが、過去分詞は、duc-tus である。語幹母音の長さの変化も、アクセントの移動で説明できる。 du:c は、印欧祖語 *deuko- (導く)に遡るが、現在形ではアクセントが前にあって、de'uko- であったとすれば、-e'u- の二重母音が、長母音 u: となるのは規則変化である。ドイツ語と同じように過去分詞でアクセントが接尾辞に移動して、 *deuk-o'n- となったとすれば、アクセントのなくなった e が消失して、*duko'n となり、過去分詞 における短母音が説明できる。 (「印欧人」のことば誌 A.マルティネ著 神山孝夫訳 p.206 の要約。/ p.246-251辺りも参照) 従って、語末へのアクセント移動によって形容詞を派生するシステムが日本祖語に存在したからと言って、それがAN祖語起源と断定する事はできない。別の言語の影響か、あるいは、日本語内で独自に発達した形式である可能性も有り得る。 ノストラティック超語族説の信奉者からすれば、上の注)で述べた印欧祖語の派生法は、印欧祖語と日本語が同源である証拠のヒトツ(!?)ということになるかもしれない。 しかし、今まで検討してきたように、日本語の古い時代(確実に遡れるのは平安朝までだが)のアクセントは、AN祖語アクセントを継承していると考えて、ほぼ間違いない。 筆者の見積もりでは、平安朝日本語とAN祖語(フィリピン諸語アクセントも利用しての比較だが)の語頭声調一致率は、約70%とかなり良好であり、統計学的に有意に一致する(参考ページ)。とすれば、AN祖語で機能していた形容詞派生システムが、そのまま完全な形で、或いは Toba-Batak 語において見られるような更に拡大された形で、日本祖語に継承された可能性は非常に高い。 日本語は、2音節語の場合、AN祖語にはなかった、HH、HF、LL、LF (Fは下降調)といった各種声調パターンを生み出した。(AN祖語は、HLとLHの2パターンのみ。)これは、日本祖語では、語末子音がほぼ全面的に脱落するなど、音韻体系がAN祖語よりも大幅に簡略化されたために、アクセントに、AN語におけるよりも、より大きな機能的負荷が課せられた事による日本語独自の発展形態であると、筆者は推定する。 だとすれば、なおのこと、語の弁別機能のみならず、文法的・形態論的機能の一部をアクセントに分担させるAN祖語のシステムが日本祖語に継承される蓋然性は、インドネシア諸語と比べると、ずっと大きかったと推定される。 問題は、上に引用した Wolff説を鵜呑みにして良いかどうかである。要約文からも分かるように、「語末アクセントを形容詞の標識とするシステム」が完全な形で残存するのは実質的にはタガログ語のみで、Toba-Batak 語にはその痕跡が残るに過ぎない。Wolff 自身も、アクセントによる語弁別機能を痕跡的に残す他のインドネシア諸語、例えば、Aceh語やMudurese語では、(データが不十分と断っているが)そのようなシステムの存在は発見できなかったと述べている。(前掲論文 p.2) Wolff 説の真偽の判定は、筆者の能力を超える課題である。 それはAN言語学者たちの将来の検討に任せ、本稿では、Wolff説を正しいものと仮定して以下の論考を展開する。 4.タガログ語における形容詞派生システムについて まずは、「AN祖語の形容詞派生システムを、ほぼ完全な形で継承している」(Wolff 説)というタガログ語の例を簡単に紹介しておく。 世界の諸言語を、形容詞が名詞に近いものと、動詞に近いものの2種類に分類できるとすれば、フィリピン諸語では、形容詞は動詞であると言える。 語例をいくつか挙げる。日本語に訳しづらいものもあって英訳を付けた。注)。
注) 語例と英訳のいくつかは、B. Evans & M. Ross の論文 " The History of Proto-Oceanic "ma" OCL Vol.40 No.2 (2001) に基づくが、筆者が Rubino の辞書を参照して付け加えたものもある。 語幹の語頭にアクセントが来る場合は、後ろにアクセントが移動すると、〜ed というような、受動態風の形容詞になる。 接頭辞の ma- が付くと、アクセントは移動せず、become 〜ed のような、「〜になった」(現在も〜である)という意味の状況を表わす動詞になる。 色の名称のような元々形容詞的な意味を持つ語幹は、最初からアクセントが後ろにあり、これに ma- が付くと、形容詞のままか、受動態風の形容詞になる。 辞書を見ると、 iti'm は「黒」という名詞でもあり、「黒い」という形容詞でもあり、ma-iti'm も形容詞とある。 ma を付けると、どういうニュアンスの違いが発生するかは、以下の例文を見ると、ある程度、雰囲気が分かると思う。
即ち、bilo'g は、「丸い」という月が本来的に持っている性質を表わすのに対し、ma-bi'log は、「自然推移的なプロセスの状態」を表現する。(puti の「白い」、ma-puti の「色褪せた」も参照) 筆者も細かいニュアンスは分からないが、おそらく、ma-iti'm は、「黒ずんだ」というような意味ではないかと思われる。 ma は、「家」や「火」のような純粋名詞(筆者の勝手な造語だが)にも接続し、"having 〜" という意味合いの形容詞になる。純粋名詞にアクセント移動が起きて形容詞が派生されることはない。このような ma の挙動は、日本語の接頭辞「ま」との比較において興味深いものがあるのだが、本稿ではこれ以上は立ち入らない。 タガログ語における用例をやや強引に、「感覚的に」まとめると、以下のようになる。
注) タガログ語の例からすると、「色の名称」は「本質的に形容詞的な名詞」という事になるが、では、「高さ」と「幅」はどうかと言われると、定まった判断基準はない。「属性名詞」も筆者が勝手に作った造語であるが、何がそれに属するかという明確な基準はない。「非純粋名詞」と言った方が良いかもしれない。 以下の日本語における語例分析に適用できるように、アクセント形を基に書き換えると、
という、機能とアクセントが異なるペアが派生されるという事になる。 単純に「日本語では形容詞が語頭低声調の傾向がある」というだけでは、それが、AN語起源である証拠としては弱い。しかし、上のようなアクセントと機能の異なるペアを発見できれば、日本語においてもタガログ語と類似したシステムが稼動していた可能性はずっと高くなる。 これで、準備が整った。 問題は、上の表に示したような語例を日本語に発見できるかどうかである。 更新記録: 2006年8月13日 初稿作成 2006年8月15日 タイプミス修正 |