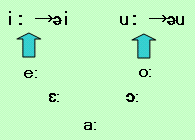�P�D�@�������ʌ��ꂩ�H
����Řb����Ă��錾�����{��̈�����Ƃ��邩�A�ʂ̌���Ƃ��邩�́A�w�҂ɂ���Ĉӌ����قȂ邻���ł��B����w�ł́A�݂��Ɉӎu�̑a�ʂ��s�\�ȂقLjقȂ�����̌���͈قȂ�����̌���ł���A�ƒ�`����܂����A�������A�ʌ��ꂩ�́A���́A����w�ł͂Ȃ��u�����v�Ō��܂�܂��B
���݂��Ɉӎu�̑a�ʂ��\�ȂقǗގ����Ă���̂ɁA���Ƃ��قȂ邽�߂ɕʌ���Ƃ���Ă���Ⴊ�������i�k���̌���Ȃǁj�A�݂��ɒʂ��Ȃ��قLjقȂ��Ă��Ă��A�������Ƃɑ����邪�̂ɁA�����Ƃ݂Ȃ���錾��i������Ȃǁj�̗�͐���������܂��B
�ӎu�̔�a�ʐ����Ȃ��ĈقȂ錾��Ƃ����`�ɏ]���ƁA����A��B�AB��C�̊Ԃł͒ʂ���̂ɁAA��C�ł͑a�ʂ�����ȏꍇ�AA��C���قȂ錾��ŁAB��A��C�̕����ƒ�`����鎖�ɂȂ�܂����A�Ⴆ��B�����V�A��̂悤�ȁu�L�͍��Ɓv�̌���ł���ꍇ�A���V�A����u�����v�Ƃ���w�҂́A�����A���Ȃ��ł��傤�B
�����̍e�ł́A����̌�����A�u�����v�Ƃ͊W�Ȃ��A�u������v�ƌĂ�ŕʂ̌���Ƃ��Ĉ������Ƃɂ��܂��B����́A���̍e�̖ړI���A����̌�����r����w�̑ΏۂƂ��Ĉ������Ƃɂ��邩��ł��B
�u������v���������ʂ̌��ꂩ�A��f�l�������I�ɔ��f����Ȃ�A���炩�ɕʂ̌���ł��B�ȉ��ɁA�̂��N���̉�b�̗�������܂����j�B
���j�@�����̕������͔��ɑ傫���̂ł����A�����Łu������v�Ƃ����ꍇ�A�{���u�����v���w�����̂Ƃ��܂��B
������F
�T���I
�C�����V�F�[�r�e�B�@�E���[���~�V�F�[�r���I
�k�[�V�F�[�@�����V�F�[�r�[�K���[�H
�i�}�[�@�E���W�~�V���[�`�A�C�����V�F�[�r����
��F
���߂����B
�悭���o�łɂȂ�܂����B�@�������ɂȂ��ĉ������B
����l�͂�������Ⴂ�܂����H
���͂��o�����ɂȂ��āA��������Ⴂ�܂���B
���̗������ƁA�����ꂪ���{��ƊW���錾��Ƃ͓���v���܂���B
�]�ˎ���̊w�҂��A������𒆍��ꂪ�a�������̂ƍl�����i�I�j�̂������͂���܂���B
���ǂ�ł��A���{��Ƃ̑Ή����S�R������܂���B���ꂾ������A�h�C�c��Ɖp��A�t�����X��Ɖp��̕�����قǎ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
���̉�b������߂Č������ɂ́A
�܁`�A�k�[�V�F�[�́A�u��v�i�ʂ��j���ȁH
�u�T���v�͂��������āA�u�����A�L��v�������肵�āH�H�H
���炢�����A�i�p�������Ȃ���j�A�v�����܂���ł����B
�u�C�����V�F�[�r�����v���A�Ȃ��u��������Ⴂ�܂���v�Ɠ����Ɣ���ł��邩�L�b�`���Ɨ�������ɂ́A���Ȃ�̗\���m�����K�v�ł��B���̌�`�ɂ��ẮA�ʃy�[�W�Ŏ�舵���܂��B�����̂�����͎Q�Ƃ��ĉ������B
����́A�܂��͂Ƃɂ����A�u���������v�ł��B
�Q�D�@���ꗿ���̃��j���[���u��ǁv����
�������X�s�����ꗿ���̂��X�œ��肵���u����v�����v�Ƒ肷��`���V�́A�����āi�ǂ��炪�\���s���ł����j�ɗ�����A���ɓ��{��ʼn��ꗿ���̃��j���[���L����Ă��āA�܂��ɁA�������ǂ́u���[�b�^�X�g�[���v�i���[�b�^�E�y�[�p�[�Ƃ����ׂ����H�j�ł��B
�܂��́A
�u�E�`�i�[ �X�o�v�F�@uchinaa suba
�Ƃ����P������グ�܂��B���̌�ɂ́A������Ɠ��{��̉��C�Ή��Ɋւ���G�b�Z���X���l�܂��Ă���̂ł��B
��̒P��́Aa, i, u �̂R�̕ꉹ���܂�ł��āA�@e, o ������܂��A����͋��R�ł͂Ȃ��A������ɂ́A�i�����Ƃ��āj�ꉹ���R�����Ȃ��̂ł��B
���C�Ή��P�F
| ���{�� |
a |
i |
u |
e |
o |
| ������ |
a |
i |
u |
i |
u |
���A�܂��ŏ��ɒm��Ȃ�������Ȃ��ł���{�ƂȂ鉹�C�Ή��ł��B���̋K�����u�E�`�i�[�X�o�v�ɓK�p����ƁAu ,i �͓��{��� o, e �ɑΉ�����\��������̂ŁA
uchinaa suba�@�� o(u)chi(e)naa �@so(u)ba
�ƂȂ�܂��B�㔼��suba �́Asoba �̉\��������A����́A���{��́u�����v�ɑΉ��������ł��B�������A���ꗿ�����ɂ�����t�B�[���h���[�N�i���n�����j�ɂ��ƁA�u�X�o�v�͊֓��l�̌�b�ł́A�u���[�����v�ł��B�������Â��L�^�ɂ��A���āu���[�����v�́u�V�i�\�o�v�Ƃ��Ă�Ă������Ƃ�����Asuba �́A���{��́u�\�o�v�Ɠ����ƒf�肵�ĊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�ł́A�O���́@uchinaa�@�͂ǂ����H
�����ő��̉��C�Ή��A
���o�ꂵ�܂��Bki����chi�ւ̕ω����u���W���v�ƌĂ����Ɉ�ʓI�ȉ��ω��ł��B���{��ł��A�^�s��ti�� chi�Ɣ�������܂�������́A�O��ꉹ�@i �̉e���ŁAt-�̒����_���Y���āAch �ɂȂ����̂ł��B��ˎ����́u�u���b�N�W���b�N�v�ɏo�Ă���s�m�R�́u�ǁ[���āv���u�ǁ[���āv�ƌ����܂����A��������W���̗�ł��B
�]���āAuchinaa�@�́A
uchinaa�@���@ okinaa
�ł���\�����o�Ă��܂��B�����܂ŗ���A okinaa�@���A�u����v�ł���\���������ė���̂ł����A��r����w�Ƃ����w��́A�����Ȋw��ŁA�Ō�̕ꉹ���Ȃ����ꉹ�Ȃ̂��������ł��Ȃ��ƃ_���Ȃ̂ł��B
������u�E�`�i�[�v�̍č\�`�@�@okinaa
���{��u����v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ okinawa
���r����ƁA�������-aa-�@�ɁA���{���-awa- ���Ή����Ă��鎖��������܂��B���{��́u��v(kao)�̌Ì`���Akawo �A�u�L�v(kai)�̌Ì`���Akahi < kapi �ɑk�鎖���l����ƁA�ꉹ�ɋ��܂ꂽ�Aw ���邢�́@h �i������� ���{�c�� p�ɑk��܂��j�������������Ƃ�������܂����A����Ɨގ��������ۂ�������ł��������̂ł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B
���{��ł́Akawa �̂悤�ɁA����a �ŋ��܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A���͏����Ȃ������̂ł����A������ł́A�ꉹ�ŋ��܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A���ׂĂ����������Ă��܂����̂ł��B
�����A��O�̉��C�ω�
�����肳��A����Ń��f�^�N�A
uchinaa�@���@ okinawa
�Ɗ��S�ȑΉ����������܂��B
�u�E�`�i�[�@�X�o�v�͐��m�ɁA�����ɁA���{��u����\�o�v�ɑΉ����܂��B
������ł͕ꉹ�ɋ��܂ꂽ�������ׂď����Ă��܂����̂ł����A���̑���Ɂu�E�`�i�[�v�̂悤�Ȓ��ꉹ�������܂����B���{��́u���v�͗�����ł�
�E�`�i�iuchina) �ɉ��C�ω�����n�Y�ł����A�E�`�i�[�ƃE�`�i�ł͑S���قȂ�Ӗ���L����悤�ɂȂ郏�P�ł��B������ł͂̒����̋�ʂ͔��ɏd�v�ł��B
����A���{��ł̓I�L�i�[�Ɖ������������Ă��I�L�i�ł��Ӗ��͕ς��܂���B��ʂɓ��{��ł͒��ꉹ�ƒZ�ꉹ�̍��͈Ӗ��ٕ̕ʂɂ͖��W�ł��B������ł͈ꌩ���C���ȒP�������悤�Ɍ�����̂ł����A���̑㏞�Ƃ��ĉ����ʂ̗v�f������邱�Ƃɂ���Č�ٕ̕ʂ��Ȃ������̂Ȃ̂ł��B
�R�D�@�ʓ˂��Փ˂Ő����鉹�C�ω��ɂ���
���̂܂����C�Ή��̗�������Ă����A���ꗿ���̃��j���[���u��ǁv�ł���n�Y�Ȃ̂ł����A�������������̎d���́A���̖{�ӂł͂Ȃ��̂ł��B
���̍e�̖ړI�́A�������j���[��ǂނ��Ƃł͂Ȃ��A�����܂ŗ��j����w�i���邢�͔�r����w�j�Ƃ����w��̍l�������Љ�邱�Ƃɂ���܂��B
�����Řb�����h�[���Ƒ傫���U��܂��B
���́A����w�Ƃ����w��́u�Ȋw�v�ł���ƐM���Ă��܂��B�ł́u�Ȋw�v�Ƃ͂ǂ������w�₩�ƌ����A�ꌩ���G�Ɍ����錻�ۂ�����ʓI�ŊȒP�Ȗ@���ɊҌ����Đ������鎎�݂ł���ƁA���͍l���܂��B
���C�Ή�����������ł́A�u�����w�v���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
���A��X�������Ă���e�[�}�ɂ��Č����ƁA����́u��������L�̉��C�ω���I�ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����H�v�Ɩ₤���Ƃł��B
�ēx�A��ɏq�ׂ�������̉��C�ω��������܂��B�i���̏����́A���{��E������ŋ��ʂȂ̂ł����ł͖������܂��B�j
|
�P |
�Q |
�R |
| ���{�� |
e |
o |
ki |
| ������ |
i |
u |
chi |
�ŏ��̂Q�́A�ꉹ�Ɋւ�����̂ŁA�R�Ԗڂ͎q���̕ω��ł��B�����̕ω����ǂ��u����I�Ɂv�W�t�����炢���̂ł��傤���H
�����ŁA�ꉹ�̕��ނɂ��Đ�������K�v������܂��B���{��̂T�̕ꉹ���A�������鎞�̐�̈ʒu�ŕ��ނ���Ɖ��̕\�̂悤�ɂȂ�܂��B
|
�O�� |
���� |
��� |
| ���� |
i |
|
u |
| ���� |
e |
|
o |
| ���� |
|
a |
|
������ł́Ae��o �����ꂼ��@i,u �ɕω��������P�ł����A����́A�u�����̍��������ʂ̕ꉹ���A�Ƃ��ɁA���㉻�����v�ƕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�ȁA�����ʒu������ꉹ�ɕω�����悤�ȉ��C�ω����u���㉻�v raising �ƌĂ�A���E�̌���ł��悭����ω��Ȃ̂ł��B
�u������\�����������ł͂Ȃ����v�ƌ��������܂łł����A��̂P�ƂQ�̕ω����A�����w�I�ɋ��ʂ����ω��ł��邱�Ƃ�������܂��B
���āA���̂悤�ȉ��̕ω����N�����ꍇ�Aki��ke�A������ko��ku���������ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ⴆ�A�u��v�itaki�j �Ɓu�|�v�itake�j ������taki�ƂȂ��Ă��܂��A�P��̋�ʂ����ɂ����Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����ŁA��̕\�̎O�Ԗڂ̉��C�ω����v���o���ĉ������Bki��chi�ɕω����Ă��܂��B�܂�Ake ���u���㉻�v�ɂ���ĉ�����オ���Ă����̂ŁA�����炠���� ki���A�Փ˂�����邽�߂ɁAchi�Ɏp��ς��āi�܂�q�������W�����āj���������̒P�ꂪ�����Ă��܂��̂�������ꂽ�̂ł��B
���̍l�����������Ƃ���A�J�s�ȊO�ł����W�����������Ă���n�Y�ł��B���ہA���{��́u�Z�v(se)�ɂ́A������́u�V�v(si)���Ή�����̂ɑ��A���{��́u�V�v(si)�ɂ́A������́u�V�B�v(shi)���Ή����܂��B
| ���{�� |
e |
i |
ke |
ki |
se |
si |
| ������ |
i |
i |
ki |
chi |
si |
shi |
��̕\������ƁAke, se ���@ki, si �ɕω��������߂ɁA�����炠���� ki, si
�����W�������������Ď���Ǝv���܂��B
|
�O |
�� |
�� |
|
| �� |
i�� |
ï |
u |
|
| �� |
e�� |
|
o |
|
| �� |
|
a |
|
|
����������ł��A�����ɂ���ẮA�قȂ�u�Փˉ����v���̗p����܂����B�Ⴆ�A��p�߂��̔��d�R�E�{�Õ����ł́A���}�̂悤�ɏオ���ė���
e ������邽�߂� i ������ꉹ�ɕω����܂����B
����ł́Aku �͂ǂ��Ȃ������H
�u���W���v�Ƃ������ۂ́A�����w�I�Ɂi�q���{�O��ꉹ�j�Ƃ����g�ݍ��킹�łȂ��Ɣ������Ȃ��̂ŁAku �ɂ͓����ꂪ����܂���ł����B�Ƃ������P�ŁA���{��́u�_�v(kumo)�Ɨ�����́@kumu�@�̑Ή��Ɍ�����悤�ɁAku �͉��ω������ɂ��̏�ɗ��܂�܂����B�i�L�C��kh�ɕω���������������܂����B�j
�ȏオ�A�u������ɋN�������C�ω���I�ɗ������鎖�v�̒��g�ł��B�ʔ����Ǝv���l�͖ʔ����ł��傤�B���͖ʔ����Ǝv���܂��B����͂��̂悤�ɁA�K���I�ŃV�X�e�}�e�B�b�N�ȕω������������ŁA���d�R�E�{�Õ����̂悤�ɑ��l�ő��ʂȕω������o���čs�����̂Ȃ̂ł��B
�ꉹ�̕ω��iraising)���L�b�J�P�Ƃ��āA�q���i�����ɂ���Ă͕ꉹ���j�̕ω��������N�����ꂽ�̂ŁA�����������C�ω����A�A������(chain shift)�ƌĂ�܂��B����������A�u�ʓ˂����C�ω��v�Ɩ��t�������Ƃ���ł��B
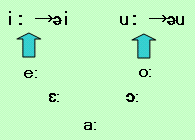 |
|
|
|
���j����w��A�ꉹ��Chain Shift�ŗL���Ȃ͉̂p��ł��B�����p��̒��ꉹ���A���������̑�ω��𐋂��܂����B���̈�A�̕ω��́u��ꉹ���ځv(Great
Vowel Shift)�ƌĂ�Ă��܂��B
�����p��̒��ꉹ�́A���}�̂悤�ɁA�V�ꉹ���L���C�ɔz�Ă����̂ł����Ai: �Ɓ@u: �������s���ȗ��R�ɂ���āA��d�ꉹ�ɕω����Ă��܂������߂ɁA�ɂȂ�������ꉹ�̈ʒu�߂悤�ƁA�Ⴂ�ʒu�ɂ������ꉹ���A���I�Ɏ��X�ƍ��㉻���܂������j�B
pine �� feet �̂悤�ɁA�X�y�����O�Ɣ������Ή����Ȃ��P�ꂪ������������܂����A����͎�Ƃ��āA��ꉹ���ڂ������ł��Bfeet �́A�����ɂ����Ă͒Ԃ�ʂ�A�u�t�F�[�g�v�Ɣ�������Ă����̂ł����A����p��Łu�t�B�[�g�v�Ɣ��������̂́A��̐}�Ɏ������悤�ɁAe: �́Araising ���N�������߂ł��B
���j�@�A���V�t�g�ɂ́A��ꉹ���ڂ̂悤�ɁA�g���K�[�ƂȂ鉹�ω��ɂ���Đ����̈�߂悤�Ɖ����ω�����^�C�v�̂��́idrag shift)�ƁA������Ő������悤�ȁA���ω��ɉ�����Ď��̕ω���������^�C�v(push shift)�̃t�^�c�̃^�C�v������܂��B�����u�ʓ˂��^�v�ƌ����̂́A��҂�push shift
�ɑΉ����܂��B
�ł́A��ꉹ���ڂ���ɐ��������悤�ȒP���� drag shift �ƌ��Ȃ���邩�ƌ����ƁA�ǂ��������ł͂Ȃ������Ȃ̂ł��B��ꉹ���ڂɐ��ޕs���Ȍ��ۂ̈�[�ɂ��ẮA�ubreak
�Ɓ@meat �̕ꉹ�͂Ȃ��قȂ�̂��H�v�Ƃ����L�����������̂ŎQ�Ƃ��ĉ������B
�R�D�@�u����炳��v�����j����w
�����ł��̍e���I���ɂ��悤�Ǝv�����̂ł����A�薼���u�w����炳��x�̗��j����w�v�����������v���o���܂����B
�m�g�j�̃h���}�̂������ŁA�u����炳��v���u���l�v���Ӗ����问����ł��鎖�́A�L���i�H�j�m���鎖�ɂȂ�܂������A�����ł��������A���܂œ����m�������ɁA���̌�̗��j����w�I���͂����s���Ă݂܂��傤�B
�㔼�́u�T���v�́A��������L�̌`�e������ŁA�u�T�L��v�ɑk��Ƃ���Ă���̂ł����Asa-ari ���Ȃ� san(g) �ɕω��������́A���́A���͗ǂ�������Ȃ��̂Łi����͑����A�㋉�҂ɑ����܂��j�A�����ł́A�ꊲ�́u�`�����v�ɂ��čl���܂��B
�u�`�����v�@���@chyura
�ƃ��[�}���\�L���鎖�ɂ��܂��B
ch- �Ƃ����u���W�����v�́A��ɏq�ׂ��悤�ɁAchi ���甭�������n�Y�ŁA����́A���{��́@ki �ɑΉ�����Ɛ��肳��܂��B�܂��A������� u �����{��� o �ɑΉ�����\�����l�����Č��^���č\����ƁA
chyura �� kiyura �� kiyora
�ƂȂ�A�u�L�����v�Ȃ��`�������яオ���ė��܂��B��r����w������Ėʔ����̂́A���̏u�Ԃł��B�݂̍肩�������ꂽ�閧�̕������ł��Ԃ����玚�������яオ���ė����A����ȋC���ɂȂ�܂��B�i���ƃI�[�o�[���B�j
�u�L�����v�͂����Ɓu���炩�v�ł���ɈႢ����܂���B����́A���ē��{��ł͐��A�������C�ł��邱�Ƃ��Ӗ������ł������A������ɂ�����Ӗ��u�������v�Ƃ͈قȂ��Ă��܂��B
�����ŌÌꎫ�T�ׂĂ݂܂��B�u��g�Ìꎫ�T�v�ɂ��A
�����F�@�u��ꗬ�̋C�i������A�ؗ킳�A�Ҕ��������v�Ƃ���A�u�@ �C�������Ĕ��������܁v�Ƒ����܂��B
�Ȃ�ƁA�u���炩�v�Ƃ����̂́A�u�����q�v��A�u�|�敨��v�A�u��������v�i�p��̏o�T�����ł��j�́A��ƂȂ��A�݂�т̎���ɂ́A�S�[�W���X�ŃA�[�o�����m�[�u���Ȕ���\�����錾�t�������̂ł��I
���Ƃ���ƁA�������q���u����炳��v�ƌĂԂ̂͂�����ƃC���[�W�I�ɈႤ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B�ޏ������l�ł��鎖��ے�͂��܂��A�ǂ��炩�ƌ����A�u�ؗ�E�Ҕ��v�u�C�������Ĕ������v�Ƃ������́A�ߐ����{��́u���炩�v�̃^�C�v���Ǝv���܂��i���Ȃ��Ƃ��h���}�ł́B�j�B
����͂Ƃ������A���{�����������ɁA��������I���W�i���̈Ӗ����A��萳�m�Ɍp������Ă��鎖�ɂȂ�̂ł��B
���{��ɂ́A����Łu�����v�Ƃ����`�e��������܂����B������́A�u����ʼn���E�����肪�Ȃ��A�]�v�ȉ��҂��Ȃ��ӁB�����A���C�œ����̈ӁB�v�Ƃ���܂��i�p��̏o�T�͖��t�W�j�B�����A�u���炩�v�́u�����v�ɋz���E��������ăI���W�i���̈Ӗ��������Ă��܂������̂Ɛ��肳��܂��B
�X�Ɉ���ł́A�u�����v�Ƃ����ꂪ�����āA������ǂނƁA�u�����ɂȂ��ăL�������g���Ȃ��Ȃ�ɏ]���A�i���̌ꂪ�j��ʓI���Y�킳�������v�悤�ɂȂ����A�Ƃ���܂��B
�u�����v�u����v�u�����v�A�����R�̌�b�̈Ӗ��̕ϑJ��H��ƁA�����A���̕\�̂悤�ɂȂ���̂Ǝv���܂��B����w�Ō����������ǂ̎�����w���̂��m��Ȃ��̂ł����A���Ɏ�������Ƃ��Ă����܂����B
| ��b |
�ޗǎ��� |
�������� |
�����i�����H�j |
���a�O�� |
���� |
| ���� |
����E���C |
�� |
�� |
�� |
�قƂ��
���� |
| ���� |
�H |
����(�M���I�j |
����E���C |
�� |
���� |
| ���� |
�H |
�Y��i�����I�j |
�� |
���� |
���� |
���̕\����A�u����炳��v��������ɓo�ꂵ���N����G�c�ɐ��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�����A���ꂪ��������̂��Ƃł������Ƃ���A�u����v�́A���Ɂu�����v�ɍ�������āu����E���C�v�̈Ӗ��ɂȂ��Ă����̂ŁA�u����炳��v���u���l�v�̈Ӗ��ł��鎖�Ɩ������܂��B
�]���āA�u����炳��v�a���̔N��́A�������ォ�玺������(?)�̊Ԃł���Ɛ��肳��܂��B�����A�u����炳��v�ł͂Ȃ��u���ガ����v�������Ƃ�����A����́u�����v�ɑΉ�����̂�(kiyoge
> chiyugi > chugi)�A�N��̓���͍�������ł��傤�B
���̂悤�ɁA������ɂ͏��Ȃ��Ƃ���������ɑk��A�Â�����̓��{�ꂪ�ۑ�����Ă���̂ŁA���{��̋N�����l���鎞�ɂ́A���̌�������Ă͂����Ȃ��̂ł��B
�u������E������v�Ə̂��āA�����������t�́A�u�E�`�i�[�X�o�v�Ɓu����炳��v�����ł������A������Ɠ��{��̊W���ǂ��𖾂��ꂽ���ɂ��Ă̊�{�������������ł��B
�`���ɏЉ���A�u�C�����V�F�[�r�����v�i��F�@��������Ⴂ�܂���j���A�ǂ������ϑJ��H���Đ����������A����͂����Ɠ���ł��B
�ʍ��L��
�u�ꉹ�ω��̗��j�v
�ŁA���̌�`�̕��͂����݂܂��B�����̂�����́A�Q�Ƃ��ĉ������B
�Q�l�����F
������E���{��֘A�@�Q��
�{�e�œ��ɎQ�l�ɂ����̂́A�ȉ��̕����ł��B950�y�[�W�قǂ̑咘�ŁA��قǂ̐���҂łȂ��ƁA�ǂ�ł��`�b�g���ʔ����{�ł͂���܂���B
| JP-8 |
���{���q |
���{����j�̌����@�i1990�j�@��C�ُ��X |
�X�V�L�^�F�@
���e�@�Q�O�O�S�N�S���Q�X���@�쐬
���e�@2004�N�V���Q�S���@��ꉹ���ڂ̍��ɒ���NjL
�t�^�F
���ꗿ�����œ��肵���`���V���A�������g�킸�ɉ�ǂ��悤�Ǝ��݂��̂ł����A����ł��`�I
�X�[���`�@�E�`�i�[���@�k�`�O�X�C�@���k�f�B�@�C�C�l�H
�E�`�i�[�`���K�@�J�������k���@�A���V�J���@�N���V�J���@�T���O�g�D�@�h�D�[���J�C
�}�V�����f�B�`�E���e�B�@�k�[���e�B���@�J���O�g�D�@�W�b�R�[�@�W���[�g�D�@�����o�[�@�J�T�I�I
�Ƃ���������̕��͂ł��B
��̕��͂���ǂ��鎎�݂ɂ��ẮA������ց@�C�����V�F�[�r���I
|