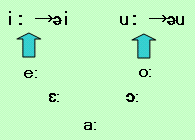| Break と Meat の母音の発音はなぜ異なるのか? |
(2004 7月)
|
(音韻法則の破綻について)
break の発音は「ブレイク」 meat は「ミート」と発音されます。-ea- という綴りは同じなのに、発音が違う。中学生になって始めて英語を勉強した時、「なんでだろう?」と疑問を抱いた人も多いでしょう。素朴な疑問ですが、実はこれは、長年にわたり言語学者を苦しめ続けた難問だった事を、最近になって知りました。
答えの手がかりが得られ始めたのは、なんと1960年台も末になってからです。この問題の解明によって、19世紀に確立したと思われた歴史言語学の基本テーゼ、「音韻変化に例外なし」は、破綻しました。
「中学生レベルの素朴な疑問」に対し、「それは、そういうものなんだ。覚えるしかない事なんだ。」と決めつけてはいけないのです。特にそれが言語に関するものである場合には。
1. 大母音推移について
この疑問が言語学的にどういう意義を有しているか知るためには、少しばかり予備知識が必要です。
前に、「ちゅらさん」の歴史言語学」(琉球語超入門)と言う記事を書いたのですが、その中で、中世から近世英語に生じた、大母音推移(Great
Vowel Shift)という現象についてチラリと触れました。これは、英語の7つの長母音に起きた「連鎖シフト」の例です。簡単に復習します。
左図は、それぞれの母音が発音される時の舌の位置を示します。左上が「前舌・高舌」、右下が「後舌・低舌」の母音であることを示します。
大母音推移は、まず、高舌母音のi:とu: が、どういうワケか2重母音に変化した所から始まりました。それらの母音が無くなってしまった穴を埋めようと、それぞれの母音が高舌母音に次々と変化していきました。
問題のmeat とbreak ですが、15世紀から16世紀初めには、母音が共に[ε:]という発音だった事が確認されています。(当時の発音をどうやって知るかというと、古代中国語の音韻の推定と同じ要領で、主に詩や韻文、駄洒落などから、どの単語が韻を踏んでいたかを調べて音を推定するのです。)
meat は、やがて、meet[me:t] と発音が合流し、最終的に [mi:t]となったワケですが、これは、大母音推移のために、発音の際の舌の位置が高くなっていった過程と説明できます。綴りがmeet
(「メート」)なのに「ミート」と発音されるのは、大母音推移により発音が変化したのに綴りが変わらなかったからです。
関係する単語の発音の推移を下の表にまとめます。
| 語(母音) |
16世紀 |
17世紀 |
現代 |
| meet [e:] |
→ |
融合 [i:] |
[i:] |
| meat [ε:] |
→ |
融合 [ε:] |
分離→ |
| break [ε:] |
→ |
→ |
→ |
[ei] |
| mate [a:] |
→ |
冒頭の「素朴な疑問」を、こうした英語の音韻変化史を踏まえて歴史言語学上の問題として言い換えると、以下のようになります。
16世紀初めには、meat/break/mate の母音が同じ[ε:]だったのに、17世紀以降、meatとbreak
は異なった音韻推移を辿った。meatはmeetと融合し、breakはmateと融合したまま別の音韻変化を遂げて[ei]
になった。同じ音韻[ε:]から出発しながら、異なった音韻に変化した事は、歴史言語学の基本法則 「音韻推移は規則的である」に反する。
breakと同じ変化を辿った語に、great があります。もしかして、-ea- の前にr があると異なった音韻変化を示すのでしょうか? しかし、steakも[ei]ですし、breach (違反する)は[i:]なので、この考えはうまく行きません。歴史言語学の「基本法則」は、「例外的な音韻変化は説明可能である」とも主張するのですが、この音韻変化はどーしても説明不能なのです。
2. 不思議な音韻変化の発見について
この謎は、長い間、言語学者を苦しめ続けました。解明の手がかりは、1960年代のアメリカで見付かりました。
フィラデルフィアで方言の調査を行なっていた社会言語学者は、標準英語のmad
[mæd]が、[me: d]と発音される現象について調べていました。このような音韻変化が起きている語を調べてみると、mad
/bad/ glad /man/ hamではこのような変化が起きているのに、同じ母音を有するハズのsad/
dad/ cab/ ran/ hammockなどには、このような変化が見られず、標準語と同じ発音[æ]が保持されている事が分りました。 d]と発音される現象について調べていました。このような音韻変化が起きている語を調べてみると、mad
/bad/ glad /man/ hamではこのような変化が起きているのに、同じ母音を有するハズのsad/
dad/ cab/ ran/ hammockなどには、このような変化が見られず、標準語と同じ発音[æ]が保持されている事が分りました。
このような例は、一旦発見されるとゾクゾクと見つかりましたが、このような音韻変化は、従来の歴史言語学では全く取上げられて来なかったタイプのものなのです。
19世紀に主張された音韻推移則では、
- 音韻変化は、緩慢に進行するので、同時代の人間にとってはそのような変化を認識する事ができない。
- 音韻変化はすべての語彙で同時に進行する。
と仮定していました。
日本語の例で言えば、「ハ行音の変化」が上のようなタイプの音韻推移に対応します。
「ハ音」は、Pa → Fa(厳密にはΦa) → Wa → Ha
という変化を辿って来たと考えられていますが、これは、「発音の際に唇を使わなくなる」という長く一貫して(千年以上)続いた大きな流れの結果発生したものです。
このような音韻変化が起きた場合には、kapa(河・皮)もkupa(鍬)も、pada(肌)も、pana(花・鼻)も、一斉に同じ音韻変化を受けました。なぜなら、pa の発音の仕方自体が変化したので、ある単語だけがこの変化を受けずに留まる事は不可能だからです。金田一春彦氏の譬えで言えば「同じ電車に乗っている乗客がすべて同じ方向に移動するのと同じ事」です。
しかし、フィラデルフィアで発見されたようなタイプの音韻変化は、
- 変化前の音韻に対し、不連続的(あるいは跳躍的)である。
- この音韻変化は、すべての語彙に同時には作用しないが、変化が適用される語彙の数は次第に増加する。
- 変化がある時点で停止し、変化を免れる語が残る。
という特徴を備えている事が判明しました。
beak/great がなぜ、meatと違う発音になったのか、これは多分、フィラデルフィアで発見されたと同じタイプの音韻変化が生じたためだろうと言うのが、現在の定説(多分)になっています。
2の過程で起きる変化を「語彙拡散」(lexical diffusion)、変化を免れた語を「残留語」(residue)と呼びます。(用語の日本語訳は、今、私が勝手に付けたので正式な訳語は知りませんので悪しからず。)
この仮説が正しいとすると、 [ε:]を有する語が、[e:]にジワジワーと、長い時間を懸けて一斉に変化したのではなく、1年前は、meat が、今年はbeatが、というように、各単語の母音がバラバラに、しかも突然に、[ε:] から[e:]へ変化した事になります。そして、break/ great /steakはこの変化から取り残された残留語であると解釈されます。
どの語が変化して、どの語が変化しないのか、その選択がどう為されるか説明できる理論は、私の知る限りでは、まだありません。
とにかく、このlexical diffusionの発見により、19世紀の比較言語学の金字塔、「音韻変化に例外なし」のテーゼは、崩壊しました。とは言っても「音韻対応」の有効性が歴史言語学において喪失したワケではなく、「音韻変化に一部の例外あり」と書き替えるべきだ、という事なのです。
3.いわゆる「ら抜き言葉」との類似について
日本語で語彙拡散に似たタイプの語形変化があるかと言うと、いわゆる「ら抜き言葉」の挙動がこれに良く似ています注)。俗に「ら抜き言葉」と言いますが、言語学の観点からすると、「食べれる」「来れる」「やめれる」「見れる」などが「ら」の脱落によって生じたと考えるのは誤りです。
可能を表現する有力な動詞形として、「書ける」「行ける」「飲める」といった「正しいラ抜き形」が存在するワケですが、「新参のラ抜き形」は、「正しいラ抜き形」を真似る事によって活用形を単純化・統一化させようとする変化、言語学で「類推」(analogy)あるいは「平準化」(leveling)と呼ばれるタイプの語変化であると解釈されます。
ちなみに: 「ら抜き言葉はけしからん!」という規範圧力があまりに強くなり、可能を表わす表現として、例えば「書けられる」などというような語形が登場した場合、これを「過剰修正」(hypercorrection)と言います。)
活用形態の単純化は、古今東西、あらゆる言語で起きたことで、私自身は「ら抜き言葉」を単純に「言葉の乱れ」と断罪するのは誤りだと思います。
個人的には「やめれない」には説明不可能な違和感を感じます。つまり、私の頭の中では、この語形変化による、語彙拡散(lexical
diffusion)が進行中で、なぜ「やめられない」がやめれないのか説明不能で、私にとっては「やめられない」が残留語(residue)であるという事になります。
私としては、この変化が今後どのような経緯を辿るかに興味を覚えます。もし、この変化が、語彙拡散と同じタイプのものだとすれば、「ら抜き形」が適用される動詞の数は今後も増加して行くと予想されます。
しかし、一方で、break/greatが音韻変化を免れて「ブリーク」や「グリート」に変化しなかったのと同じように、たとえ百年たっても「ら抜き形」に吸収されずに「・・られる」という語形を保存する動詞が残るハズなのです。残念ながら、どの動詞が変化を生き残るかは予測できないし、私自身がそれを確認できる可能性はありませんが。
注) 上の議論は「類推」(analogy)という言語現象も、語彙拡散の一種と見なせるのではないかという「類推」によるもので、私の「思いつき」です。
To be continued ?
こうして「break/great がなぜ、meatと違う発音になったのか?」という疑問は解決されたかのように思えます。しかし、疑問の解決は、また新たな謎を産みます。
古典的な音韻推移則を「NG(ネオ・グラマリアン)型」、新しい音韻変化を「LD(語彙拡散)型」と仮に名づけることにします。それでは、どういう変化の際に、どちらのタイプの音韻変化が生じるのかが問題になります。
現在のところ、
1. 不連続的な変化の場合はLD型
2. 連続的かつ緩慢な変化の場合はNG型
の音韻変化が生じるという事になっています。
bad が[be :d になる、あるいは「ら抜き型か否か」は明らかに1に属する変化ですし、古代日本語から現代日本語にかけての
pa > Fa > wa > haは、2に属するという事で、確かに辻褄は合っているとは思われます。 :d になる、あるいは「ら抜き型か否か」は明らかに1に属する変化ですし、古代日本語から現代日本語にかけての
pa > Fa > wa > haは、2に属するという事で、確かに辻褄は合っているとは思われます。
しかし、[ε:] > [e:] の変化が本当にLD型の挙動を示したと実証できるかについて、疑問が残ります。そもそも思い起こすと、大母音推移が起きたのは、i: と u: がそれぞれ、 i, i,  u に変化した事から始まったワケですが、この変化自体が不連続変化ぽい。フィラデルフィアで起きた変化に似ていないでもない。だとすると大母音推移のトリガーとなったのもLD型変化という事になる。 u に変化した事から始まったワケですが、この変化自体が不連続変化ぽい。フィラデルフィアで起きた変化に似ていないでもない。だとすると大母音推移のトリガーとなったのもLD型変化という事になる。
それでは大母音推移で起きた変化すべてがLD型音韻推移とみなせるのかと、おおいに疑問と興味が沸く所です。(こういう事を論じた論文が一杯出ていて専門家には周知の定説が出来ているのかもしれませんが、さすがにそこまでは手が回りません。)
最後に、上の考え方を日本祖語で発生したと推定される音変化に適用するとどうなるか考えてみます。日本祖語で生じた事が明らかな音韻変化のヒトツに、語頭の有声子音(濁音)の無声化があります。
このHPで良く上げる例ですが、オーストロネシア語から日本祖語が誕生する際に、
花: baŋa > pana (b > p)
という音韻変化が起きたと考えられます(関連記事参照)。
古代日本語は語頭子音に有声音(濁音)が来ないという顕著な特徴を備えていました。漢語・カタカナ語を除くと、現代日本語においてすら、濁音で始まる語はほとんどが否定的な意味を持っています。これは日本語は濁音が先頭に来る語を嫌うという「伝統」の痕跡です。
有声音から無声音への変化は不連続変化とみなされるので注)、上のリクツから言えばLD型になるハズです。すると、残留語が存在するハズという事になりますが、それは多分、文献的には実証できないように思われます。(有声音が語頭に立たないという言語は他にいくらでもありますが、有声音の残留語があるという話しは聞いた事がありません。)このような変化の場合には、残留語が生じる余地がないほど急激な変化が起きるという事なのでしょうか?
有声音から無声音への音韻変化をどう扱うか、スッキリした理論はないように思われます。
いずれにしても、まだまだ、音韻変化は謎です。
注)音韻論で言う[+voiced]/[-voiced]という標識が本当にデジタルな属性であると断言できるのかは不勉強にして分かりませんが、「12%有声化音」などというものがあるとも思えません。
|
 |
|
参考文献
| R. L. Trask |
Historical Linguistics (1996) Oxford University Press |
| A. MacMahon |
Understanding Language Change (1994) Cambridge |
更新記録:
1. 2004/07/13
|