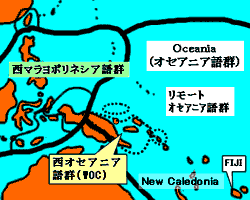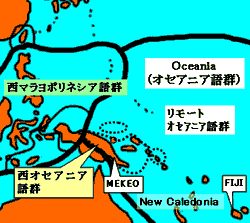崱夞偼嵞傃愙摢帿偵娭偟偰榑偠傞丅偟偐偟丄側偤暃戣偑乽愙旜帿偺婲尮乿側傫偩偲巚傢傟傞偐傕偟傟側偄偑丄偦傟偼杮暥傪尒偰偺偍桖偟傒偱偁傞丅崱夞偼杮榑偵撍擖偡傞慜偺尐姷傜偟偲棟榑晅偗傪帋傒偨偺偩偑丄惉岟偟偨偲偼尵偊側偄偐傕偟傟側偄丅 侾丏 慜峞偺暅廗 嶐擭(2006擭乯偼丄侾侾寧偐傜擭枛偵偐偗偰報墷斾妑尵岅妛偺朸摿掕僥乕儅拲乯傗朸僪儔儅偵僴儅僢偨傝丄杮嬈偑傗偨傜偵朲偟偐偭偨傝偟偰俀働寧峏怴傪僒儃僢偰偟傑偭偨丅傗偼傝丄偟偽傜偔婰帠傪彂偐側偄偱偄偨偣偄偐榬乮摢丠乯偑僫儅偭偰偟傑偭偨丅昅幰偺儕僴價儕傪寭偹偰丄傑偢偼慜峞偺暅廗偐傜擖傞帠偵偡傞丅斚傢偟偄偲巚傢傟傞曽偼丄旘偽偟偰捀偒偨偄丅 拲乯丂報墷慶岅偵尰傟傞挿曣壒乮偄傢備傞墑挿奒掤乯偑杮尮揑側傕偺偐偳偆偐偲偄偆栤戣丅恄嶳岶晇巵偺乽報墷慶岅偺曣壒慻怐乿偲偄偆杮傪撉傫偱偙偺栤戣偵偡偭偐傝僴儅僢偰偟傑偭偨丅寢嬊丄徚壔晄椙偱曻偭偰偁傞丅乮傗偼傝慺恖偱偼婎慴抦幆偑懌傝側偄両乯 慜峞偱昅幰偑峫嶡偟偨偺偼丄屆戙擔杮岅偵偍偗傞丂(俀抜摦帉楢梡宍)亖(岅姴)亄i 丂偲偄偆宍懺偑丄 (俙俶慶岅岅姴) + (俙俶慶岅愙帿 "i" ) 偐傜惗偠偨偲峫偊傞帠偑偱偒傞偐斲偐丄偲偄偆栤戣偱偁傞丅 椺偊偽丄*at'at (愺偄帠乯偺応崌拲乯丄偙傟偵愙帿丂"i" 偑愙懕偡傞偲丄asati 偱丄屆戙擔杮岅偺 ase2 偵偼側傜側偄丅asati > asai 偺傛偆側岅拞偺 t 偑徚幐偡傞壒塁曄壔傪憐掕偡傞偺偼丄傑偢晄壜擻偱偁傞丅廬偭偰忋偺憐掕偼娙扨偵斲掕偝傟傞偐偵尒偊傞丅 拲乯丂/t' /偼僨儞僾僂僅儖僼偑愝掕偟偨壒塁偱丄ty 偺傛偆側壒丅尰嵼偺掕愢偱偼丄t' 偱側偔 s 偲昞婰偝傟傞偑丄杮摉偵[s] 偲偄偆壒偩偭偨偐偵偮偄偰偼斀榑傕偁傞丅 堦曽丄懞嶳偼丄*at'at 偑偄偭偨傫丄岅枛巕壒傪幐偭偰 *at'at > asa 偲奐壒愡壔偟偨屻偵丄僣儞僌乕僗婲尮偺柤帉壔愙帿丂"i" 偑愙懕偟偰丄asai > ase2 偵側偭偨偲峫偊偨丅懞嶳愢偱偼丄奐壒愡壔偟偨僣儞僌乕僗揑尵岅偺扴偄庤偑丄戝検偵俙俶岅岅渂傪庁梡偟偰尨巒擔杮岅偑惗偠偨偲峫偊傞丅堦尒丄傕偭偲傕傜偟偔巚偊傞偺偩偑丄巕壒岅姴偺係抜摦帉傪偳偆埖偆偐偲偄偆栤戣偑偁傞丅 昅幰偺尰嵼偺峫偊偼丄乽暘偐傜側偄乿偱偁傞丅 慜峞偵傕彂偄偨偑丄僣儞僌乕僗慶岅偵柤帉壔愙帿丂"*i" 傪嵞峔偱偒傞偐偳偆偐偼昅幰偺尰嵼偺敾抐偱偼媈栤偲峫偊傞丅妋偐偵儔儉僗僥僢僩偼傾儖僞僀慶岅偵柤帉壔愙帿丂"*i" 傪嵞峔偟偨偺偩偑(嶲峫暥專丗丂K-21 儘僔傾岅斉丂p.96)丄偦偺屻偺傾儖僞僀榑幰偵傛偭偰偙偺愢偼巟帩偝傟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟傞丅乮A. Vovin : Ref. JP-21 嶲徠乯 堦曽丄俙俶慶岅偺愙帿 "i"丂偱偁傞偑丄偙傟偼丄幚偼柤帉壔愙帿偱偼側偔丄懠摦帉壔愙帿偱偁傞丅俙俶彅岅偺拞偵偼偙偺愙帿偑柤帉壔偵巊梡偝傟偰偄傞傕偺傕偁傝丄擔杮岅偱傕丄椺偊偽丄乽弬乿偺乽棫偰乿偵尒傜傟傞傛偆偵丄俀抜摦帉楢梡宍偲柤帉宍偼枾愙偵娭楢偟偰偄傞丅乮戝嶨攃偵尵偊偽丄係抜摦帉偺枹慠宍偵愙帿 i 傪晅偗偨宍偑丄懠摦帉宍偐偮柤帉宍偱偁傞丅乯 偦偙偱偙偺栤戣偺庤妡偐傝傪扵傞傋偔丄慜峞偱偼丄俙俶慶岅婲尮偲尒傜傟傞擔杮岅摦帉偵丄俙俶慶岅偺岅枛巕壒偑巆懚偟偰偄傞傕偺偑偁傞偐偳偆偐挷傋偨丅 寢壥偼丄俙俶慶岅偺岅枛巕壒偼丄椉怬壒偺 p/m 偵偮偄偰偼丄傎傏姰慡偵巆懚偟偨偲峫偊傜傟傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅惓妋偵尵偆偲丄椉怬壒偺 p/m 偑巆懚偟偨宍偲徚幐偟偨宍偺擇庬椶偺摦帉偑懚嵼偡傞偙偲偑暘偐偭偨丅 椺偊偽丄kanapu (揔傆乯偲 kanu (寭偸乯偼丄堦尒慡偔暿偺摦帉偱偁傞偑丄屆偄帪戙偺梡椺傪挷傋傞偲丄嫟偵俙俶慶岅 gənəp 偵婲尮偡傞偲峫偊傞帠偑偱偒傞丅尨巒擔杮岅偵偍偄偰丄柍愙帿宍偲愙帿宍偺 gənəp丂丂丂丂丂 帺摦帉丂*乽乣偑寚偗傞帠側偔懚嵼偡傞乿 gənəp-i丂丂丂丂懠摦帉丂*乽乣偑乣偵枮偪偰偄傞乿 偑埥傞堦掕婜娫嫟懚偟偨屻丄慜幰偺岅枛偑徚幐偟偰丄kənə 偲側偭偨偨傔偵丄傗偑偰椉幰偑摨尮岅偲堄幆偝傟側偔側偭偨傕偺偲悇掕偝傟傞丅 偱偼丄嵟弶偵嫇偘偨 *at'at 偺応崌偼偳偆側偺偐丠庤妡偐傝傪媮傔偰丄擔杮岅偲摨偠傛偆偵岅枛巕壒偑徚幐偟偨僆僙傾僯傾彅岅乮俴倎倳岅乯偺椺傪挷傋偨丅 *at'at 偵懳墳偡傞椺偱偼側偄偑丄僆僙傾僯傾慶岅丂*maqurip 乮惗偒偨; alive乯偺応崌丄埲壓偺傛偆側懳墳偑尒傜傟傞丅 乮俙俶慶岅偼丄*ma-qu'd2ip丂偲嵞峔偝傟偰偄傞丅)
懠摦帉宍偼丄岅枛巕壒偑徚幐偟偨帺摦帉宍偵丄婲尮偺椙偔暘偐傜側偄愙帿 si 偑愙懕偟偰攈惗偝傟偰偍傝丄慶宍*maquiripi 偐傜偺婯懃揑側壒塁曄壔偱惗偠偨傕偺偵偼側偭偰側偄丅 偙傟傪 *at'at 偺椺偵揔梡偡傟偽丄岅枛巕壒偑徚幐偟偰惗偠偨 *asa 偐傜愙帿 i 偑愙懕偟偨宍 asai 偑攈惗偟丄*at'ati 偑嬱拃偝傟偨偲峫偊偰傕栤戣偼側偄偙偲偵側傞丅 埲忋偺専摙寢壥偐傜丄 (俀抜摦帉楢梡宍)亖(岅姴)亄i 丂偲偄偆屆戙擔杮岅偺宍懺偑丄 (俙俶慶岅岅姴) + (俙俶慶岅愙帿 "i" )丂 偐傜惗偠偨偲峫偊偰傕晄搒崌偼惗偠側偄丅 偲尵偊傞丅偙傟偑慜峞偺寢榑偱偁偭偨丅 俀丏丂奐壒愡壔僾儘僙僗偵娭偡傞峫嶡 乮僆僙傾僯傾彅岅偲偺斾妑乯 偝偰丅 偦傟偱偼懞嶳愢偑斲掕偝傟偨偐偲尵偆偲丄偦偆偱偼側偄丅僣儞僌乕僗乮揑乯尵岅偺扴偄庤偑丄岅枛椉怬壒傪巆偟偰俙俶岅傪庁梡偟偨壜擻惈偼斲掕偝傟側偄丅偁偔傑偱俀抜摦帉傪宍惉偡傞愙帿 "i" 偑俙俶婲尮偲峫偊傞帠偑壜擻偲偄偆偩偗偱偁傞丅 昅幰偑惉壥偲峫偊傞帠偼丄擔杮岅偵偍偗傞奐壒愡壔偺恑峴僾儘僙僗偺堦抂偑敾柧偟偨帠偱偁傞丅屆偄抜奒偵偍偗傞擔杮岅偵偼丄巕壒廔傝偺岅偑偁偭偨丅偙偺帠偐傜丄岅枛巕壒偑姰慡偵徚幐偟偨億儕僱僔傾彅岅偼丄擔杮岅偺慶愭偵偼側傝摼側偄偲寢榑偝傟傞丅 偱偼丄嵟屻傑偱巆偭偨岅枛巕壒偑丄椉怬壒(p/m)偱偁偭偨偲偟偰丄偙偺傛偆側壒塁曄壔偼帺慠側曄壔偲尵偊傞偺偩傠偆偐丠 尰戙乮昗弨乯擔杮岅偱嫋梕偝傟傞岅枛乮壒愡枛乯巕壒偼旲壒 n 偺傒偱偁傝丄椉怬壒(p/m)偑嵟屻傑偱巆偭偨偲偄偆偺偼捈姶偵斀偡傞傛偆側婥偑偡傞丅 偙偙偱嵞傃僆僙傾僯傾彅岅偵偍偗傞壒塁曄壔偑嶲峫偵側傞丅偦偙偱姰慡偵奐壒愡壔偟偨億儕僱僔傾彅岅偵暘婒偡傞慜偺僆僙傾僯傾彅岅偵偍偄偰丄偳偺傛偆側夁掱傪宱偰岅枛巕壒偑徚偊偰偄偭偨偺偐挷傋偰傒傞偙偲偵偡傞丅
"Final Consonants in Remote Oceanic" OCL Vol.44 No.1 (2005)丂 乽儕儌乕僩丒僆僙傾僯傾岅懓偵偍偗傞岅枛巕壒乿 偱偁傞丅偙偺榑暥偱偼丄庡偵丄僯儏乕僇儗僪僯傾彅搰嬤曈偺尵岅乮儕儌乕僩丒僆僙傾僯傾岅孮丟忋恾嶲徠乯偵偍偄偰丄岅枛巕壒偑偳偺傛偆側僾儘僙僗傪宱偰徚偊偰偄偭偨偐傪榑偠偰偄傞丅榑暥偵嫇偘傜傟偨帠椺傪偄偪偄偪徯夘偟偰傕巇曽側偄偺偱丄昅幰乮巹乯偑嫮堷偵傑偲傔偨昞傪帵偡偙偲偵偡傞丅
忋偺昞偼丄挷嵏懳徾偲側偭偨僆僙傾僯傾彅岅偵偍偗傞岅枛巕壒偺巆懚忬嫷傪丄壒塁偛偲偵帵偟偨傕偺偱偁傞丅億儕僱僔傾彅岅偺傛偆偵岅枛巕壒偑姰慡偵徚幐偟偨尵岅偵堏峴偡傞慜偺丄俙俶岅偺堦斒揑忬嫷傪斀塮偡傞偲峫偊傜傟傞丅 棑偺拞偺悢帤偼丄尵岅偺悢傪昞傢偡丅椺偊偽丄倫偑姰慡偵徚偊偰偟傑偭偨尵岅偑俀偮丄姰慡偵偼徚偊偢偵巆偭偨傝巆傜側偐偭偨傝晄埨掕側尵岅偑俀偮偁傞帠傪帵偡丅壒塁偛偲偵尵岅偺廤寁憤悢偑堎側傞偺偼丄僨乕僞偑彮側偔偰僴僢僉儕偟偨帠偑暘偐傜側偐偭偨傝丄乽栺敿暘偑巆懚乿偲偄偆搒崌偺椙偄忬嫷偑側偐偭偨傝偱丄尵岅偵傛偭偰忬嫷偑傑偪傑偪偩偐傜偱偁傞丅 偙傟傪尒傞偲丄ŋ丂傪娷傔偨旲壒偼巆懚椺偑彮側偔丄 帟宻壒 t/s 偺巆懚棪偑崅偄丅p/k 偼偦偺拞娫偱偁傞丅旲壒偼偁傞堄枴曣壒偵嬤偄壒塁側偺偱徚偊偵偔偄偲巚偄偒傗丄徚幐棪偑崅偄偺偼堄奜偱偁傞丅 堷梡暥專偱偼丄岅枛巕壒偼堦婥偵徚幐偟偨偺偱偼側偔丄抜奒揑偵徚幐偟偰偄偭偨偲寢榑偟丄偦偺僷僞乕儞偐傜儕儌乕僩丒僆僙傾僯傾彅岅偺楌巎揑暘婒僾儘僙僗傪悇應偟偰偄傞偺偩偑丄偦偺徻嵶偼徣棯偡傞丅 尨巒擔杮岅偲儕儌乕僩丒傾僙傾僯傾彅岅偵偍偗傞岅枛巕壒偺徚幐夁掱傪斾傋傞偲 侾丏丂旲壒(n)偑愭偵徚偊傞 俀丏丂摿掕偺挷壒応強偺巕壒偑嵟屻傑偱巆傞 偲偄偆摿挜偑嫟捠偟偰偍傝丄昅幰偑悇應偟偨尨巒擔杮岅偵偍偗傞岅枛巕壒偺徚幐僾儘僙僗偼丄彮側偔偲傕晄帺慠偱偼側偄偲尵偊傞丅乮倣傕旲壒偱偼側偄偐偲撍偭崬傑傟傞偲捝偄偺偱偁傞偑丅乯 昅幰偼埲慜丄乽崟乿傗乽敀乿偵偍偗傞 kura 佁 kuro丄sira 佁丂siro丂偲偄偭偨岅枛曣壒偺岎懼傪丄岅枛椉怬壒偺塭嬁偲夝庍偟丄慶宍傪丂*kurap/ *sirap 偲嵞峔偟偰俙俶慶岅 *gəlap / *silap 偲斾妑偟偨丅傑偨丄乽挬乿偵偍偗傞丂asa 佁丂asu 偺曣壒岎懼偐傜丄丂*asam 傪嵞峔偟偰拞婜娯崙岅丂ac儵m 偲斾傋偨丅椉怬壒偑嵟屻傑偱巆懚偟偨偲偄偆忋偺悇掕傪曗嫮偡傞傕偺偲峫偊傞丅 俁丏丂僆僙傾僯傾慶岅偲擔杮岅偺娭學偵偮偄偰 傗傗榖偟偑扙慄偡傞偑丄偙偙偱僆僙傾僯傾慶岅偲擔杮岅偺娭學偵娭偡傞昅幰偺峫偊傪弎傋偰偍偔偙偲偵偡傞丅 僆僙傾僯傾岅懓偱偼丄惣儅儔儓億儕僱僔傾岅懓偲斾傋傞偲丄愙摢帿偑暥朄揑偵偝傎偳廳梫側婡擻傪墘偠偰偄側偄丅僼傿儕僺儞彅岅傗戜榩彅岅偵尒傜傟傞傛偆側愙摢帿偱摑岅峔憿偑巜掕偝傟傞僔僗僥儉乮僼僅乕僇僗丒僔僗僥儉乯偼姰慡偵曵夡偟偰偍傝丄銹拝岅偵嬤偄怳傞晳偄傪帵偡拲乯丅 拲乯丂椺偊偽丄僼傿僕乕岅偵偍偄偰丄懠摦帉偼丄忋偵嫇偘偨俴倎倳岅偲摨條偵丄-a/-ca/-ka/-ma 側偳偺奺庬愙旜帿傪愙懕偡傞偙偲偵傛偭偰攈惗偝傟傞丅丂傑偨丄庴摦懺偼愙旜帿丂-i 偵傛偭偰宍惉偝傟傞丅乮椺丗丂lomana丂乽垽偡傞乿 仺 lomani 乽垽偝傟傞乿丄丂kila丗 乽抦傞乿仺丂kilai 乽抦傜傟傞乿丂側偳乯 偡側傢偪丄僆僙傾僯傾彅岅偱偼丄俙俶慶岅偵懳偟偰壒塁峔憿偑扨弮壔偟丄愙摢帿偑壔愇壔偡傞孹岦偵偁傝丄偦傟偵懼傢偭偰愙旜帿傗彆摦帉偑庡梫側暥朄婡擻傪扴偆偲偄偆堄枴偵偍偄偰丄擔杮岅偲椶帡偟偰偄傞偲尵偆偙偲偑偱偒傞丅 幚嵺丄嶈嶳棟巵偼丄摨條側崻嫆偵婎偯偄偰丄擔杮岅偺宯摑榑偵娭偟偰丄俙俶慶岅傛傝傕僆僙傾僯傾慶岅偲偺娭學傪廳帇偡傞愢傪揥奐偟偰偄傞丅 乮乽屆戙擔杮岅偵偍偗傞僆乕僗僩儘僱僔傾岅懓偺梫慺乿丂嶲峫暥專丗JP-28 丂強廂乯 偟偐偟昅幰偼丄擔杮岅偼丄僆僙傾僯傾慶岅偺塭嬁壓偱惗偠偨偺偱偼側偔丄偁偔傑偱俙俶慶岅偑僣儞僌乕僗揑尵岅偲偺愙怗偱曄梕偟偰惗偠偨傕偺偲峫偊傞丅乮偦偺崻嫆偼庡偲偟偰壒塁榑揑側傕偺偱偁傞偑丄偦偺偆偪傑偲傔偰榑偠傞偙偲偵偟偨偄丅乯廬偭偰丄僆僙傾僯傾彅岅偲擔杮岅偺娫偵尒傜傟傞乽堦庬偺椶帡惈乿偼丄婲尮揑側傕偺偱偼側偔丄暲峴揑側傕偺偲峫偊傞丅 僆僙傾僯傾慶岅偑戝偒側夵曄傪庴偗偨棟桼偼丄偍偦傜偔僷僾傾彅岅偲偺愙怗偵傛傞僺僕儞丒僋儗僆乕儖壔傗丄峀戝側椞堟偵偍偗傞岎堈偺曋媂惈丒昁梫惈偵傛傞娙慺壔偵媮傔傜傟傞傕偺偲巚傢傟傞丅 乮僆僙傾僯傾慶岅偺惉棫偵偍偗傞僷僾傾彅岅娭梌愢偼丄俙俶斾妑尵岅妛偵偍偄偰傎傏掕愢壔偟偰偄傞偲巚傢傟傞丅慜宖彂偵偍偄偰傕搚揷帬巵偑椶帡偟偨敪尵傪偟偰偄傞丅乯 廬偭偰丄僆僙傾僯傾彅岅偼丄俙俶慶岅偑懠偺尵岅偲愙怗偟偨応崌偵丄偳偺傛偆側曄壔偑惗偠傞偐偲偄偆尵岅曄壔偺儌僨儖採嫙偟偰偔傟傞儚働偱偁傞丅乮忋偺岅枛巕壒偺巆懚椺偼偦偺堦椺偱偁傞丅乯 昅幰偺僆僙傾僯傾彅岅偵懳偡傞娭怱偼偙偺揰偵偁傞丅恾幃揑偵帵偣偽埲壓偺傛偆偵側傞丅
屄暿尵岅傪庢傝忋偘傞偲丄嫽枴怺偄尵岅曄壔偺椺偼怓乆偁傞丅椺偊偽丄僷僾傾丒僯儏乕僊僯傾搶抂偵偁傞俵倕倠倕倧岅偼俙俶岅偵懏偡傞偑丄椬愙偡傞僷僾傾彅岅偺塭嬁偱丄擔杮岅偲摨偠俽俷倁偺岅弴偵曄壔偟偨丅尵岅愙怗乮埥偄偼崿崌乯偵敽偆岅弴曄壔偺栤戣偵偮偄偰偼丄杮榑偺拞偱庢傝忋偘傞丅 係丏丂愙旜帿偺婲尮偵娭偡傞壖愢 偝偰丅 崱傑偱偑慜彂偒偱丄傛偆傗偔偙偙偐傜偑杮榑偱偁傞丅 昅幰偼丄乽擔杮岅偺愙摢帿偼俙俶岅婲尮偐丠乿偵偍偄偰愙摢帿乽僀乿傪庢傝忋偘丄俙俶慶岅偲偺娭楢偵偮偄偰榑偠偨丅屆戙擔杮岅偵偍偗傞乽僀乿偺婡擻偑丄僼傿儕僺儞彅岅偵偍偗傞愙摢帿 "i" 偲嬼慠偲偼巚偊側偄椶帡惈傪桳偡傞帠傪帵偟偨丅偙傟偼昅幰偑僆僙傾僯傾慶岅偱偼側偔丄惣儅儔儓億儕僱僔傾彅岅偲偺娭學傪廳帇偡傞崻嫆偺僸僩僣偱偁傞丅 偟偐偟丄慜偵傕榑偠偨傛偆偵丄偦偟偰懡偔偺榑幰偑巜揈偡傞傛偆偵丄屆戙擔杮岅偵偍偗傞愙摢帿偼慡偔壔愇揑側懚嵼偱偟偐側偄丅擔杮岅偵偍偗傞庡梫側暥朄婡擻偼愙旜帿偑扴偭偰偄傞丅愙摢帿偼婡擻傪傎偲傫偳姰慡偵掆巭偟偰丄愙旜帿拲乯偵栶妱傪忳偭偨傛偆偵尒偊傞丅 拲乯丂暥朄妛幰偼暥嬪傪尵偆偩傠偆偑丄偙偙偱尵偆乽愙旜帿乿偼丄妶梡岅旜偩偗偱側偔丄彆帉丒奿彆帉丒彆摦帉傪娷傓傕偺偲偡傞丅偁傞偄偼乽屻抲帉乿偲尵偭偨曽偑椙偄偺偐傕偟傟側偄丅 偱偼愙旜帿偺婲尮偑僣儞僌乕僗婲尮偱愢柧偱偒傞偐偲尵偆偲丄偙傟偑側偐側偐擄偟偄丅乽偼乿乽傪乿乽備乿乽備傝乿側偳偺堦晹偺奿彆帉偵娭偟偰偼僣儞僌乕僗岅偲偺娭楢偑柧傜偐偲巚傢傟傞偑丄偦偺懠偺彆帉傗妶梡岅旜傪僣儞僌乕僗婲尮偲尒側偡帋傒偑惉岟偟偰偄傞偲偼巚偊側偄丅 偙偙偱乽帪戙暿崙岅帿揟丂忋戙曇乿偵偍偗傞愙摢帿偵娭偡傞婰弎傪尒偰傒傞丅椺偊偽埲壓偺擛偒偱偁傞丅愨朷揑側偔傜偄偵婰弎偑彮側偄丅 乽偐-乿丗丂庡偲偟偰宍梕帉偵愙偟偰偦偺堄枴偵堦庬偺怓挷傪偦偊傞丅 乽偝-乿丗丂傎偲傫偳幚幙揑側堄枴偼側偄丅 乽偨-乿丗丂峀偔柤帉丒暃帉丒摦帉丒宍梕帉偵姤偟偰梡偄傜傟傞丅 傗傗徻偟偄婰弎偑尒傜傟傞偺乽傑-乿偔傜偄側傕偺偱偁傞丅 偝偰丅 偙偙偱戝抇偵敪憐傪揮姺偟偰 偙傟傜偺愙摢帿偑愙旜帿偲偟偰揮梡偝傟偨偺偱偼側偄偐偲峫偊偰傒傞丅 愙旜帿偵娭偟偰偼丄婰弎偼堦曄偟偰偐側傝徻嵶側傕偺偲側傞丅椺偊偽丄 乽-偐乿丗丂愙旜岅丅 忣懺揑側堄枴傪昞傢偡岅婎偵偮偄偰忣懺揑奣擮傪屌掕偟丄忣懺暃帉傗偄傢備傞宍梕摦帉偺岅姴傪宍惉偡傞丅壋椶偺ke2 偵揮偠偰僋妶梡宍梕帉偺岅姴偲傕側傞丅儎僇丒儔僇偺宍傪庢傞偙偲傕偁傞丅 乽-偝乿丗丂愙旜岅 嘆丂宍梕帉偺岅姴偵愙偟偰偙傟傪懱尵壔偟丄乽乣偱偁傞帠乿偺堄傪昞傢偡丅 嘇丂柤帉偵偮偄偰曽岦偺堄傪晅偗壛偊傞丅 嘊丂堏摦傪昞傢偡摦帉偵偮偄偰堏摦偺搑拞偱偁傞偙偲傪帵偡丅 杮棃偼丄忣懺偺堄偺柤帉偐偲峫偊傜傟傞丅嘇偼曽岦傪栚巜偡忬懺偺堄偲峫偊偰椙偄丅乽媡偝乿偺岅旜偺僒傕摨偠傕偺偱丄偙傟傪僒僇僒儅偲傕偄偆傛偆偵丄乽僒儅乿偼丄僒偺愙旜帿儅偑愙偟偨岅偱偁傠偆丅條巕丒忬懺偺堄偲摨帪偵曽岦偺堄傪梡偆傞揰偱傕堦抳偟偰偄傞丅 乽亅偨乿乽亅偩乿丗丂暃帉傪嶌傞岅旜偺僸僩僣丅 傾儅僞丒傾儔僞丒僂僞僞偲僀僋僟丒僀儅僟丒僐僉僟丒僐僐僟丒僒僴僟偼惔戺偺堘偄偼偁傞偑摨偠傕偺偐丅 偲偄偆嬶崌偱偁傞丅 偦偙偱帋偟偵丄愙旜帿偺乽-偐乿傪丄俙俶彅岅偺愙摢帿 "ka-/kə" 偲斾妑偟偰傒傞丅 僙僽傾僲岅丂乮僞僈儘僌岅丄僀儘僇僲岅偱傕梡朄偼傎傏摨偠丅乯 "ka-" 丗丂宍梕帉偵愙偟偰巊梡偝傟傞愙帿丅 嘆丂宍梕帉偑帵偡忬懺傪堄枴偡傞柤帉偵側傞丅丂椺丗丂subu 乮斶偟偄乯仺丂kasubu 乮斶偟偝乯 嘇丂姶摦丒嬃扱傪昞傢偡丅丂椺丗丂daku (戝偒偄乯丂仺丂kadaku (側傫偲僨僇僀両乯 僀儞僪僱僔傾岅丗 "ke-"丂丗丂岅崻摦帉埥偄偼宍梕帉偵愙摢偝傟偰柤帉傪宍惉偡傞丅 俙俶彅岅乮惣儅儔儓億儕僱僔傾彅岅乯偱丄*ka- 偼丄宍梕帉偵愙懕偟偰偦傟傪柤帉壔偡傞愙帿偲傒偰丄傑偢娫堘偄側偄丅 偱偼丄屆戙擔杮岅偵偍偗傞丄乽嬸偐乿乽惷偐乿乽壺傗偐乿乽偝傗偐乿側偳偵尰傟傞乽-偐乿偑丄暥朄揑偵偳偆偄偆婡擻傪桳偟偰偄偨偺偐丅偙傟偼屆揟暥朄偵慳偄昅幰偵偼丄側偐側偐擄偟偄栤戣偱偁傞丅 椺偊偽丄乽嬸偐偵偦変偼巚傂偟乿乮枩丗14-4049)偺応崌丄乽偵乿偼丄懱尵偲梡尵傪楢寢偡傞奿彆帉偲夝庍偝傟傞傛偆偱偁傞丅乮偙偺椺偼學傝寢傃宍側偺偱丄乽嬸偐偵巚傂偟乿偑杮棃偺岅弴偱偁傞丅乯 乽娾攇屆岅帿揟乿偱偼丄乽埳惃偺奀偺堥傕偲偳傠偵婑偡傞攇乿(#600)傗丄乽偼傠偼傠偵巚傎備傞偐傕乿乮#866)側偳偵尰傟傞乽偵乿傪丄懱尵偲梡尵傪愙懕偡傞奿彆帉偲尒側偡丅偙偺 乽偵乿傪乽側傝乿偺楢梡宍偲傒側偡愢傕偁傞傛偆側偺偩偑丄乽側傝乿偼乽偵乿亄乽偁傝乿偵婲尮偡傞偲偄偆偺偑崙岅妛偺掕愢偺傛偆偱丄寢嬊偼丄奿彆帉乽偵乿偺愙懕偲傒側偡帠偑偱偒傞傛偆偱偁傞丅 偲偡傟偽丄乽嬸偐偵乿偺乽偵乿傕奿彆帉偲偄偆帠偵側傞丅偩偲偡傟偽乽嬸偐乿偼懱尵偱偁傞丅 嶃憅撃媊偺乽岅峔惉偺尋媶乿(暥專丗 JP-2)丂偱偼丄愙旜帿乽偐乿偵偮偄偰丄乽宍幃柤帉揑惈奿傪傕偭偰偄偨乿偲偡傞丅(p.323-325; 嫮挷偼昅幰偵傛傞丅扐偟嶃憅巵偺榑巪偵偼昅幰偺廬偄擄偄売強偑怓乆偲偁傞偑丄偙偙偱偼怺擖傝偟側偄偱偍偔丅乯 傑偨丄乽嬸偐恖乿偲偄偆昞尰偑偁傞偑丄嶃憅巵偺榑偵廬偊偽丄偙偺宍幃偼丄乽僸僜僇僐僩乿乽儈僕僇儐僼乿乮抁栘柸乯偲摨偠偔丄(宍梕帉)亄(柤帉)偱偼側偔丄暋崌柤帉偲夝庍偝傟傞丅 梫偡傞偵丄乽嬸偐乿偼柤帉揑宍懺偱偁傝丄廬偭偰愙旜帿乽-偐乿偼丄宍梕帉惈偺岅姴傪柤帉壔偡傞婡擻傪帩偭偰偄偨帠偵側傞丅偙傟偼丄俙俶慶岅偺愙摢帿丄*ka- 偲乽帡偰偄傞乿偲尵偊傞偩傠偆丅 傑偨忋戙偵偼妋擣偝傟側偄偑丄乽嬸偐両乿乽惷偐両乿偲偄偆姶扱宍偼丄僙僽傾僲岅偺梡椺偲摨偠偱偁傞帠傕嫽枴傪堷偔丅 偝偰丅 乽嬸偐乿偼丄乽嬸偐側傝乿偲偄偆宍梕摦帉偺岅姴偱偁傞丅宍梕摦帉偼丄忋戙偵偍偄偰偼枹敪払偺抜奒偵偁偭偨偑丄偦傕偦傕丄宍梕帉偲偄偆傕偺偑偁傝側偑傜丄側偤宍梕摦帉偲偄偆岅椶偑敪惗偟偨偐偵偮偄偰偼丄崙岅妛偵偍偄偰昁偢偟傕柧夣側愢柧偑側偝傟偰偄傞儚働偱偼側偄傛偆偱偁傞丅偙偙偱偙偺栤戣偵怺擖傝偡傞偮傕傝偼側偄偑丄嶳岥壚婭偺乽屆戙擔杮岅暥朄惉棫偺尋媶乿強廂偺乽僫儕宆宍梕摦帉偺惉棫乿乮p. 377-406; Ref. #JP-37)偵傛傟偽丄 乽乮岅姴偑乯丄惷揑忬懺傪昞尰偟摼傞傕偺偱偁偭偰弶傔偰宍梕摦帉偲側傞偙偲偑壜擻乿偩偭偨偲偡傞丅 乮ibid. p. 378; 嫮挷偼昅幰偵傛傞丅乯 偙偺尵愢傪慜採偲偟偨忋偱丄昅幰偺嫽枴傪堷偔偺偼丄宍梕摦帉偺岅姴偵丄乮愙摢帿乯亄乮岅婎乯偲偄偆宍幃傪庢傞傕偺偑懚嵼偡傞偙偲偱偁傞丅慜宖彂偱偼丄 僇傾儝乮偐惵乯丄僇僋儘乮偐崟乯丄僒傾儝乮偝惵乯丄儅僫儂乮傑捈乯 偑椺帵偝傟偰偄傞丅(ibid. p.385) 偙偙偱拲栚偝傟傞偺偼丄椺偊偽乽惵側傞乿偲偄偆昞尰偼嫋偝傟側偄偺偵丄愙摢帿傪愙懕偟偰乽偐惵乿偲偡傞偲丄宍梕摦帉乽偐惵側傝乿亙乽偐惵 偵 偁傝乿偲偄偆宍幃偑壜擻偵側傞帠偱偁傞丅慜宖彂偱偼宍梕摦帉偺岅姴偵側傝摼傞岅偺徻嵶側暘愅偑峴側傢傟偰偄傞偑丄偙偺僞僀僾偺宍梕摦帉偵娭偡傞暘愅偼寉偔棳偝傟偰偄傞丅乮乽宍梕帉偵丄偁傞庬偺愙摢帿偑偮偔偲丄僋岅旜偱側偔僯岅旜傪庢傞偙偲偑懡偔丄偙傟傕偦傟偱偁傞丅乿丟 ibid. p. 387偲偁傞偩偗丅乯 忋偵堷梡偟偨傛偆偵丄宍梕摦帉偺岅姴偑丄乽惷揑忬懺傪昞尰偟偨傕偺乿偱偁傞偲偡傟偽丄乽惵偟乿偲乽偐惵側傝乿=乽偐惵偵偁傝乿偺堘偄偼丄嫮偄偰塸岅偱昞尰偡傟偽丄宍梕帉宍偼丄"be丂blue" 丄宍梕摦帉偼丄"be in state of blue" 偲偄偆帠偵側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅"be in 乣" 偑乽偵偁傝乿偵懳墳偡傞丅 懄偪丄愙摢帿乽偐-乿偼丄宍梕帉惈岅姴傪柤帉壔偡傞婡擻傪帩偮偲夝庍偝傟丄偙傟偼丄乽嬸偐乿偺愙旜帿乽-偐乿偺婡擻偲摨偠偱偁傝丄偐偮丄俙俶慶岅愙摢帿丂*ka- 偲摨偠偲偄偆帠偵側傞丅 偄偝偝偐嫮堷偱偼偁傞偑丄偙偙偱僸僩僣偺壖愢傪棫偰傞帠偑偱偒傞偲巚傢傟傞丅懄偪丄 俙俶慶岅婲尮偺丂 (柤帉宍) = ka-(宍梕帉惈岅姴) 偲偄偆宍幃偑丄 屆戙擔杮岅偵偍偄偰 乮柤帉宍乯亖乮宍梕帉惈岅姴乯-ka 偵曄壔偟偨丅壔愇揑偵丄ka-(宍梕帉惈岅姴)傕巆懚偟偨丅 偲偄偆乮帺暘偱尵偆偺傕側傫偩偑乯戝抇側壖愢偱偁傞丅 崙岅妛幰偺娫偱偼丄忋偺壖愢偲偼媡偺悇堏偑掕愢偵側偭偰偄傞傛偆偱偁傞丅乮儌僠儘儞丄偙偙偱尵偆乽媡乿偼惉棫偺弴彉偵偮偄偰偱偁傞丅乯椺偊偽忋偱偼堷梡傪棯偟偨偑丄乽帪戙暿崙岅帿揟乿偺乽-偐乿偺崁栚偵偼丄埲壓偺婰弎偑偁傞丅 忣懺惈偺堄傪乮乽-偐乿偲摨偠偔乯屌掕偡傞愙旜岅偵丄乽傑乿丒乽偝乿側偳偑偁傞偑丄乽偐乿傪娷傔偰偙傟傜偼摨堦偺宍偱愙摢岅偲偟偰傕梡偄傜傟丄宍梕帉丄摦帉丄媦傃庒姳偺柤帉偵姤偣傜傟偰庡偲偟偰塁暥偵尰傟傞丅丂乮嫮挷偼昅幰偵傛傞乯 偙傟傪慺捈偵撉傔偽丄愙摢岅偺僇丒僒丒儅側偳偲丄愙旜岅偺偦傟傜偼摨尮岅偱偁傝丄杮棃偼愙旜岅偩偭偨傕偺偑丄塁暥偺傛偆偵摿庩側暥偱偼丄愙摢岅偲偟偰傕巊梡偝傟偨偲庡挘偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅 偙傟偲摨偠庡挘傪丄嶃憅巵偑擔杮岅偺婲尮栤戣偵娭偟偰弎傋偰偄傞丅 乮愙摢帿偲偟偰偼乯儅丒僒丒僇丒僞偁傞偄偼僀側偳偑丄拲栚偵抣偡傞傕偺偱偁傞丅嫽枴偁傞帠幚偼丄偙傟傜偑乮乽僀乿傪彍偄偰乯偄偢傟傕愭偵忣懺尵傪峔惉偡傞愙旜岅偲偟偰偁偘偨傕偺偲丄傑偝偵摨宍偺宍懺慺偱偁傞偙偲偱偁傞丅乮拞棯乯 偙傟傜偺愙摢帿偼丄傗偼傝奺庬偺岅婎偵偮偄偰丄偙傟偵忣懺惈偺堄枴乮埥偄偼丄傓偟傠僯儏傾儞僗乯傪揧偊偨偺偱偁傠偆丅偙偆偟偨揰偐傜傕丄偙傟傜偺儅丒僒丒僇丒僞側偳偙偦愙摢帿偲屇傃摼傞傕偺偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞偑丄偨偩拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄偙傟傜偵傛傞攈惗岅偼丄忋戙暥專偵偍偄偰偼丄塁暥偁傞偄偼乽梬擵尵乿偲偄偆傛偆側摿庩側暥懱偵偟偐梡偄傜傟偢丄嶶暥偵偼偄偭偝偄尰傟偰偙側偄偲偄偆帠幚偱偁傞丅 偩偲偡傞偲丄忋戙擔杮岅偵偼愙摢帿偑堦斒偵惙傫偵梡偄傜傟偨側偳偲偄偆偙偲傕丄庤曻偟偵偼尵偊側偄偙偲偵側傞丅 乮乽屆戙擔杮岅偺撪揑嵞峔乿丟丂乽擔杮岅偺宍惉乿強廂丂p.302-303乯 嫲傜偔丄崙岅妛偵偍偗傞庡棳側峫偊偼丄 捠忢偺 (岅姴)-ka/sa/ta/ma 偲偄偆愙旜帿偺宍幃偑丄 塁暥偲偄偆摿庩側娐嫬偱偼丄 ka/sa/ta/ma-乮岅姴乯 偲偄偆愙摢帿偺宍幃傪庢傞偙偲偑偁偭偨丅 偲偄偆傕偺偩偲巚傢傟傞丅忋戙暥專偵懄偟偰峫偊傞尷傝丄偙偆峫偊傞偟偐側偄帠偼傛偔暘偐傞丅昅幰偑傓偟傠堄奜偵巚偭偨偺偼丄乽僇丒僒丒僞丒儅乿偲偄偭偨宍懺慺偑丄岅姴偺屻傠偵傕慜偵傕愙懕偟偨壜擻惈傪崙岅妛幰偑擣傔偰偄傞帠偱偁傞丅 偩偲偡傟偽丄昅幰偺壖愢 尨巒擔杮岅丗丂ka-(宍梕帉惈岅姴) 亜丂屆戙擔杮岅丗丂(ka)-乮宍梕帉惈岅姴乯-ka 偼丄乽崙岅妛偺掕愢乿乮丠乯偲偼惉棫偺弴彉偑堎側傞偩偗偱丄昁偢偟傕峳搨柍宮偲偄偆儚働偱傕側偔丄偳偪傜偑愭偵惗偠偨偐偲偄偆栤戣偼撪揑嵞峔偵傛偭偰偼寛拝偑晅偐偢丄斾妑尵岅妛偺庤朄偵傛偭偰寛掕偝傟傞偲嫮曎乮丠乯偡傞偙偲偼偱偒偦偆偱偁傞丅 偙偙傑偱偑丄偄傢偽梊旛専摙偱偁傞丅偙偙傑偱偔傟偽丄昅幰偺栚榑尒偼柧傜偐偱偁傠偆丅崱傑偱弎傋偰棃偨偙偲傪惍棟偡傞偲埲壓偺傛偆偵側傞丅
偟偐偟丄側偵偟傠憡庤偼偨偭偨堦壒愡偺宍懺慺偱偁傞丅扤傕偑擺摼偡傞宍偱偺徹柧偼尷傝側偔崲擄偱偁傞丅椺偊偽忋偵嫇偘偨榑嫆偱傕偭偰丄愙旜帿乽-偐乿偑丄俙俶彅岅 ka- 偲摨尮偱偁傞偲徹柧偝傟偨偲峫偊傞幰偼偄側偄偩傠偆丅乮愙旜帿乽-偐乿偺婲尮偵偮偄偰偼丄AN岅傪帩偪弌偝側偔偰傕丄懠偵偄偔傜偱傕榑傪棫偰傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅乯 偦傕偦傕丄偙偺傛偆側媍榑偼丄擔杮岅偑AN慶岅婲尮偱偁傞帠偑媈偆梋抧側偔徹柧偝傟偨屻偱偺傒桳岠側偺偱偁傞丅偟偐偟丄偦偺徹柧帺恎偑旕忢偵崲擄偱偁傞埲忋丄偙偆傗偭偰愴慄傪奼戝偟偰丄忬嫷徹嫆傪廤傔偰偄偔偟偐擔杮岅偺婲尮偵敆傞庤抜偼側偄偲昅幰偼峫偊傞丅 俆丏丂岅弴偺曄壔偵娭偡傞堦斒揑尨懃偵偮偄偰丂 懠偺愙摢帿偵偮偄偰榑偠傞慜偵丄傑偢偼忋偱弎傋偨傛偆側尵岅曄壔偑杮摉偵婲偙傝摼偨偺偐傪専徹偟偨偄丅偦傟偵偼岅弴乮僞僀億儘僕乕乯偺楌巎揑曄壔偵娭偡傞堦斒懃偵偮偄偰偺抦幆偑昁梫偲側傞丅 偦傕偦傕丄愙摢帿偑愙旜帿偵揮梡偝傟偨偺偱偼側偄偐偲昅幰偺敪憐偺僉僢僇働偼丄報墷慶岅偺孅愜岅旜偵娭偡傞儅儖僠僱愢偵偁傞丅乮傾儞僪儗丒儅儖僠僱挊丂乽報墷恖偺偙偲偽帍乿嶲徠乯 椺偊偽丄儘僔傾岅偺暋悢梌奿偼丄 乽嶨帍偵乿乮抝惈柤帉乯丗丂剋剠剛剘刾剕刾剗 乽応強偵乿乮拞惈柤帉乯丗丂剗剈剝剟刾剗 乽怴暦偵乿乮彈惈柤帉乯丗丂剆刾剎剈剟刾剗 偲偄偆傛偆偵丄岅旜偵 -am 偑晅偔丅偙傟偼丄屆偄帪戙乮屆戙嫵夛僗儔償岅乯偵偼丄-mu/-mi 偩偭偨丅僊儕僔儍岅傗僒儞僗僋儕僢僩岅偱丄偙傟偵懳墳偡傞宍幃偼丄-phi 丄-bhis丂偱偁傞丅儅儖僠僱偼丄偙傟傜偺岅宍傪摑堦揑偵愢柧偡傞偨傔偵丄報墷慶岅偵慜旲壒壔壒塁乮俙俶岅傒偨偄偩両乯丄mb- 偑懚嵼偟偨偲偟偰丄mbhi 丂乮乣偱/乣偵乯偲偄偆岅傪嵞峔偟偨丅 乽愙帿乿偱側偔乽岅乿偲偄偆偺偼丄尦偺昳帉僞僀僾偑傛偔暘偐傜側偄偐傜偱偁傞丅mbhi 偼丄忋偺彅尵岅偵偍偄偰偼愙旜帿偱偁傞偑丄儅儖僠僱偼丄偙傟偑僎儖儅儞岅偵偍偄偰偼愙摢帿埥偄偼慜抲帉偲偟偰弌尰偡傞偲偄偆戝抇側愢傪採彞偟偨丅 儅儖僠僱偵傛傟偽丄僎儖儅儞岅偱偼丄偙偺愙旜帿偼摦帉愙摢帿 be-丂乮僪僀僣岅偺丂besprechen 傗塸岅偺 become 偵尒傜傟傞丂be- )傗丄慜抲帉偺 bei (僪僀僣岅乯丄by 乮塸岅乯偲側偭偨丅by 偲丂be- 偑摨尮偲偄偆偩偗偱傕廩暘偵堄奜偱偁傞拲乯丅丂(ibid. p. 203/p.231乯 拲乯丂偮偄偱偵晅偗壛偊偰偍偔偲丄僶僗(bus)偼丄儔僥儞岅偺 omni-bus 乮乽偡傋偰偺幰偵乿乯偺bus 偑岅尮偱丄bus 偼丄bu-s 偲暘夝偝傟傞偑偙偺 bu 偑 mbhi 偵懳墳偡傞丅bus 偲 by 偑摨尮偲偼傑偡傑偡堄奜偱柺敀偄丅 偙偺愢傪弶傔偰抦偭偨帪丄昅幰偼乽側傫偲戝抇側乿偲巚偭偨傕偺偱偁傞偑丄偙偺傛偆側愢偑嫋偝傟傞偺偱偁傟偽丄擔杮岅偺愙摢帿偑丄僞僀億儘僕乕偺曄壔偵楢摦偟偰丄愙旜帿偵揮梡偝傟傞偔傜偄偺帠偑偁偭偰傕椙偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑丄忋偱採帵偟偨壖愢傪峫偊傞僉僢僇働偲側偭偨儚働偱偁傞丅 偱偼丄偙偺愢偑徹柧偱偒傞偐偲偄偆偲擄偟偄丅偟偐偟丄彮側偔偲傕偙偺傛偆側揮梡偑峴側傢傟摼傞偲偄偆乽奧慠惈乿偼帵偝傟側偔偰偼側傜側偄丅埲壓偵弎傋傞帠偼昅幰側傝偺夝庍偱偁傞丅報墷岅偵娭偡傞帠偩偑丄俙俶岅傗擔杮岅偵傕揔梡壜擻側楌巎尵岅妛忋偺堦斒榑偵婎偯偔丅 乽嵞夝庍乿偵傛傞宍懺曄壔偵偮偄偰 忋偺僞僌僀偺摑岅榑忋偺尵岅曄壔傪愢柧偡傞嵺偺丄楌巎尵岅妛偵偍偗傞掕愇偺僸僩僣偼丄乽嵞夝庍乿(reanalysis)偲偄偆峫偊曽偱偁傞丅 屆戙僎儖儅儞岅偼丄俽俷倁偲偄偆岅弴偱偁偭偨偲悇掕偝傟偰偄傞丅椺偊偽丄屆戙僲儖僩岅偼 godagastiz runo faihido. 丂乽恄偺敽乮丠乯 偼丄偙偺儖乕儞暥帤傪丂昤偄偨丅乿 偲偄偆嬶崌偱偁傞乮俙俢係侽侽擭偔傜偄偺儖乕儞暥帤旇暥偵傛傞乯丅尰戙僪僀僣岅偺丄 Paul hat ein Buch gekauft. 丂乽Paul 偼 杮乮Buch)傪丂攦偭偨丅乿 偲偄偆俽俷倁偺岅弴偼丄屆戙僎儖儅儞岅僆儕僕僫儖偺俽俷倁宍傪斀塮偟偰偄傞傕偺偲偝傟傞丅 廬偭偰丄椺偊偽乽傾僪儖僼偼恄偵榖偟偐偗傞丅乿偼丄尨巒僎儖儅儞岅偱偼丄乽恄偵乿偑庡岅偲摦帉偺娫偵擖偭偰 Adorf Gudam-mbhi sprekat. 偲偄偆傛偆側岅弴偱昞尰偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丂(忋偺岅宍偼昅幰偑彑庤偵僨僢僠忋偘偨僀儞僠僉尨巒僎儖儅儞岅偱偁傞丅嬶懱揑側岅宍偼偙偙偱偼杮戣偲娭學側偄丅栤戣側偺偼偁偔傑偱岅弴偱偁傞丅乯 偙偙偱丄mbhi丂偲偄偆岅偑丄撈棫惈偺崅偄宍懺慺乮暃帉乯偲偟偰嵞夝庍偝傟丄偐偮 bi 偵曄壔偟偨偲偡傞偲丄 (I)丂亜Adorf Gudam mbhi sprekat.丂> Adorf Gudam bi spricht.(II) 偲側傞丅(I) 亜(II) 偵偍偄偰偼丄偨偩昞婰忋僴僀僼僅儞偑徚偊偨偩偗偱偁傞偑丄偙傟偑乽嵞夝庍乿偱偁傞丅峏偵丄bi 偑摦帉偺愙摢帿偲嵞夝庍偝傟丄俽俷倁偺岅弴偑俽倁俷偵曄峏偝傟傞偲丄乮岅弴曄壔偵偮偄偰偼屻弎乯 (II) 丂> 丂Adorf Gudam bi-sprekat. 丂> 丂Adorf bisprekat Gudam. 仺 Adorf bespricht das God. (僪僀僣岅乯/ Adorf bespeaks the God.乮塸岅乯 偲側傞丅岅宍偑曄傢傜偢婡擻偵娭偡傞夝庍偺曄壔偑偦偺屻偺曄壔偺僩儕僈乕偲側傞偲偄偆偺偑丄儈僜偱偁傞丅偙傟偑丄乽嵞夝庍乿偵傛傞宍懺曄壔偱偁傞丅嵶晹偵栤戣偑偁傞偑丄柤帉偺愙旜帿偑偄偐偵偟偰摦帉愙摢帿偵曄壔偡傞偐偵娭偟偰偼丄偍偦傜偔僾儘偺尵岅妛幰傕摨偠傛偆側夝庍傪嵦梡偡傞偲巚傢傟傞丅 僞僀億儘僕乕曄壔偵娭偡傞堦斒懃 儅儖僠僱偑嵞峔偟偨報墷慶岅愙旜帿丂mbhi 偑丄慜抲帉偺 by (僪僀僣岅偱偼 bei)偵曄壔偟偨宱堒偵偮偄偰偼丄暿偺朄懃偑敪摦偟偨偲峫偊側偔偰偼側傜側偄丅惗偠偨曄壔偼埲壓偺傛偆側傕偺偩偭偨偲峫偊傜傟傞丅 Adorf Gudam bi sprekat.(II) > Adorf Gudam-bi spricht (III) > Adorf sprekat bi-Gudam (IV) 乮俬俬乯偺抜奒偐傜丄嵞傃(III)偺傛偆偵丄bi 偑屻抲帉偲嵞夝庍偝傟偨偲壖掕偡傞丅俽俷倁亜俽倁俷偺岅弴曄壔偑惗偠偨嵺偵丄偦傟偵楢摦偟偰丄bi 偑慜抲帉偵曄壔偟偨偲峫偊傞偺偱偁傞丅偙偺曄壔傪愢柧偡傞偺偑丄乽僞僀億儘僕乕挷榓乿偲偄偆尰徾偱偁傞丅揱壠偺曮搧偁傞偄偼墿栧條偺報饽偺傛偆側朄懃偱偁傞丅 偦傕偦傕丅 側偤丄尵岅偺楌巎揑曄壔偵偍偄偰SOV偐傜SVO偺傛偆側岅弴曄壔偑惗偠傞偺偐丅 偙偺婎杮揑側媈栤偵懳偡傞摎偊偼埲壓偺傛偆側傕偺偲巚傢傟傞丅 尵岅偼堦斒揑偵丄捠忢偺尵偄夞偟偺懠偵丄偦傟偵懼傢傞偦傟傎偳堦斒揑偱側偄尵偄夞偟傪旛偊偰偄傞帠偑懡偄丅椺偊偽塸岅偱偼丄晛捠偺岅弴偼丄俽倁俷偱偁傞丅変乆偼丄晛捠偼丄" I can't recommend this book." 乮巹偼偙偺杮傪姪傔傞偙偲偑偱偒側偄乯偲丄俽倁俷偺岅弴偱榖偡丅偙傟偑丄柍昗宍偱偁傞丅偟偐偟丄偁傞摿暿偺栚揑偺偨傔偵丄変乆偼丄"This book I can't recommend." 乮偙偺杮偼偍姪傔偱偒側偄丅乯偲尵偆偙偲偑偁傞丅偙傟偼丄椺偊偽丄懠偺杮偲崱栤戣偵偟偰偄傞杮偺斾妑傪嫮挷偟偨偄帪偵巊偆尵偄夞偟偱偁傞丅偙偺丄俷俽倁偲偄偆岅弴偺摿暿側暥宆偑丄桳昗宍偱偁傞丅 偝偰丄傕偟塸岅偺榖偟庤偑丄偙偺桳昗宍傪丄尰嵼傛傝傕傕偭偲昿斏偵梡偄偨偲偟傛偆丅偡傞偲丄挿偄帪娫偺娫偵偼丄俷俽倁偑柍昗宍丄俽倁俷偑桳昗宍偲側傞丅偙偺傛偆側乽昗幆宍偺僔僼僩乿(shift of markedness)偑丄岅弴曄壔傪堷偒婲偙偡偙偲偵側傞丅塢乆丅 乮"Historical Linguistics" R.L. Trask p.140偺戞堦丒戞俀僷儔僌儔僼偺梫栿 Ref. #LN-18) 忋偼岅弴偺帺敪揑曄壔偵偮偄偰偺堦斒懃傪弎傋偨傕偺偩偑丄屻弎偡傞傛偆偵丄岅弴偼懠偺尵岅偲偺愙怗偵傛偭偰傕曄壔偡傞丅偙偙偱旕忢偵嫽枴怺偄偺偼丄忋偱弎傋偨杒僎儖儅儞岅偺傛偆側帺敪揑曄壔偵偮偄偰偼丄俷倁偐傜倁俷傊偺曄壔偼悢懡偔曬崘偝傟偰偄傞偺偵懳偟丄倁俷偐傜俷倁偺曄壔偺傎偲傫偳偑丄尵岅愙怗偵傛偭偰惗偠偨傕偺偲偝傟傞帠偱偁傞丅 ("Reanalysis in word order stability and change" by Jan Terle Faarlund ; Ref #LN-31偵傛傞丅) 廬偭偰丄傕偟擔杮岅偑俙俶岅偵婲尮偡傞偲偄偆壖愢偑惓偟偄偲偡傟偽丄擔杮岅偺俽俷倁偲偄偆岅弴偼丄帺敪揑曄壔偱偼側偔尵岅愙怗偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨壜擻惈偑崅偄帠偵側傞丅 偝偰丅 崱傑偱丄乽岅弴乿偲尵偊偽丄庡岅乮俽乯-摦帉乮倁乯-栚揑岅乮俷乯偵娭偡傞傕偺偵尷掕偟偰榖偟傪恑傔偰偒偨偑丄尵岅偵偼丄宍梕帉乮俙乯偲柤帉乮俶乯丄強桳奿乮俧倕値乯偲柤帉乮俶乯丄彆摦帉乮俙倁乯偲摦帉乮倁乯偺偳偪傜偑愭偵棃傞偐丄慜抲帉偲屻抲帉偺偳偪傜傪梡偄傞偐傕岅弴偵娭偡傞廳梫側僷儔儊乕僞乕偱偁傞丅 偙傟傜偺岅弴偵偮偄偰偼丄崱傑偱偨傃偨傃弌偰偒偨乽僞僀億儘僕乕挷榓乿偲偄偆尰徾偑偁傝偦偆偩偲偄偆帠偵側偭偰偄傞丅偙傟偼丄梫偡傞偵丄尵岅傪擔杮岅偺傛偆側俷倁尵岅偲塸岅偺傛偆側倁俷尵岅偵戝暿偟偨応崌丄
偲偄偆岅弴偵側傞応崌偑懡偄偲偄偆傕偺偱偁傞丅椺偊偽丄俽俷倁偱慜抲帉傪庢傞尵岅偼婬偱偁傞摍乆丅偟偐偟塸岅偺椺偱暘偐傞捠傝丄偙偺朄懃偼尩枾偵惉棫偡傞傕偺偱偼側偄丅偳偺傛偆側婯懃偑嵟傕晛曊揑側傕偺偲峫偊傜傟傞偐傪弰偭偰懡偔偺媍榑偑偁傞偑乮壓婰嶲峫暥專嶲徠乯丄偙偙偱偼怺擖傝偟側偄偱偍偔丅摿偵宍梕帉偲柤帉偺岅弴偵偮偄偰偼堦斒揑側朄懃傪懪偪棫偰傞帠偼擄偟偄傛偆偱偁傞丅偪側傒偵丄僞僈儘僌岅偲擔杮岅偼丄偙偺朄懃偺桪摍惗偱偁傞丅 乮嶲峫暥專丗丂僶乕僫乕僪丒僐儉儕乕挊丂乽尵岅晛曊惈偲尵岅椶宆榑乿丂ref: #LN-32乯 側偤偙偺傛偆側孹岦偑惗偠傞偐偵偮偄偰偼丄楌巎尵岅妛偲偄偆傛傝傕丄偄傢備傞乽尵岅晛曊惈乿傗傜乽尵岅廗摼乿乮戞堦尵岅乯偵娭傢傞栤戣偱傕偁傝丄僠儑儉僗僉乕棟榑傗傜惗惉暥朄偵偮偄偰夝愢偟側偔偰偼側傜側偄丅乮忋偵嫇偘偨僐儉儕乕偺挊彂偱偼偦偺僞僌僀偺媍榑偵偼椻扺側偺偩偑昅幰帺恎偼堦掕偺嫟姶傪妎偊側偄偱傕側偄丅乯嫽枴偺偁傞曽偼丄僗僥傿乕償儞丒僺儞僇乕偺乽尵岅傪惗傒弌偡杮擻乿乮俶俫俲僽僢僋僗丂Ref. #LN-21乯曈傝傪丄挻擖栧曇偲偟偰撉傫偱捀偒偨偄丅 偙偺朄懃傪揔梡偡傞偲丄SOV尨巒僎儖儅儞岅偑丄SVO宆偵曄壔偟偨嵺偵丄屻抲帉偑慜抲帉偵曄壔偡傞乽埑椡乿偑摥偔偙偲偑愢柧偱偒傞儚働偱偁傞丅 俇丏丂僞僈儘僌岅偵惗偠摼傞僞僀億儘僕乕曄壔偵偮偄偰丂 埲忋弎傋偰偒偨丄 侾丏丂嵞夝庍 俀丏丂桳昗宍幃偺僔僼僩 俁丏丂尵岅愙怗 係丏丂僞僀億儘僕乕挷榓 偑丄岅弴乮僞僀億儘僕乕乯曄壔傪愢柧偡傞偨傔偺摴嬶棫偰偺奣棯偱偁傞丅偙傟傜傪尦偵丄僞僈儘僌岅傪椺偵庢偭偰偳偺傛偆側曄壔偑摑岅峔憿偵惗偠摼傞偺偐僔儈儏儗乕僩偟偰傒傞丅 僞僈儘僌岅偼埲壓偺丄俀庬椶偺暥宆傪桳偟偰偄傞丅慜幰偑柍昗宍丄屻幰偑桳昗宍偱偁傞丅偙偙偱摿偵拲栚偝傟傞偺偼丄暃帉偁傞偄偼彫帿偺埵抲偱偁傞丅 俙丂捠忢偺彇弎宍丗 mabait 丂na 丂丂siya 丂sa 丂丂akin. 桪偟偄丂姰椆丂丂斵丂丂乣偵丂巹乮偵乯 乽斵偼丂巹偵丂婛偵桪偟偄丅乿 俛丂搢抲宍乮嫮挷宍乯拲乯丗 siya丂 丂ay 丂丂丂丂sa 丂丂akin 丂丂maganda 丂na. 斵丂丂搢抲昞帵丂乣偵丂巹乮偵乯丂桪偟偄丂 丂姰椆 乽斵偙偦偼 巹偵丂婛偵丂桪偟偄丅乿 偙偙偱丄"ay" 偼丄搢抲峔暥偱偁傞帠傪昞帵偡傞彫帿偱偁傞丅"na" 偼丄乽婛偵乣偱偁傞乿偲姰椆傪堄枴偡傞彫帿偱偁傞丅僞僈儘僌岅偱偼丄傾僗儁僋僩乮帪惂乯傗媈栤暥丄婓媮暥偺傛偆側丄儌乕僪乮朄乯傪昞尰偡傞偺偵丄偙偺傛偆側彫帿偑梡偄傜傟傞丅 拲乯丂昅幰偑嶲徠偟偨暥朄彂偱偼丄搢抲宍偺栿傕乽斵偼巹偵偡偱偵桪偟偄丅乿偲偁傝丄偙偺宍幃偼岞幃暥彂側偳偺傛偆偵僼僅乕儅儖側応偱巊梡偝傟傞偲偺偙偲偱偁傞丅偟偐偟嫮挷偺堄枴傕敽偆傜偟偄偺偱丄偙偙偱偼暘偐傝傗偡偔嫮挷宍偲偟偰偍偔丅 僞僈儘僌岅偵偍偗傞捠忢暥偼丄俙偺傛偆偵丄 弎岅丂彫帿乮帪惂丒朄乯丂庡岅丂栚揑岅乮側偳乯丂 偲偄偆倁俽俷椶帡偺岅弴傪庢傞偑丄嫮挷峔暥俛乮搢抲宍乯偱偼丄 庡岅丂ay 栚揑岅丂弎岅丂彫帿乮帪惂丒朄乯 偲偄偆傛偆偵丄擔杮岅偵椙偔帡偨丄俽俷倁椶帡偺岅弴傪帵偡丅堘偄偼丄乽巹偵乿偲偄偆奿昞帵偑丄sa akin 偲慜抲帉偵側偭偰偄傞強偩偗偱偁傞丅 廬偭偰丄傕偟傕丄僞僈儘僌岅偵偍偄偰乽昗幆宍偺僔僼僩乿偑婲偒傟偽丄擔杮岅偲岅弴偑椶帡偟偨尵岅傊偺堏峴偑壜擻偲側傞丅搢抲宍傪嵞宖偡傞丅 siya丂 丂ay 丂丂丂丂sa 丂丂akin 丂丂maganda 丂na. 斵丂丂搢抲昞帵丂乣偵丂巹乮偵乯丂桪偟偄丂 丂姰椆 乽斵偙偦偼 巹偵丂婛偵丂桪偟偄丅乿 搢抲宍偱偁傞偙偲傪昞帵偡傞 ay 偼丄倷 偲偄偆徣棯宍傪桳偟偰庡岅偵寢崌偟丄 siya'y 丂sa akin 丂maganda na.丂乮A) 偲傕尵偄昞偝傟傞丅傕偟偙偙偵丄擔杮岅偵椶帡偟偨尵岅偺塭嬁傪庴偗偰乽昗幆宍偺僔僼僩乿偵傛傞岅弴曄壔偑惗偠丄偦傟偑屌掕壔偝傟傞偵敽偄嵞夝庍偲僞僀億儘僕乕挷榓偑婲偒偨偲偡傟偽丄 saya-i 丂akin-sa 丂maganda-na.丂乮B) 乽斵偼丂丂巹偵丂丂丂丂桪偟-側偭偨丅乿 偲側傞丅偙傟偼丄忋偺暥乮A)偲傎偲傫偳宍偵曄壔偼側偄偑丄婛偵僞僈儘僌岅偲偼暿偺尵岅偱偁傞丅乮儌僠儘儞宯摑榑揑偵偼丄暥嬪側偟偺AN岅偱偁傞偑丅乯 僞僈儘僌岅偺 y < ay 偼丄偙偺乽怴尵岅乿偱偼庡奿昞帵偺奿彆帉 "i" 偵丄岦奿昞帵偺慜抲帉 "sa" 偼屻抲帉偵曄傢偭偰乮僞僀億儘僕乕挷榓乯丄彆帉偺 "sa" 乮乽僆儔搶嫗偝峴偔偩乿偺乽偝乿両乯偵丄姰椆昞帵偺 "na" 偼丄姰椆彆帉 "na " 偵曄壔偟偨丅 尰抜奒偱偼昅幰偺乽栂憐乿偵夁偓側偄偑丄偙偆偟偰惗偠偨偙傟傜偺宍懺慺偼丄偄偢傟傕屆戙擔杮岅偵偍偗傞彆帉丒彆摦帉偱偁傞 庡奿昞帵偺乽僀乿丗丂丂丂丂丂丂丂丂乽栄栰偺庒巕僀揓悂偒忋傞乿 曽岦昞帵偺乽僒乿丗丂丂丂丂丂丂丂丂乽廲僒偵傕偐偵傕墶僒偵傕搝乮儎僣僐乯偲偧変偼偁傝偗傞乿 彆摦帉乽僰乿偺枹慠宍乽僫乿丗丂丂乽挭枮偪棃僫傓乿乮挭偼枮偪棃偨偱偁傠偆乯 偲岅宍丄婡擻偲傕椶帡偟偰偄傞丅屻偼丄岅旜偺乽側乿偑彆摦帉偺岅姴偲嵞夝庍偝傟偰乽妶梡乿偡傟偽丄摑岅榑揑偵傕宍懺榑揑偵傕丄傎偲傫偳擔杮岅偲摨偠尵岅偵側傞丅 偙偙偵嫇偘偨乽僀乿乽僒乿乽僫乿偲偄偆岅宍偼尰戙僞僈儘僌岅偐傜摫偐傟偨傕偺側偺偱丄屆戙擔杮岅偺岅宍偲斾妑偡傞偺偼楌巎尵岅妛揑峫嶡偲偟偰偼柍堄枴偲偄偆斀榑偑偁傠偆偑丄乽僒乿偲乽僫乿偵偮偄偰偼丄S. Wurm/B. Wilson偺AN岅嵞峔宍帿揟(Ref #D-15)傪尒傞偲丄
偲偁偭偰丄AN慶岅偵丄乽偝乿乮応強奿乯丄乽側乿乮姰椆愙帿乯偑嵞峔偝傟偰偄傞丅乮乽僀乿偼尦偑丂ay 側偺偱丄屆戙擔杮岅乽僀乿偲偺斾妑偼儉儕偱偁傞丅乯 忋弎偟偨乽偐乿傪娷傔丄庢傝姼偊偢丄妉暔偑俁旵偐偐偭偨偲昅幰偼巚偭偰偄傞丅偙偺乽栂憐乿傪杮峞偺屻敿晹偱峏偵朿傜傑偡帠傪栚榑傫偱偄傞儚働偱偁傞偑丄偦偺慜偵丄尵岅愙怗偵傛傞AN岅曄壔偺幚椺傪挷傋偰偍偔偺偼丄崱屻偺榑巪偺揥奐偵傕丄傑偨崱傑偱弎傋偰偒偨僞僀億儘僕乕曄壔偵娭偡傞堦斒懃傪妋擣偡傞偲偄偆娤揰偐傜偟偰傕桳塿側帠偲巚傢傟傞丅 俈丏丂AN彅岅偺尵岅愙怗偵傛傞曄壔椺 摿偵嫽枴偑偁傞偺偼丄僞僀億儘僕乕偺曄壔偵墳偠偰愙摢帿偑愙旜帿偵曄壔偟偨俙俶岅偺椺偑偁傞偐偳偆偐偱偁傞丅偁傟偙傟偲挷傋偨偺偩偑丄崿崌尵岅偵娭偡傞榑暥廤 "The Mixed Language Debate" Edited. by Y. Matras/ P. Bakker (Ref. #LN-13) 乽崿崌尵岅傪弰傞媍榑乿 偱丄旕忢乣偵嫽枴偁傞僋儗僆乕儖尵岅偺懚嵼傪抦偭偨拲乯丅偦傟偼丄僗儕儔儞僇偵偍偗傞丄僗儕儔儞僇丒儅儗乕岅偱偁傞丅偙傟偼丄俙俶岅偱偁傞儅儗乕岅偲僞儈儖岅偺僋儗僆乕儖乮揑乯尵岅偱偁傞丅 僞儈儖岅偺摑岅峔憿乮僞僀億儘僕乕乯偑丄擔杮岅偲僜僢僋儕椶帡偟偰偄傞帠偼丄戝栰怶偩偗偱側偔丄僪儔償傿僟岅偺尃埿偱偁傞僘償僃儗價儖傕擣傔傞強偱偁傞丅乮愘峞嶲徠丂摿偵戞侾俁榖乯 偙偺尵岅偱偼儅儗乕岅傪慺嵽偵偟偰僞儈儖岅偺塭嬁壓偱俽俷倁宆偑惗偠偨丅椺偊偽丄 Se se-pe-bini-ka 丂duit 丂nya-kasi. 巹丂巹-偺-嵢-偵丂丂嬥丂丂夁嫀-梌偊傞丅丂亖丂巹偼巹偺嵢偵嬥傪梌偊偨丅 偲偄偆傛偆偵丄岅渂偼偡傋偰儅儗乕岅偱偁傝側偑傜丄岅弴偼俽俷倁偱丄儅儗乕岅慜抲帉婲尮偺 pe 傗 ka 偑丄屻抲帉偵揮梡偝傟偰偄傞丅椺偊偽丄ka 偼儅儗乕岅偺丄ke 偵懳墳偡傞丅乮Cf. ke pasar 乽巗応傊乿乯丂 偙傟偼傑偝偵丄倁俷偐傜俷倁傊偺曄壔偵墳偠偰丄慜抲帉偑屻抲帉偵曄壔偡傞偲偄偆丄乽僞僀億儘僕乕挷榓乿偺嫵壢彂揑側幚椺偱偁傞丅 偟偐偟丄偙偺尵岅偱偼帪惂傪昞傢偡偺偼愙摢帿偱偁傝丄乮nya 偼忋弎偟偨僞僈儘僌岅偺姰椆彫帿丂"na" 偲摨尮乯丄摦帉亄彆摦帉偺傛偆側擔杮岅偲摨偠乮偲偄偆偐僞儈儖岅偲摨偠乯宍懺偵傑偱偼曄壔偑恑峴偟偰偄側偄丅偙偺尵岅偺楌巎偼傎傏侾俉悽婭偵巒傑傞偺偱丄傑偩敪揥偺楌巎偑愺偡偓傞偺偐傕偟傟側偄丅 傑偨丄偙偺尵岅偱偼俙俶岅偺愙摢帿偼岅姴偵梈崌偟偨宍偱壔愇壔偟偰偍傝丄昅幰偑媮傔偨愙摢帿偑愙旜帿偵揮梡偝傟偨幚椺傪敪尒偡傞帠偼偱偒側偐偭偨丅 乮暥專丗丂K. Adelaar "Some notes on the origin of Sri Lanka Malay" Pacific Linguistics A-81p. 23) 偟偐偟丄嬌傔偰嫽枴偁傞尵岅偱偁傞帠偼娫堘偄側偄丅忋婰 Adelaar 偺榑暥偼丄僗儕儔儞僇偵偨偭偨偺侾廡娫懾嵼偟偰摼傜傟偨尵岅帒椏偵婎偯偔傕偺偩偦偆偱丄傕偭偲徻嵶側僨乕僞偑梸偟偄偲偙傠偱偁傞丅 拲乯丂偙偺尵岅偺懚嵼傪抦偭偨偺偼丄俀擭慜偺偙偲偱偁傞丅AN岅偲僞儈儖岅偐傜惗偠偨僋儗僆乕儖岅偲偼丄傑偝偵AN岅偲僣儞僌乕僗岅偑崿崌偟偨傜偳偺傛偆側尵岅偑惗偠摼傞偺偐傪悇掕偡傞偨傔偵丄揤偑梌偊偰偔傟偨幚尡椺偱偁傞偲丄偄偝偝偐偺嫽暠傪妎偊偨傕偺偱偁傞丅 偟偐偟丄偦偺偡偖屻偵丄嶈嶳棟巵偺乽僆乕僗僩儘僱僔傾岅懓偲擔杮岅偺宯摑娭學乿偲偄偆榑暥乮崙棫柉懓攷暔娰尋媶曬崘丂俀俆姫係崋丂p.465-485)傪擖庤偟偨帪偵丄僈僋慠偲偟偨丅傑偝偵偙偺榑暥偱偼丄僗儕儔儞僇丒儅儗乕岅偑丄擔杮岅偺惉棫傪榑偠傞暥柆偺尦偵丄俽倁俷尵岅偐傜俽俷倁尵岅傊偺曄壔椺偲偟偰庢傝忋偘傜傟偰偄偨偺偱偁傞両 僗儕儔儞僇丒儅儗乕岅傪擔杮岅惉棫偺嶲峫儌僨儖偲偡傞偲偄偆偺偼丄偦偺帪傑偱偼昅幰僆儕僕僫儖偺傾僀僨傾偩偲巚偭偰偄偨偺偱丄惓捈尵偭偰僈僢僇儕偟偨丅偟偐偟丄傑偁丄僘僽偺慺恖偑撈棫偵AN岅傪愱栧偲偡傞僾儘偺尵岅妛幰偲摨偠敪憐偵帄偭偨偺偩偐傜丄偙傟偼傓偟傠帺傜傪屩傞傋偒帠偩傠偆偲巚偄捈偡偙偲偵偟偨丅 幚偼丄忋婰偺嶈嶳榑暥偱偼丄俙俶岅愙摢帿偲擔杮岅愙摢帿偺斾妑傕専摙偝傟偰偄傞丅堦斒偵偼擖庤偟偵偔偄暥專偲巚傢傟傞偺偱丄師峞偁偨傝偱撪梕傪徯夘偡傞偮傕傝偱偁傞丅 傕偆僸僩僣丄昅幰偑拲栚偟偨偺偼丄僷僾傾彅岅偵愙偡傞俙俶岅偱偁傞丅僷僾傾僯儏乕僊僯傾偵僩傾儕僺岅偲偄偆尵岅偑偁偭偰丄偙傟偵椬愙偟偰俙俶岅偺俵俤俲俤俷岅偑偁傞乮壓恾嶲徠乯丅僩傾儕僺岅偑擔杮岅偲椶帡偟偨僞僀億儘僕乕傪帵偡帠偼丄侾俋俈俁擭偺擔杮尵岅妛夛偵偍偄偰峕幚巵偵傛偭偰巜揈偝傟偨丅偙偺屻偡偖偵丄戝栰巵偑偙偺愢傪庢傝忋偘丄僩傾儕僺岅偑擔杮岅偺婲尮夝柧偵峷專偡傞偩傠偆偲庡挘偟丄戝栰丒峕椉巵嫟摨偱丄擔杮岅偲乽懳墳乿偡傞僩傾儕僺岅偺儕僗僩偑嶌惉偝傟偨拲乯丅 拲乯丂偙偺曈傝偺帠忣偲偄偆偐丄峕丒戝栰愢偵娭偡傞昡壙偵偮偄偰偼丄懞嶳幍榊偺挊彂丄乽擔杮岅偺婲尮傪傔偖傞榑憟乿傪嶲徠偺偙偲丅乮嶲峫暥專丗丂#JP-15) 偪側傒偵丄昅幰偑俵俤俲俤俷岅偵峴偒拝偄偨偺偼丄戝栰巵偺榑愢偲偼壗偺娭學傕側偄丅俽俷倁偺岅弴傪帵偡俙俶岅傪扵偟偰俵俤俲俤俷岅偵扝傝偮偄偨傜丄偦偺椬傝偵僩傾儕僺岅偑偁偭偰丄乽偦偆偐丄側傞掱両乿偲巚偭偨師戞偱偁傞丅 僩傾儕僺岅傕傑偨丄僞儈儖岅偲摨偠偔戝栰怶巵悇慐偺擔杮慶岅偵懳偡傞婎憌尵岅偺僸僩僣偩偭偨儚働偱偁傞偑乮偮偄偱偵億儕僱僔傾岅傕両乯丄僩傾儕僺岅偵塭嬁偝傟偨俵俤俲俤俷岅傕丄僗儕儔儞僇丒儅儗乕岅偲摨條偵丄擔杮岅偲椶帡偟偨僞僀億儘僕乕傪帵偡丅俵俤俲俤俷岅偵偮偄偰偼丄A. Jones 偵傛傞 "Towards a lexicogrammar of Mekeo" 丂(Pacific Linguistics C-138 1998) 偲偄偆暘岤偄乮俇侽侽儁乕僕乯儌僲僌儔僼偑偁傞丅椺偊偽丄 lopia 丂丂丂丂imoi 丂丂丂丂oo 丂丂丂丂丂丂e-peni-a. 廢挿乮偼乯丂巕嫙乮偵乯丂僶僫僫乮傪乯丂偁偘傞丅 偲偄偆傛偆偵丄庡岅-娫愙栚揑岅-栚揑岅-摦帉晹丂偲偄偆傛偆側擔杮岅偲摨偠岅弴傪帵偡偑丄娞怱偺摦帉偺宍懺偵偮偄偰偼丄愙摢帿偺愙旜帿壔偼敪尒偱偒側偄丅 巆傞偼丄僆僙傾僯傾彅岅偵偍偗傞帠椺偱偁傞丅僼傿僕乕岅偵偼丄摨偠偲尒傜傟傞宍懺慺偑愙摢帿偲愙旜帿偺椉曽偵尰傟傞摦帉宍偑敪払偟偰偄傞丅愙摢帿宍偼帺摦帉偵丄愙旜帿偼懠摦帉偵尰傟傞丅 乮嶲峫榑暥丗 D. Arms "Whence the Fijian Transitive Endings ? OCL Vol. 12 (1973 ) p.503-558 乽僼傿僕乕岅懠摦帉偺岅枛巕壒偼壗張偐傜棃偨偺偐丠乿乯 杮峞幏昅帪偺嵟弶偺峔憐偵偍偄偰偼丄偙偺僼傿僕乕岅偺椺傪傗傗徻偟偔徯夘偟偰擔杮岅偺岅椺偲斾妑偡傞偮傕傝偩偭偨偺偩偑丄嫇偘傜傟偨岅椺偵愢摼椡偵寚偗傞傕偺偑懡偔丄偨偄偟偰嶲峫偵側傜側偄偲敾抐偟偨丅乮僆僙傾僯傾岅偺宍懺榑側偳夝柧偝傟恠偔偝傟偰偄傞偐偲巚偄偒傗丄偗偭偙偆晄柧側強偑懡偄偺偱偁傞丅乯 嶲峫傑偱偵丄僼傿僕乕岅偲俵俤俲俤俷岅偺応強偲暘婒忋偺埵抲傪帵偡丅
昅幰偲偟偰偼丄偐側傝偺楯椡傪旓傗偟偨偺偩偑丄巆擮側偑傜俙俶彅岅乮僋儗僆乕儖岅傕娷傓乯偵丄愙摢帿偑愙旜帿偵揮梡偝傟偨岅椺傪桳偡傞尵岅偼敪尒偱偒側偐偭偨丅 偨偩嫽枴怺偄偺偼丄俙俶彅岅偑懠偺尵岅偲愙偡傞廃曈椞堟偵偍偄偰丄婎杮揑偵偼倁俽俷偺岅弴傪桳偡傞俙俶岅偑丄尵岅愙怗偺塭嬁偱丄俽俷倁尵岅偵曄壔偟偨偙偲偱偁傞丅偩偲偡傟偽丄俙俶岅偺暘晍偡傞杒曽椞堟偵偍偄偰傕丄俙俶岅傪婲尮偲偟偨俽俷倁尵岅偑抋惗偟偨偲偟偰傕壗偺晄巚媍傕側偄帠偵側傞偩傠偆丅 俉丏師夞偺梊崘 偙偙傑偱尨峞傪彂偄偨強偱婥椡偑恠偒偨丅 杮峞偱恀柺栚偵庢傝忋偘偨愙摢帿丒愙旜帿偼乽偐乿偺傒偱偁傞丅 彂偒巒傔傞慜偵偼丄傕偭偲懡偔偺愙帿傪庢傝埖偆偮傕傝偩偭偨偺偩偑丄僼傿僕乕岅偲偺斾妑偑撢嵙偟偰榑巪偑曵夡偟丄傗傗棟榑揑偲偄偆偐曽朄榑揑側榖偟偑懡偔側偭偰偟傑偭偨丅 師夞偼丄杮峞偱弎傋偨棟榑揑懁柺傪傕偆彮偟曗嫮偟偰偐傜丄懠偺愙摢帿丄摿偵乽傑乿偵徟揰傪摉偰偨媍榑傪揥奐偡傞偮傕傝偱偁傞丅杮峞偱採帵偟偨乽栂憐乿偵偳傟偩偗愢摼椡傪梌偊傞帠偑偱偒傞偐偱偁傞偑丄傗偼傝愙摢帿丒愙旜帿偺埖偄偼擄偟偔丄偳偆側傞偐偼暘偐傜側偄丅 峏怴婰榐丗 丂丂
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||