「アイ ラヴ ユー」 の比較言語学 (Nostratic 起源の助詞について)
§3.助詞の起源 (九州弁「なんば しちょると!」の比較言語学)
定石通り、いくつかの助詞について、日本語の助詞とアルタイ語の接尾辞を比べ、日本語の古形を推定してから、印欧祖語と比べる事にします。
1.主格・対格接辞 ”pa/wo ”と印欧語 ”-ma”
日本語助詞のアルタイ起源説については、やはり、村山先生に登場いただく事になります。村山は、Greenbergの著書でも引用されているように、1957年のドイツ語の論文、”Vergleichende Betrachtung der Kasus-Affixe im Altai-Japanische" (「アルタイ-日本語の格接尾辞の比較考察」) において、初めて、日本語の「〜を」と、ツングース語の対格接辞、”-wo” および満州語の”-be ”の比較を行いました。ここでは、村山の文献3に沿って説明します。
両者の類似は、見るからに明らかなのですが、細かく用法を検討すると、更に顕著な類似性があるのです。
日本語では、「〜を」てのは、目的語の表示の他に、色々な役割を担っています。
| 1 | 場所の表示 | 「私は、森を通って行った。」 |
| 2 | 時の副詞の形成 | 「私は、三年を、ドイツ語の勉強に費やした。」 |
| 3 | 詠嘆・強調(古代) | 「あなにやし、えをとこを」 (古事記:国産み神話より) (訳: お〜、良い男じゃないか!) |
上に挙げた、1から3の用法は、すべてツングース語に存在します。
1とか2の用法は、我々は、意識せずに使ってますが、他の言語と比べると、目的語を表わす接辞が、場所や時の副詞、強調・詠嘆の表現のために使用されるというのは、考えてみれば、特異な事です。例えば、1と2を英訳するには、 through forest とか for three years とか、異なる前置詞を使わなければならない事を考えると、これらが当たり前の表現でない事が分かると思います。
このような用法が、細部に至るまでツングース語と類似している事は、助詞「〜を」がアルタイ起源である事の決定的な証拠です。
ツングース語の-wo は、語環境によって、 wa/w
 〜ma/m
〜ma/m 〜ba/b
〜ba/b 〜pa/p
〜pa/p と一連の「両唇音」を語頭とし、「中舌母音」/「前舌母音」を対立させる、語形を取ったと考えられます。
と一連の「両唇音」を語頭とし、「中舌母音」/「前舌母音」を対立させる、語形を取ったと考えられます。
前に、人称代名詞について検討した際、古代日本語の一人称複数: wa が、アルタイ語: bi/mi と対応した事を考えると、日本語の wo 「〜を」も、ba/ma/pa などに遡ると考えて良いと思われます。
九州方言、「なんばしちょると!」のba には、そのような古形が保存されていると考えられます。(これは、私のいい加減な推測でなく、村山の説です。)
「〜を」woが、ツングース語の3つ組、ba/ma/pa に遡り、その一つが、九州方言 ba に残っているとして、ヴァリエーションの一つ、 pa はどうでしょう?
主語を表わす「〜は」 は、奈良時代には、 pa でした。ha行が古代にはpa行だった、というのは、既に何回も説明した通りです。「〜を」は、目的語に付く助詞だと思っていたら、なんと、主語に付く「〜は」と起源が同じだという事になるのです。
これは不思議でもなんでもなくて、現代日本語で、「これは、使わないでください。」と言った場合の、「〜は」は、明らかに目的格であって、しかも、強調に使用されています。これは、上に挙げた古代の用法3の痕跡なのです。
私事ですが、小学生の時に、「〜は」は主語を表わすと教わった時、明らかにそれと異なる用法がある事に気づいて、「これは、おかしい」と、おおいに悩んだのでした。
遥か後年になって、村山説を知り、ようやく謎が解けた気になりました。
主格接辞の「〜は」は、元はツングース語の接辞、ba/pa に遡り、3に挙げた強調の用法から出発して、やがて主格を表わすように変化する一方で、ba/pa の子音と母音の異形「〜を」 w
 は、対格・場所・時を表示する役目を担っていたのです。
は、対格・場所・時を表示する役目を担っていたのです。
つまり、「〜は」と「〜を」は、起源となるツングース祖語まで遡れば、同じ語の変音ヴァリエーションと考えられるのです。これが、「〜は」が強調を伴った目的格(対格)にも使用される理由です。
いささかややこしいので、まとめると、
| ツングース語 | 日本語 | |
/ba/pa/ma/ 〜 /b /p /p /m /m / / |
→ | 対格: w > wo > wo |
| (対格・強調・場所・時の接辞) | → | 対格: 九州方言 ba |
| → | 対格: 古代 pa > 主格: pa > 現代 ha (〜は) |
となります。アルタイ語において、対格 -m を持つのは、ツングース語のみなのですが、モンゴル語にも、痕跡的な i-ma (彼を)があり、ウラル語に、祖語 -*ma を立てるのは定説だそうです。
変母音のaと
 は、母音調和を維持するためのもので、woは後者からの発展形です。また、主格と対格の混同や、強調などの種々の用法は現代に引き継がれましたが、なぜか、maは、日本語には、残りませんでした。
は、母音調和を維持するためのもので、woは後者からの発展形です。また、主格と対格の混同や、強調などの種々の用法は現代に引き継がれましたが、なぜか、maは、日本語には、残りませんでした。
(古代のワが、ワタシとして生き残ったのに、アルタイ代名詞のmi/mu も、なぜか現代日本語には、生き残りませんでした。不思議です。)
古代日本語では、元々は主格接尾辞なるものは、存在しなかったものと考えられ、この点については、国語学者の意見も一致してます。
ここで、このシリーズの一番最初に紹介した、Svitechがノストラティック語で書いた詩を思い出してください。
kela wete-i aku-n kahla
訳: 言葉(は) 時という 川の 浅瀬
というように、主語の「言葉」(kela)の語尾には、何も接辞がありません。恐らく、Svitechも、主格を表示する接尾辞は、後世になってからの発展形とみなしたのだと思います。日本語の「〜は」「〜が」は、本来、主語を表わす役を担ってはいなかったのです。
最初に、 I Love You. の日本語のヴァリエーションを、助詞の付け方を変えて作った例を出しましたが、
「わたし あなたが 好きです。」と主格接辞を抜いた方が、「わたしは あなたが 好きです。」
という表現よりもインパクトがあるのは、前者が古代の言葉により近いからなのです・・・
て事だったら、面白いな〜と思います。
さて、日本語 -wo/-wa が、アルタイ・ウラル語と結びついたところで、次に印欧語との比較に行きましょう。
印欧語では、対格(〜を)は、前に挙げた印欧祖語の再構形から知れるように、 -m で終わっています。ノストラティック仮説では、これを、対格接尾辞: -m の痕跡と解釈し、更に -*ma に遡ると考えます。
最古の印欧語であるヒッタイト語の例を見てみましょう。
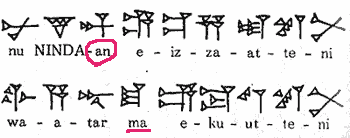 左の図は、紀元前2千年に、今のトルコの地に帝国を打ち立てた、ヒッタイト人の言語を記した楔形文字の例です。
左の図は、紀元前2千年に、今のトルコの地に帝国を打ち立てた、ヒッタイト人の言語を記した楔形文字の例です。
すでに解読されていたバビロニア楔形文字が音表記に用いられていたため(一部シュメール語が表意文字として混じってますが)、発音は「読めた」のですが、発掘から7年たっても、どういう言語を記したものか、分からなかったのです。
しかし、解読に取り組んだ、チェコ人、フロズニ(1879〜1952)は、ある日、この楔形文字のアルファベット表記を見て、「ヒラメイタ」のです。
この文字は、
nu NINDA-an ezza-teni
watar-ma eku-teni
と読めます。NINDAは、シュメール語のパンです。語尾の -teni は、ラテン語やサンスクリット語の動詞活用になんとなく、似てます。すると ezza- は動詞かもしれません。一見、荒唐無稽ながら、一行目の ezza- は、ドイツ語の「食べる」= essen に似ています。「もしかしてパンを食べる?」
すると、「もしかして、2行目の watar て、水か?!」「そうか分かった!!」
こうして、20世紀の言語学における最大の発見の一つとされる、最古の印欧語、ヒッタイト語解読の端緒が見い出されたのです。
赤で囲った、 -an は、まさしく、確認される最古の対格接辞の姿です。もしノストラティック仮説(あるいはユーラシア仮説)が正しいなら、これは、九州弁、「〜ば」の遠い遠い親戚なのです。
(では、水に付いてる -ma は何だって? 残念ながらこれはアッカド語なんだそうです。-an と -ma の使い分け? そんな難しい事、聞かないで下さい。)
ちなみに、「水を」と来れば、後は「飲む」ですが、 eku- は、ラテン語の aqua (水)と同源なのです。 water と aqua の起源は、こんなにも古いのです。
そして、aqua(水) の起源は、更に想像を絶するほど古いと思われるのです。
この話題については、次回に紹介しようと思ってますので、乞うご期待。
このように、ヒッタイト語は、4000年前のトルコで使われていた言語でありながらゲルマン語・ラテン語に近いという驚くべき特徴を備えているのです。
動詞活用形、 -teni は、グリーンバーグ流・ノストラティック流の解釈では te = 複数接辞、 ni = 二人称複数代名詞で、「あなた方」の意味です。実際、上の文章は、「汝等、パンを食い、水を飲む」と訳される事が判明してます。
上で述べたように、-*ma は日本語には、生き残らなかったのですが、かつては、-ba / -pa / と並んで、-*ma が機能していた時期が存在していたのが、-wa / -wo に統一されたものと思われます。
ツングース語学者のベンツィングは、上に挙げた wa/ba/ の用法の内、2については、「ツングース語と印欧語に共通しているが、他のアルタイ語にはない」と述べているそうです。
私のような素人は、すぐに「これは、ツングース語に残存するノストラティック的要素の一つではないか?」と思ってしまうのですが、多分、専門家は、こういう見方には冷たいのでしょうね〜。
とにかく、ツングース語を仲介として、日本語の「主格」「対格」の -pa/-wo は、特殊機能まで含めて、印欧祖語 -*ma と関連付けることができると思われます。(ウラル祖語の-*maに、対格以外の用法があるかどうかは、確認してませんが。)
2. 位格もしくは奪格 -t(a)
「奪格」「位格」なんて言葉は、普通、聴いた事もないでしょうが、まあ要するに「〜から」「〜で」を表わす格です。
今度は普段と順序を逆にして、印欧語から入ってみましょう。
「奪格」「位格」は、ラテン語で一部の単語が同じだったりして、区別が難しいです。上の表は、Beekesの教科書に載ってる形の引用なのですが、「狼」の場合、奪格では-d 、位格は -e です。
しかし、Greeberg によれば、位格語尾をサンスクリットの副詞「ここ」から -*dhe と再構する考えもあるそうで、ヒッタイト語を考えると、どうのこうのとか、けっこうヤッカイな議論が書いてあるです。でも、結局は、位格で ta 、奪格で -t と再構して議論してるので、ここでは区別しないでおきます。
ウラル語学者も、位格、奪格を区別して、それぞれ、-*t, -*ta と再構してるそうです。
次にアルタイ語ですが、「位格」については、ツングース語、モンゴル語、チュルク語から、に -da/-de, -du/-d
 が再構されます。
が再構されます。
Greenbergは、「位格」の日本語の対応語に、「下」(si-ta) に見られる -ta を挙げているのですが、実はもっとピッタリの古代日本語があるのです(ここから村山説です。)
万葉集の山部赤人の有名な歌、
「田子の原ゆ 打ち出でて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪ぞ 降りける」
に見られる、「ゆ」( -yu )です。
アルタイ語と日本語の音韻対応で、アルタイの d- と、日本語の y- は、けっこうキレイな対応を示す例の一つなのです。例を挙げると、
| 日本語 | アルタイ語 | |
| 夜 | yo | dolpa |
| 四 | yo | d rben rben |
| 山 | yama | daban |
| 装う | yosop- | dasa- |
| 湯 | yu | du:l (暖かい) |
てな所です。
日本語の「〜から」は、奈良時代では「〜ゆ」( yu )であり、音韻対応から、アルタイ語の du に遡ります。しかも、ツングース語には、「〜より」に対応する、 duli なんて形まであるので、両者の対応は明白です。
印欧語の「奪格: 〜から」「位格: 〜で(場所)」は、Greenberg によれば、 -t, -ta に遡るワケですが、 t →d の音韻変化は、良くあることなので、印欧語 〜 アルタイ語(特にツングース語)〜 日本語の対応は、かなり確実と言えるでしょう。
3. その他
こんな調子で、対応例を列挙していってもタイクツでしょうから、ここらでやめておきます。
グリーンバーグの本には、延々、200ページに渡って72種類の助詞、代名詞の比較が述べられているのですが、素人の私が言うのもなんですが、日本語の比較については「甘い」感じがします。
代名詞については、アルタイ語については、私が自分で調べたのより説得的な説明をしてます(ま〜当たり前か。)しかし、日本語の分析は、やはり「甘い」気がします。助詞・接辞に限って、日本語との関連が論じられているものを挙げると、
| 主格 | -k | 所有格 ŋa ? |
| 複数形成接辞 | -l/r | ko-ra (子等) |
| 所有格 | -n | -no (〜の) |
| 位格 | -ru | kochi-ra, dochi-ra (こちら等) |
| -n | ni (〜に) | |
| 呼格 | -e | -ya, -ye(これは私の説) |
| 名詞形成接辞 | -i- | 連用形の i (村山説と同じ) |
| 分詞(過去) | n | -nu |
| 現在分詞形成辞 | L | 動詞活用接辞 -r |
| 動詞形成辞 | -k- | 綱 > つな-ぐ |
| 否定辞 | -n | na 係り結びの「な〜そ」等 |
| 疑問辞 | k | 〜か? |
| n | なぜ? < na-nzo < na-n-so |
てところです。結局、72個の語から、対応する言語が少ない10個ほどの単語を除いた約60個の語の内、約3分の1の、20個で、ユーラシア語と日本語の対応が確認された事になっています。
日本語で「〜は」について重要な格助詞、-ŋa 「〜が」については、意味・用法ともにツングース語との対応には問題ないのですが、日本語・ツングース語では、所有格が元の用法で、対格・目的格の用法は、後世の発展形です。
印欧語では対応語に、ヒッタイト語の -*Ha しかなく、これを -Ka と再構してるのですが、大雑把に言うと、これは主格接辞で用法が合わないので、クエスチョンです。
助詞・接辞は、代名詞と違って種類や用法が複雑で、一筋縄ではいかないシロモノなのですが、上に示したグリーンバーグの比較例は、「ユーラシア語族」の存在と、日本語のそれへの帰属を支持するに足るものと思います。
しかし、本の内容をキチンと理解するには、私には荷が重い箇所も多く、ハッキリ言って消化不良です。前に検討した古代日本語の動詞活用体系の復元に、おおいに参考になりそうな記述もあり、勉強し直してジックリ検討する必要がありそうです。
§4. 「アイ ラヴ ユー」 の比較言語学
以上の結果を元に、再度、I love you. の再構形を、日本語と印欧語で比較します。今度は、英語 love のところには、文献4に従って、印欧祖語の再構形、 *leubh- を使います。これの原義は、「気にかける」「欲する」だそうです。活用は、教科書通り、O語幹にして一人称語尾 -mi をくっつけました。
ノストラティック語の対格は、 -ma です。
今のところ、ノストラ語の「好く」は不明なので、印欧祖語の bh が、ノストラ語の b に対応するものとし(文献6)、 *leubh- をO語幹・ゼロ-grade型にしておきました (この専門用語、自分でも良く分かってないので気にしないで下さい。)。
一方、古代日本語で、「わたしは あなたが 好きです。」を何と言うか、実は、これが、けっこうな難問だと、今になって気が付きました。動詞「好く」「求む」の使用は、奈良時代には確認されてません。
愛情表現て、「愛し(いとし、うつくし)」「かなし」、あるいは、もっと直に「欲し」とか、み〜んな形容詞を使ってるんですね。考えてみると、そもそも、日本語には、形容詞と形容動詞はあっても、愛情を表現する動詞がないんですね! (今初めて気づいた。)
「マグアヒ セム」ではなんだし、「思ふ」「想ふ」はイッパイ用例があるんですが、当人を前にして口にする言葉ではない、との事で(以上、文献5による)、困った。困りました。
これは、印欧人と、日本人の発想の違いで、言語というより、文化の差ですね。互いに離れている時は、動詞で「想い」、会っている時は形容詞で「現わす」てのは、なんとなく「日本的」て気がします。
そこで、古事記に出てくる「(八千矛の神)沼河姫を婚はむとして」の、「よばはむ」の語幹を使い、
(私が読んだテキストの注には、この語は「呼ぶ」を語義とすると書いてあるんだけど、後の展開みると、この神様のやってる事は、「夜這い」そのものなんですよね〜。)
yobap- < *dobap- < ?loba-
をデッチあげてみました。 y < d の変化は、上に述べた通り日本語 < アルタイ語で実証されてます。 dob- < lob- の音韻推移も、なんとなくありそう(と思います)。
これは、「ヨバハウ」(夜這う?)と love が同源という、わたしの「遊び」です。(上付きの?は「根拠なしの再構形」, Vは不明な母音の意味です。)
こうして、前回説明した動詞活用の古形も考慮すると、以下の対応が得られます。
| 現代英語 | I love you. |
| 現代日本語 | Watasi-wa anata-wo suk-i-des. |
| 古代日本語 | Ware si-wo yobapa-mu. |
| *プロト日本語(真面目な推定形) | B(/m)i si-ba dobap-ri-mi. |
| **プロト・プロト日本語(いいかげん推定形) | Si-ma ?loba-rV-mi. |
| 印欧祖語(教科書通り) | |
| ユーラシア祖語(いいかげん推定形) | Si-ma ? lob-V-mi. |
この対応表に、前回(人称代名詞・動詞活用)と今回(助詞)の検討結果が集約されてます。 (黒字の所はすべて真面目な再構形です。)
プロト・プロト日本語の訳は、「我 汝を 呼ぼう(結婚しよう)。」で、印欧祖語は、「我 汝を 求む。」です。
繰り返しになりますが、「プロト日本語とプロト印欧祖語の間に見られる、基本文法の細部に至る類似性」は明らかだと思います。(動詞の活用についてはもっと深い解釈が必要ですが。)この類似は、日本語・アルタイ語・ウラル語間にも存在し、従って、これを基本に、ユーラシア超語族なる概念を設定するのは、ごく自然な発想であり、けっしてこの仮説が荒唐無稽なものではない事が言えると思います。
人称代名詞の一人称・二人称(主格/目的格)が、b/m, t/s のシステムを持つ事が、この仮説の最大の根拠になってるワケですが、ある言語の子音の平均数を、仮に20種類として(これは少ない方です)、このようなシステムが、ある言語で偶然に発生する確率は、後者はtかsのどちらでもOKなので、(1/20)^2x(2/20)^2=3E−6になります。4つの語族で、このシステムが偶然、まるごと一致する確率は、その4乗で、4E-19になります。小数点以下、ゼロが19個です! 5つの語族だと、ゼロは23個。
更に、今回検討した助詞が計算に加わります。「〜を」「〜ゆ」の他、上の表で言うと、否定辞:「な」、所有格:「〜の」、疑問辞:「か?」を含めた、最低、5つは、確実な対応だと思います。それだけで、偶然の一致の確率は、更に、(1/20)^5 = 3E-7 に減ります。
助詞は、「ガンコ」な文法要素で、上の5つの内、4つが現代まで生き残りました。文法システムの異なる言語からの借用は、代名詞よりも更に、起こりにくいと考えられます。
いかに偉い比較言語学者が、何と言おうと、この事実を覆す事は、不可能だと思います。
「アイ ラヴ ユー の比較言語学 」などと、ふざけた題名の文章を書きましたが、日本語には、古来、こういう愛情の表現は無かったという事が、文法比較の最大のネックになってしまいました。
でも、これは、挙げた例が悪かったんで、全体の論拠が崩れるワケではないから、まあ、良しとしましょ〜〜。もしかして、ホントに「夜這い」と、love が同じ起源かもしれないし・・・(なワケない!)
やはり、日本人は「愛する」でなく「想う」民族なんでしょうか。
次回以降の予定
これまでの検討で、細部に問題はあるものの、古形に遡ると、「日本語の骨格は、印欧語と非常に似てる事」は、自分なりに納得したのですが、「それでは日本語とユーラシア語族以外の、他の語族との関係はどうなっんだ?」て事も検討しないといかんのではないかと思ってます。
そもそも「日本語は、アルタイ語と南島(オーストロネシア)語のハイブリッド言語である」というのが、このシリーズのPart Iの結論だったワケです。南の島の言語との関係はどうなってしまうのでしょうか?
どうせ先は、まだまだ長いので、近視眼的な見方に固まってしまわないためにも、ここらでいったん、広く世界に目を転じてみるのも良かろうと思います。意外な発見があるかもしれません。そして、言語におけるもうひとつの重要なシステム、「数詞」についてあれこれ考えてみるつもりです。
参考文献
| 1. | J. Greenberg | Indo-European and its Closest Relatives vol.1 Grammer (2000) Stanford University Press |
| 2. | R. Beekes | Comparative Indo-European Linguistics -An Introduction- (1995) John Benjamin Publishing |
| 3. | 村山七朗 | 日本語の起源 (1976) 弘文堂 |
| 4. | C. Watkins | The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots (2000) Houghton Mifflin Co. |
| 5. | 大野晋他 編 | 岩波 古語辞典 増訂版第12刷 (2000年) 岩波書店 |
| 6. | A. Dolgopolsky | The Nostratic macrofamily: a short introduction; in Nostratic Examining a Linguistic Macrofamily (1999) the McDonald Institute |
| 7. | 矢島文夫 | 解読 古代文字 (2001) 筑摩書房 |