|
匈奴は何語をしゃべっていたか? -アルタイ比較言語学入門- §6.匈奴の王名をトルコ語で解く この節では、匈奴語をトルコ語で解けるものがあるかどうか、検討します。 匈奴王(単干)名の表記は、ほとんどが匈奴語の漢字音訳ですが、中には例外的に漢語が用いられている例があります。 例えば、第7代の烏師廬単干ですが、歳が若かったので、「児単干」と名乗ったとあります。モチロン、「児」は匈奴語ではなく、漢語です。 私が注目するのは、冒頓単干の子、稽粥です。彼は即位すると老上単干と称したのですが、これは、漢語だと思います。「老」の語頭子音は L- で、匈奴の王名としては、他に例がありません。また、「老上稽粥単干」と、即位前の匈奴語の名前と、即位後の名前と合わせて表記されているのが特異で、この表記は、 稽粥 (匈奴語の音訳) ⇔ 老上(漢語訳) という対応を示したものと推定されます。これは、匈奴語が何語であるかを示す、極めて重要な手掛かりと思われます。 「稽粥」の音は、稽(ker-kei) + 粥(čiok-čIuk)で、上古音(青)、中古音いずれで読んでも、 keč(o/u)k を表記したものと思われます注)。 注) 上古音の推定形に関する議論(文献#75参照)については、ここでは立ち入らないことにしておきますが、稽の古音がkerだったのかについては疑問があります。私自身は、語尾の-r を推定する根拠は薄弱だと考えます。 古代チュルク語辞典(ロシア語: Древнетюркский Словарь 以下ДTCと略)を調べると、 KEčKI : 「昔しの」 「以前の」 「持ちこたえた」 という単語が見つかりました。「長い間続いた平和はかなたに過ぎ去った」(QBN)という例文が引用されています。QBNというのは、「12世紀末から13世紀中頃に書かれたと推測されるタシケントで発見された文書」だそうで残念ながら、突厥碑文で確認されるような古い単語ではありません。 古代チュルク語のK-は現代トルコ語のG-に対応し、この語は現代トルコ語の gečkin (年輩の)に変化しています。一方、現代トルコ語にはこれにやや意味が類似した koca (広大な、年取った)という語があります。古代トルコ語では、QOC(Z?)A になるハズなのですが、ДTCには対応語が発見できませんでした。 稽粥; keč(o/u)k(「老上」)と KEčKI (「昔しの」・「持ちこたえた」)の音韻と意味の対応は偶然とは思えず、匈奴語がトルコ語であることの有力な証拠になると思います。(匈奴王名の解読は18世紀から試みられているので、この「解読」が私のオリジナルな発見かどうかは分りません。多分、先人がいるものと思います。) 「老上稽粥単干」のように漢語の手掛かりがある王名はこれしかなく、他の王名は「語呂合わせ」になってしまいます。 この稿を書くキッカケになった、「呼韓邪」ですが、文献#k1によると、Hirthというドイツの学者が、トルコ語での解読を試みたそうですが、なにしろ1900年の論文では私には入手の手段もありません。なんでも、彼は匈奴語は、トルコ語の中ではウィグル語が最も近いなどということまで言っているそうです。 「呼韓邪」の発音は、 (h)oghanya/ (h)oγaya だと思いますが、ДTCで目ぼしい単語を探すと、oγlan くらいしか思いつきません。 もしモンゴル語だったとしたら、 oqa:n (知力のある)あたりと比較したいところですが、最後のyaをどう処理したら良いかが分かりません。 根拠に乏しい事は承知の上ですが、oχlan = oγanya ( la > nya の交替を仮定)であり、「呼韓邪」は「息子」という意味のトルコ語だったのではないかと推定しておきます。 §7. 古代トルコ語の音韻との整合性について 今回の検討で得られた結果が、古代トルコ語の音韻に関して知られている事実と比較します。 トルコ諸方言との比較 下の表は、トルコ語の各方言を、「足」と「山」の語形を指標として分類したものです(池田:「アルタイ語のはなし」 #k-9 p.9の表を元に作成)。 池田氏の著書では、I〜XIIの、12の方言が分類されているのですが、ここでは突厥語の「山」も入れて簡単化して示します。
トルコ語学者のDoerferの説では、IIのハラジ方言が最古の語形を保存しているとのことです(前掲書 p. 199)。また、IXのウィグル語は、古代トルコ語(突厥語)に近いそうです。 ハラジ方言では、頭子音のh-は、アルタイ祖語の*p-の反映(*p > *f > h)と考えられ、「山」の頭子音tも、突厥語と同じです。また、また、この方言では、第二子音が d で、現トルコ語で生じた d > y の音韻変化が生じていません。この方言はチュルク祖語い近い最古形を保存していると考えられています。 匈奴語の頭子音分布を見ると、pの頻度が小さくbが多くそれなりにhが多い。これは、もしかしたらハラジ方言のような古形の残存である可能性があります。しかし一方で、dとtの割合がほとんど同じで、この点では匈奴語は不思議と新しい語形を有しているように思われます。こんなことが、トルコ言語学の観点から有り得るのだろうか、という疑問が生じます。 これが本当に匈奴語の特徴なのか、それとも中国語(漢字音)への音訳によって生じた見かけ上のものなのか検討する必要があります。これは、そもそも、最初に検討すべき事項だったのですが、匈奴語が古代トルコ語ではないかという仮説を出した後の方が説明しやすいと判断して後に持って来ました。 突厥碑文との比較 上で中国史書に現れた突厥語と推定される語の頭韻分布を求めましたが、突厥は独自の文字を用いた碑文を残しています注)。これらの碑文は解読されていて発音も判明しているので、突厥語がどのような頭韻分布を有していたかを、漢字音を通してではなく、彼ら自身が用いた文字から求める事ができます。 注) 例えば「解読古代文字」 矢島文夫著 ちくま学芸文庫 参照 下に示すのは、中国史書に現れた突厥語と、碑文の単語から求めた頭韻分布を比較したものです。 (突厥碑文データには、Tonyuquq碑文、Bilgä-qaγan 碑文、šibe-usu碑文、Kül-tugin 碑文に現れる、異音異義語100語を用いた。ДTCのロシア語を読むのがシンドイので語数が少なくなってしまった。) 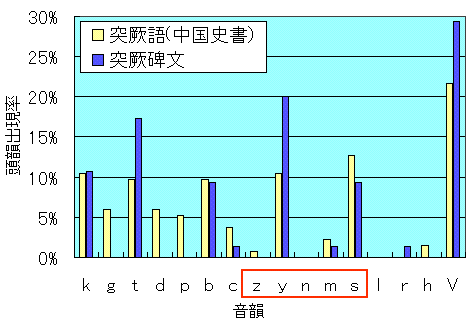 中国史書と碑文から求めた頻度分布の違いは、有声音 g、 d と、無声音 p音です。 突厥碑文では、n d がなく、 y の頻度が非常に大きくなっていますが、これは前に述べたように、n、d、が y に合流したためです。また上のグラフでは k に一括して表示したのですが、突厥語では、喉音に、KとQがありましたが、g音は存在しませんでした。 中国史書から抽出した「突厥語」では、g・d・pの頻度が突厥碑文のものと一致しません。これは恐らく、7世紀半ば頃から、中国語において有声音(g/d/b)が無声音(k/t/p)化したために、有声音と無声音の間で表記の混乱が起きたものと(取り合えず)解釈する事ができます。 中国史書から求めた頭韻分布にはこのような問題があるのですが、それでも、 /z/y/n/m/ (s)に注目すれば、古代トルコ語の特徴を判定できる。 という「仮説」は成立すると言えます。 ここで、中国史書から求めた突厥語・匈奴語の音韻分布の比較を再掲します。 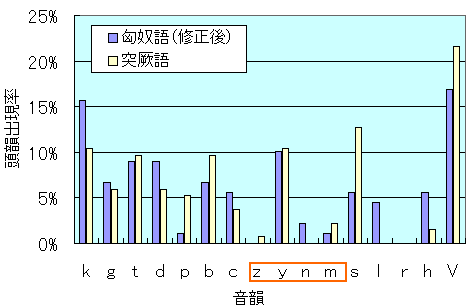 漢書が書かれた時代には、唐代で起きた有声音と無声音の混乱は生じてなかったので、「匈奴語」にはg、d 音が存在したことになります。しかし、y音の頻度が大きい事、n音の頻度が小さい事から、匈奴語には突厥語で生じた、n、d音の y音への融合が既に起きていたと推定するのが合理的と思われます。 また、古代トルコ語のk音がg音に変化したのはずっと後世の事です。 すると、なぜ「匈奴語」にd音とg音が存在するのか、という疑問が生じます。 3つの可能性があります。
結局、漢書に収録された「匈奴語」には、別民族の語彙が混入していると解釈するしかなさそうです。すると、「匈奴語」の頭韻分布から言語を同定しようという手法自体の信頼性が損なわれる事になり、残念ながら、ここが論拠の弱点ではあります。 しかし、このような問題があるにせよ、
「匈奴語はトルコ語である。」 は、かなりの確実性を以って示すことができたのではないかと考えます。 また、本稿の検討結果によると、匈奴は最古形を保持すると言われるハラジ方言(dがyに変化していない)やチュワシュ方言ではなく、むしろウィグル方言(dやnがyに変化)に近い言語をしゃべっていた事になります。上で紹介したように、Hirthというドイツの学者が、匈奴語はトルコ語の中ではウィグル語に最も近いと結論したそうですが、私の検討でも同じ結論に至りました。Hirthの論拠が分らないのがいささか残念です。 今回は、匈奴語の音韻を調べたのが「漢書」までだったのですが、「後漢書」、できれば「晋書」あたりまで、匈奴の末裔達の言語を追跡し、中国内の音韻変化によって表記が変化したかどうかも確認する必要があります。 このテーマについては、古代トルコ語や南匈奴の歴史について勉強して、また改めて論じたいと思っています。 更新記録: 2004年7月29日 論旨改訂 「古代トルコ語辞典」(ロシア語)のデータを追加。 この辞書がまともに読めるようにならないとイカン。 「おまけ」に、1900年に出版されたHirtという学者による「フン族が匈奴の直系子孫である事を証明した論文」の要旨を追加。 |