| ����N��w�̗L�����ɂ��� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�W�N�S�� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���{��̒a���͖퐶���ꕶ���H ����́A�O�e�ŏЉ�����{���̒����u���E����̂Ȃ��̓��{��v�ŏq�ׂ�ꂽ�ȉ��̎咣�̑Ó����ɂ��Č��������B �u���{�ꂪ�A�퐶����̎n�߂ɁA���m�̑������i�Ⴆ�Β��N���^�~����j����̕���ɂ���Ēa�������Ƃ���A�����̌���Ɠ��{��Ƃ͑f�l�ڂɂ�����ȂقǗގ����Ă���n�Y�ł���B�Ƃ��낪���܂łɕ���ꂽ����ȓw�͂ɂ��ւ�炸�A���̂悤�Ȍ�������o�����Ƃ��ł��Ȃ��B����́A���{��̑����ꂩ��̕���r����w�̎˒��ł����T�`�U��N���������ߋ��ɐ��������߂ƍl������B���{��̃��[�c�́A���j����w�̐��Ƃ�����܂ł��܂ɐG��Ďw�E���Ă���悤�ɁA�퐶������z���ēꕶ�̉ߋ��ɂ܂ők��ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B ���{���̌����A�u���j����w�̐��Ɓv����̓I�ɒN�̂��ƂȂ̂��M�҂ɂ͕���Ȃ����A���a�R�Q�N�ɕ����l�Y���ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �u�S�������̈��E���Ȃ����A�ł��W�R���̑傫�������Ƃ��āA���͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă���B�����A���{����܁A�Z��N�i�ȏ�H�j�O�ɒ��N��ƕ���A�i�����{�i�y�ѓ쒩�N�H�j�ɘb����Ă������A���̂����̖k��B�ɘb������������A�I���O���S�N�O�����瓯�n���ɓn���������ꂽ�O����������퐶�����̑傫���e���̉��ɁA���{�c��ւƔ��B�����B�v�@ �i�u���{��̌n���v�@��g���X�@p. 232 �@�����͈��p�ҁB) ���{�������������A�퐶����ɂ�����ڏZ�ҁi�n���l�j�Ɛ��c���������핶���̓������A�ꕶ����ɓ��{�Řb����Ă����i���j����Ƃ��̕��z�Ɍ��I�ȕϓ��������N�����A���ꂪ���{��a���̌_�@�ƂȂ�������͓̂����ł���B���҂̈Ⴂ�́A���{�i�c�j��Ɋ�{���i������ꕶ����̌���i���Ɂu�����{��v�ƌĂԂ��Ƃɂ���j���A���{���͑O�e�ŏЉ���悤�Ɍ�������p�^�[���̗ގ��������Ƃ��ē���n����ƌ���̂ɑ��A�������͒��N��Ƃ�����̓I�Ȍ��ꖼ�������Ă������j�_�ɂ���B ���j�@���R�̂��ƂȂ���A�T�C�U��N�k���������N��Ɂu���N��v�ƌ������錾�ꂪ���݂������ǂ����͕s���ł���B ���{��͓ꕶ����܂ŋN����k�錾��Ȃ̂��A����Ƃ��퐶����ɊO������̈ڏZ�҂ɂ���Ă����炳�ꂽ����Ȃ̂��H ����́A��X�̑傫�ȊS�������e�[�}�ł���B�ʂ����Ĕ�r����w�͓��{��a�����N���ɂ��āA�ǂꂾ���M���ł�����������̂��낤���H �����Œ��ڂ����̂́A�����Ƃ��Ɂu�����{��v�̒a�����T�`�U��N�O�iBC3000�`4000�N�j�����͂�����Â�����ɑz�肵�Ă��鎖�ł���B����́u����N��w�v�Ƃ����A��ʂɂ͂��܂�M�p����ĂȂ��w���������ɂ��Ă���B �{�e�́A���́u����N��w�v�̗L�����̌�������v�ȃe�[�}�ł���B ���Ȃ݂ɁB �ȉ��̋c�_�ɂ����āA�퐶����̊J�n�N������ɐݒ肷�邩�����ƂȂ�B2003�N�ɁA�������j���������ق̌����҂ɂ��A��C���̂b14�Z�x�̕ϓ����l�������Z�����s�Ȃ��ƁA�]�����̂a�b�T�O�O�N�ł͂Ȃ��a�b�P�O�O�O�N�Ƃ���̂��Ó��Ƃ����������o���ꂽ���l�Êw�҂���͕s���̐����o�Ă���悤�ł���B�u�퐶����̎n�߁v�����Ƃ��邩�́A���݂̂Ƃ��떢�m��Ƃ������ɂȂ�B ���āB ���{��ƒ��N��̔�r�Ɋւ��ĕM�҂��O����C�ɂȂ��Ă���̂́A���{�E���������̎咣�ɋ��ʂ���ȉ��̂悤�Ȍ����ł���B �u���{��ƒ��N��̊Ԃɂ͔�r����w���v�����錵���ȉ��C�Ή������o�������ł��Ȃ��B����͗��҂̕���N�オ��r����w�̗L���˒��ł���T�`�U��N�������Ă��邩��ł���B�v �M�҂��C�ɂȂ�̂́A�u�����ȉ��C�Ή��̑����v�Ɓu��r����w�̗L���˒��͂T�`�U��N�v�̂Q�_�ł���B��r����w�Ŋm�����ꂽ�m�������ɂ������̃t���[�Y�́A���{��̋N����_����ꍇ�ł��{���ɗL���Ȃ̂��낤���H �Ƃ������ƂŁA�u����N��w�v�ɂ��ĉ]�X����O�ɁA��{�ɗ����߂�A����������r����w�̎�@�Ƃ͂����Ȃ���̂ŁA���̌��E�͂ǂ��ɂ���̂��A�����L���ɋ@�\������ɂ͂ǂ̂悤�Ȓ��ӂ��K�v������̂��M�҂Ȃ���l�������Ă݂邱�Ƃɂ������B ���Ƃ����āA����w�̋��ȏ��̈����ʂ��̂悤�ȋL�q���J��L�������͂Ȃ��B�����ŁA�ȉ��̂悤�ȉ��z���E�ɂ����錾��w�҂̉ˋ�̘_����z�肵�Ă݂邱�Ƃɂ����B�ǂ�Œ�����Ε���悤�ɁA����͓��{��n���_���߂���_���j�̈ꑤ�ʁi�����܂ňꑤ�ʁI�j���p���f�B�ł���B ���z���E�ɂ�����p��n���_������_�� ���͌���̃��[���b�p�B �A�����̐��E�ɂ�������j�̗���͌����Ƒ傫���قȂ�A�P�R����P�S���I�ɂ����ă��[���V�A�嗤�̓����S���鍑�Ɋ��S�ɐ�������A�قƂ�ǂ̃��[���b�p�̌���̓����S����ɓ��������ł��Ă��܂����B �×�����̌�����p������̂́A�͂��Ƀm���}���f�B�[�����ɐ����c�����t�����X�Ɠ����C�M���X�̂݁B�������Ñォ��ߐ��Ɏ����ՁE�����͐헐�ɂ�肱�Ƃ��Ƃ��������A���ꎑ���͂��������Q�`�R�S�N�O����̂��̂����c�����ĂȂ��B�t�����X�͑僂���S���鍑�̏]�����ƂȂ��Đ������т����A�����S���R�̃h�[�o�[�C�����f�����l���\���������p���C�R�̊���ɂ���Ėh�����C�M���X�͓Ɨ����ێ������B�i�b������₱�����Ȃ�̂ŁA���̐��E�ɂ̓A�����J�嗤�͑��݂��Ȃ����Ƃ���B�j ���̐��E�ł��P�X���I�ɂȂ��Ă���A��r����w�����B���A���[���V�A�嗤�̃E�����ꑰ�A���A�W�A����I�Z�A�j�A�̃I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�A�A�t���J�嗤�̃o���g�D�[�ꑰ�Ȃǂ̊T�O���m������B�i�Ӌ��̒n�ł͂܂��Ǝ��̌��ꂪ�������тĂ���B�j���E�̎x�z�҂��郂���S���l�̌���ɂ��ẮA�A���^�C�ꑰ�������������̐^�U�������Ę_���������Ă���B�����S���x�z�n��ł́A�`�����N�E�c���O�[�X��̓����S���ꂪ�N���Ƃ������݂̂����F����Ă���B ���̂悤�ȏ�w�i�ɁA�p��̌n�����ɂ��Ă������Ș_�����s�Ȃ��n�߂��Ƃ���ł���B �����A����p��ƃt�����X��̃f�[�^�����g���Ȃ��Ƃ����������������ۂ����ꍇ�ł��A���̉��z���E�̌���w�҂́u�����v�ɒH�蒅�����Ƃ͂ł��邾�낤���H �t�����X�l����w�҃\�V�|�����̐��͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�������E�̉�X�́A��̕\�ɋ������P�ꂪ���ׂ��t�����X�ꂩ��̎ؗp��ł��鎖�A�u�p��̓t�����X�ꂩ�琶�����v�͊ԈႢ�ŁA�u�p��ƃt�����X��͈c�ꂩ�番��������v������������m���Ă���B���̓�͖��m�ɋ�ʂ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ł́A�����̎��͂��̉��z���E�ɂ����Ă����؉\���낤���H ���̐��E�ł͌ꑰ�̊T�O���m�����Ă���̂͂�������P����i�I�j����ɂ��Ăł����āA��b��r�Ɋ�Â��Čn���W���ؖ������@���嗬�ɂȂ��Ă���B�p����t�����X������܌���I�ȗv�f�͂قƂ�ǖ������Ă��܂����̂ŁA��͂��b�̔�r�����_�̊�{�ƂȂ�B�������A�p���̎�������ގ������`�����P����o���ė��A���Ƃ����ꂪ7500��i�I�j�Ƃ����c��Ȑ��ƂȂ��Ă��A����ł͐����ɒH����Ȃ����́A�\�V�[�����̗Ⴉ�疾���ł���B ���́A�ǂ̂悤�Ȍ�b���ǂ̂悤�ɔ�r���邩�ł���B �M�҂́A�ȉ��̗Ⴊ�����悤�ɁA�u��b��b�v�Ȃ�T�O�͂���Ȃ�ɗL�����ƍl����B���̉��z���E�ł̓A�����J�̌���w�҃X���f�B�b�V���͑��݂��Ȃ����A�܂��͔ނ�������b��b���r���Ăǂ̂悤�ȗގ����������ł��邩���ׂĂ݂邱�Ƃɂ���B �A���A�X���f�B�b�V���̂P�O�O�ꃊ�X�g�𗅗�̂͂��������ʓ|�ł���B�ȉ��ł͕M�҂��ƒf�Ō��I�����S�O�ꃊ�X�g���g�����Ƃɂ���B�{���͒Ԃ�ł͂Ȃ������L���ŋL���Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�Ԃ�̕����Ì`�f���Ă���̂ŗǂ��Ƃ���B�܂��A�ǂ��m���Ă���悤�ɁA��̌n���_�ł͐������d�v�Ȗ������ʂ����̂����A���{��̒u���ꂽ�ƍ��킹�邽�߂ɏ������Ƃɂ����B�t�����X��̐����́A���ׂă����S���ꂩ��̎ؗp��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��Ă����B �v���̔�r����w�҂ƂāA�ŏ��ɂ�鎖�͓����ł���B��芸�����A�����̉\������������s�b�N�E�A�b�v����̂ł���B�����ŃZ���X������郏�P�����A�ǎ҂����̉��z���E�̌���w�҂ɂȂ�������ŁA���̌�b��r�\���W�b�N���ƌ��čl���Ē��������B
�M�҂��I�������̂́A�ΐF�Ŏ������P�Q��ł���B���F�̒P��͂�����ƔY�����O�����B�i31�Ԃ́u�X�^�[�v�Ɓu�G�g���[���v�������Ǝv���l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H�j �p���"�h �i���j"�i�����̓A�C�����Ԃ肾�ƃC�[�j�ƃt�����X��� "je "(�W��)�������ł��邱�Ƃ͕����Ă��邪�A���̌�`���u�����̉\������v�Ɣ��f����l�͓V�˂ł���Bwhat�@(/hwat/) ���t�����X��� que(/ ku/) �������ƌ��j��l���V�˂ł���B �t�ɁA�p��� fly /fire / woman���t�����X��� voler /feu/ femme �Ƃ͖��W�ƍl����l��������A��قǂ̕ς��҂ł͂Ȃ����Ǝv���B�������A���̂R��͑��l�̋��U�҂ł����B�ς��҂ł��V�˂ł��Ȃ��M�҂��I�������ގ���̐��͂P�Q�ꂾ���A�U�҂��R��A�����Ȃ̂ɂ��蔲���Ă��܂����̂��R��ŁA�{���̓����ꐔ�P�Q��Ƌ��R�Ȃ����v����i�E�E�E�Ǝv���B�M�҂̓t�����X�ꂪ�S�R�ł��Ȃ��̂Ŏ��͎��M���Ȃ��B�j�ގ���`�̏o�����́A�P�Q/�S�O���R�O���ɉ߂����A���قǍ������P�ł͂Ȃ��B ����́u�p��̓t�����X��̈�����ł���ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B�v�Ƃ����\�V�[�����ɂ͑傫�ȃ_���[�W�ł���B �t�����X�ꂩ��p��ւ̎ؗp��̐��͏�ɏq�ׂ��悤�ɂV�T�O�O�������ƌ����Ă���̂ŁA��r���u��b��b�v�ɍi��Ƃ����헪���ؗp��̍�����h���A������̌n���W��_����̂ɗL���ł��邱�Ƃ�����B�i���`�����A�ؗp������S�ɃV���b�g�E�A�E�g�ł��郏�P�ł͂Ȃ��B��b��b�ւ̃t�����X��̐N�����͖�R���ł���B�j ���̌��ʂɊ�Â��A�u��ؐl�v�ƌ��ߕt�����Ă����p���l�͔��_�ɏo��B�s�D Borrow ���́A�p��̓t�����X�ꂩ��h�������̂ł͂Ȃ����m�̌��ꂩ��u���e�����ɂ����ēƎ��ɔ��������Ƃ����u�p�ꎩ�����v���咣���A�\�V�[�����ƑΗ�����B �܂��A�ʂ̃C�M���X�l����w�ҁA�v�DJaws���́A�u�p��ƃt�����X��̕���͔��ɌÂ��N��ɟ��ƍl������B���҂͍��ł͏��ł��Ă��܂������鋤�ʂ̌����番����Đ��������̂ɈႢ�Ȃ��B�v�Ɨ\���I�Ȑ����咣����B�܂�����҂́A�t�����X�l�w�҂Ƃ͔��ɁA�t�����X�ꂱ�����p�ꂩ�番�Ăł����̂��Ǝ咣����B ���̍����ɍX�ɔ��Ԃ��|�����̂��A���{��w�҂� S. Ohne ���ł���B�ނ́A�p��ƃt�����X��ŗގ�����P�Q��̂����A���ɂX�ꂪ�Ñ���{�����j�Ɖ��߂����Ƃ��i���\�j�A���ɁAwomina �Ɓ@woman �̗ގ��́u�����ċ��R�ł͗L�蓾�Ȃ��v�Ǝ咣����B ���j���{�͂��̐��E�ł����������ނ��ēƗ���ۂ��Ă���A�Ñ㕶���̏�����Ƃꂽ�B���{�����ł͓��{�ꃂ���S���N�������ł��L�͎�����Ă���B
�q���i�h�j��t���i�U��j���u��ԁv�ƊW�t����͉̂�Ȃ��炠�܂�ɋꂵ���Ƃ͎v�����A���̂悤�ȃ^�O�C�̃R�W�c�P��r�́A���{��n���_�ł͂悭��������Ƃ���ł���B�i�M�҂��������Ȃ�������Ȃ��E�E�E�B�j Ohne���ɂ��A�P�Q�`�P�R���I�ɂ����ă��[���b�p�𐪕����������S���R�c���ɓ��{����o�������u�T�����C�v�ƌĂ��R�m�W�c�����݂��A�ނ炪�t�����X�𐪕�������A�X�ɉp���ɓn��A�ޓ��̌��ꂪ��w��ƂȂ��ăt�����X��E�p�ꂪ���܂ꂽ�Ƃ���B�t�����X��Łu�R�m�v�́Achevalier �i�V�����@���G�j�ł��邪�A����́A�u�T�����C�v�ٌ̈`�@saburapi ���A saburapi > savurai > shavure: > chevalier �Ƃ����ω��ɂ���Đ������B�i�O�̈גf���Ă������A�M�҂ɂ͂��̐������ł��邱�Ƃ͕����Ă���B�j ���ԋ����F�@�u�T�����C�v�́u�T�E���r�v�i���N��j�N�����ɂ��� ��̃t�����X�� chevalier �́@saburapi ���Ή�����Ƃ����g���f���ꌹ����^�Ɏ�l�͂��Ȃ����낤�B �ł́u���ނ炢�v�̌ꌹ�����N��i�u���m�v�ɂ͕S�ό�H�I�j�́u�T�E���r�v�issaurabi) �ł���Ƃ������͂ǂ����낤���H ���̌ꌹ�������Ɂu�T�E���r�v�Ȃ���؍���f��(�E���j�܂Ő��삳��Ă�ƕ����ƁA���ɂ́u�ց[�v�Ɗ��S���ĐM���Ă��܂��l���A������������A���邩������Ȃ��B�M�҂͎������ĂȂ����A�A�}�]���Ɍf�ڂ���Ă���Љ�ɂ��A�ȉ��̂悤�ȓ��e�ł���B �܂Ƃ��Ɏ��グ��قǂ̉��l��������ł͂Ȃ��̂����A���N��̗��j�̈�[�ɂ��ĐG���ɂ͎荠�ȑ�ނȂ̂ŁA���������E�����Ă݂邱�Ƃɂ���B ����؍���̎����������ƁA�m���� ssaurabi �F�@���m �Ƃ����ꂪ����B�m���ɁA���{��̃T�����C < �@samurapi �ƌ�`�����ĂȂ����Ƃ��Ȃ��̂����A���̌�̂����ׂ� ssau-da �i�����j�@�����B ssau-m �i�����j�@�����B�����B �Ƃ����ꂪ����A�T�E���r���u�����v�Ƃ��������̔h����炵�����ɋC���t���B�펯������{�l�Ȃ�A���̎��_�ŃT�E���r�ƃT�����C�����W�ł��鎖�͂�������̂����A����ł͋l�܂�Ȃ��B������������肵�Č���w�I���͂����݂悤�B ssaurabi �́A�����炭 s-sau -r- abi �ƕ��������B�ꓪ�� s �͈��̐ړ����ŁA�u����тт����������ۓI�ɕ\�킷���ߌꓪ�����Z����������v�i�P�U���I�ɖ��ĂɌ���邻���ł���j�̃q�g�c�Ǝv����B����́u�؍���̗��j�v(p. 144 Ref. KR-2)�ɂ́A�ȉ��̌�Ⴊ�Љ��Ă���B
�ȂǁB�i�ꕔ�������B�j��ɂ�����A������u�o�v�� s �v�Ǝ��Ă��Ėʔ����B�E�����łɉ������B �Ⴆ�A�c��ɂ́A*twer- �i�j�Ƃ����ꂪ����̂����A����ɂ悭����Ȃ� s-�@�����ɂ��� *stwer- �ƂȂ邱�Ƃ�����Bs- �̋@�\�́A���N��Ɏ��Ă��āu����тт����������ۓI�ɕ\�킷���߁v�Ǝv����t�V������B�O�҂� *twer ����� trouble�A��҂���� storm ���������B�u�Г�v�Ɓu���v������̌ꂩ�琶�����Ƃ����͖̂ʔ����B �b�������ɂ��ǂ��B �ꊲ�́@sau- �ɐڑ����� r �́A�������ڎ��ŁAssaur- �͓��{��Ō����ΘA�̌`�ł���B���N��ɂ͓����𖼎�������ڎ��� ��ɋ����� -m �issaum�F ����) �ƁA���� -r �ɉ����āA-n �̂R�g�̃Z�b�g������A���ꂼ�ꂪ�����ɊW���Ă���B����͌�`�E�Ӗ��Ƃ��c���O�[�X����Ɠ����ŁA���N��A���^�C�N�����̏d�v�ȍ����̃q�g�c�Ƃ���Ă���B�@-r �́A��������邢�͖�����\�킵�i����̓����X�e�b�g�̐��ŗ��������P���Ă���B �j�A�����ł́u�`���ׂ��v�Ɩ��B�i�P�Ɂu�`����v�ŗǂ����������悤�����B�j ���łɒE������ƁA����͑��R�������A���{��ɂ��c���O�[�X�N���̖������ڎ� r �̍��Ղ�����Ƃ���B�u�V���炭�̗��v�Ƃ����\���ɉ��ΓI�Ɏc���Ă��� raku �́A ra+ku �ƕ�������Ara �ɗp���𖼎�������@�\���������Ƃ���̂����A�ǂ����낤���B�M�҂̓`�g�ꂵ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���{��� ra �ɂ͔����邢�͖�����\�킷�@�\�͂Ȃ������ł���B�i�ނ��댻�݊����H�j ���āB �Ō��abi �i�Ԃ�ł� api )�͌����ł̓X�����O�I�ȗp�@�ł́u���e�v�ł���B���{�ꂾ�Ɓu�I���W�v�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B������ł́A���ʂɁu���v�̈Ӗ��ł���B�̂��̎���ɂ͑s�N�̒j�Ƃ����ꊴ�����̂�������Ȃ����A�M�҂ɂ͕���Ȃ��B�v����ɁA���^��͂��邪�A s-sau -r- abi �́A�u�i�������j�키�i�ׂ��j�j�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���̌Ì`�́A*sa�b�ur-api �ɑk��Ǝv����B �Ñ㒩�N��̌ꊲ�ɂ͘A���ꉹ�͂Ȃ������Ɛ��肳���̂ŁA -au- �̊Ԃɂ͎q���b�����������̂Ƃ���B�܂��A���ꉹ�ł��邪�A������ɂ͌����ȕꉹ���a�������āA����ꊲ���� a �� u �͋������Ȃ������n�Y�Ȃ̂ŁA*saCor- �������́A*saC��r- �����肳���B�����ł́A�T�����q�̌Ì`�T�����q < *samorapi �Ɣ�ׂ邽�߂ɁA*saCor-�@�Ƃ��Ă����B�i���̍b���͕s���B�j �������ꉹ�͏d�v�ȗv�f�ł͂Ȃ��B���{��� samorapi �Ɣ�r����ɂ́A���N��̌Ì`���Asamor-api �ɑk��A�����Ɏ���ߒ��� �� �������������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������A�Ñ�ꂩ�璆����Ő��������C�ω��i�ꉹ�Ԃ̗L�����C���̏����j�����Ă���Ɓi����u�؍���̗��j�v�Q�Ɓj�A�\��������č\�`�́A *sa��or-api�@ *sazor-api *sahor-api < *sa��or-api �̂R�ł����āA�Ñ���{��Ɏؗp���ꂽ�Ƃ��Ă��A�ǂ���T�����q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�v����Ɍꒆ�� m ���č\���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �������āA��`�̓_����u�T�E���r�v�Ɓu�T�����C�v�͖��W�Ƃ������ɂȂ�B �{�e�̃e�[�}�͗��j�E��r����w�Ȃ̂ŁA�����Ă܂�������͂��s�������A��ɏq�ׂ��悤�ɁA����������`�����邾���ł����̂悤�Ȕ�r���������Ȃ��͖̂��炩�ł���B �u�T�����C�v�̌ꌹ�Ɋւ���ʐ��͈ȉ��̒ʂ�ł���B�i��g�Ìꎫ�T�̋L�q��⑫�j �u�T�����C�v�́A�����u�T�����t�v�̖����`�i�A�p�`�j�u�T�����q�v���琶�����B�u�T�����t�v�����t�W�Ɍ�����ŌÂ̌�`�Łu�T�u���t�v�Ƃ����ٌ`���������͕̂�����ȍ~�ł���B �u�T�����t�v�́A�u���v�i�����j�ɁA�ړ����́u�T�v�ƁA�����E�p���̐ڔ����u�t�v���j���ڑ��������̂ƍl�����A(1) ����ꏊ�ɗ��܂��ėl�q���f���Ȃ���@���҂A(2) �l�Ɏd����A������ (3) ���l�ɉ�܂�҂A�Ȃǂ��Ӗ������B ���j�@�Ⴆ�u�Z�ށv�ɑ���u�Z�����v�͌p�����A�u�U��v�ɑ���u�U�����v�͎�ɔ�����\�킷�B ������������肩��A �u�l�Ɏd����v�̈Ӗ����L�͂ƂȂ�A�A�₪�ċM���̃{�f�B�K�[�h���u�T�����q�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂ł���B�u�T�����C�v�������Łu���v�Ə����̂͂��̂��߂ł���B�u���v�́A��������܂ł́u�ׂ͂�v�Ɠǂ܂�Ă������A�x���Ƃ����q����ɂ́u���ނ�Ӂv�A�u���ӂ�Ӂv�����́u���Ԃ�Ӂv�Ɠǂނ̂���ʓI�ɂȂ����B �u���v���T�����C�Ƃ��������\�L�́A�u�T�����C�v���A���Ă͋M�l�̑��Ɂu�ׂ͂�i�����悤�ɂ��Ďd����j�v�҂ł��������m�Ɏ����Ă���B���Ȃ݂ɐ̂��̎莆�̕����ɂ悭�g��ꂽ�u�`�ɂČ�v�i���ӂ낤�j�Ƃ����̂��u������Ӂv����h��������ł���B ���悤�ɁA�u�T�����C�v�̌�`�́A�u�����v�Ƃ����Ӗ��Ƃ͑S�����W�Ȃ̂ł���B���������A�����I�����ɂȂ��Đ��������m�Ƃ��Ắu�T�����C�v�Ƃ����ꂪ�S�ϋN���Ƃ����̂ł́A���オ�S�O�O�`�T�O�O�S�N�قǍ���Ȃ��B��`�E�Ӗ��E���j�w�i�A������̓_���炵�Ă�����Ȍꌹ���͐������Ȃ��͖̂����ŁA�M�҂��f�b�`���������z���E�̃t�����X�l�w�ҁA�\�V�[�����i�\�V���[���ł͂Ȃ��I�j��A���{��w�� Sinn. Ohne���i�ނ̓h�C�c�l�ł���j���^���ł���B �b�x�� �{�e�́A���z���E�ɂ�����p��̌n���_���Ƃ����`����āA���{��̋N����_������@�ɂ��čl�������Ă݂悤�Ƃ�������Ȃ̂����A���������E�����Ă��܂����B�{�_�ɖ߂邱�Ƃɂ���B �p��̌n����肪�A �P�D�@�t�����X�ꂩ��̕���� �Q�D�@�p��E�t�����X�ꓯ�����@�i���ʑc����j �R�D�@�u���e�����������@�i���m����N�����j �S�D�@���{��N���� ��e��̕ʐ��i�����S���N�����A�A���^�C�N�����Ȃǁj�̗����ɂ��A�����̓x������[�߂Ă������E�E�E�B �Ƃ������܂Řb�����i�̂������B �ȏオ�A���z���E�ɂ�����p��̋N��������u���b�v�ł��邪�A�Q�P���i���{��������R�P�������j�̌���ꂵ�������Ɏg���Ȃ��Ƃ������Ɍ������������ۂ����ꍇ�ł��A�����i�Q�̐��j�Ɏ����i�͂���̂��낤���H �\�Ɏ����ꂽ�f�[�^�������画�f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A��͂�A�u�`�Ƃ̕��v=���C�Ή����ɗ��邵���Ȃ��B��芸�����A�ꉹ�̑Ή��͕��G�����Ȃ̂ł�����߂āA�ꓪ�q���̑Ή����܂Ƃ߂�Ɖ��̂悤�ɂȂ�B
�����Œ��ڂ����̂́A�ΐF�Ɛ��F�Ŏ������O���̌n���̑Ή��ł���B�i�E�\�ɂ܂Ƃ߂��B�j �t�����X��� /p/v/f/ ���A�p��ł́A/f/ ��/w/�ɑΉ����Ă���B�Ƃ��낪�A�\�V�[�������������u�y�[�W�v�u���v�u���́v�Ȃǂ��Ή���ł́A���ׂ��A�t�����X���/p/ ���p��ł�/p/ �ɑΉ����Ă���B �u���C�Ή��͋K���I�ł����v�Ƃ�����r����w�̊�{�e�[�[���������Ƃ���A�t�����X��� /p/ ���A�p��� /p/ �ɂ� /f/ �ɂ��Ή����鎖�͂��肦�Ȃ��B�܂��A���F���@���@�p�F p�@�̑Ή����������̂́A�ꓪ�q���ǂ��납�ꉹ���܂߂��S�̂̌�`���\�b�N�������ŁA��Ɏ�������b��b�ɂ�����Ή��Ƃ͖��炩�����I�ȈႢ������B ��b��b�̔�r�œ���ꂽ���C�Ή��̕������u�����I�v�ł���ƍl������̂ŁA�\�V�[�������������Ή������ׂ��ؗp��ł���ƃo�b�T���Ɛ�̂Ă鎖���ł���B�������āu�^�̓�����v�f���邽�߂̏d�v�Ȏ�|���肪����ꂽ�B��͂艹�C�Ή����̌��͂͐��ł���B �Ⴆ�A�t�����X��́@plat (���R�ȁj�ƁA�p��́@flat �i����ȁj�́A�Ӗ�����`���ǂ����Ă��邪�A�p�F p �̕��Fp �̑Ή��ł͂Ȃ��A��b��b�̑Ή����瓾��ꂽ�A���F p���p�Ff �̑Ή��ƈ�v����̂ŁA���Ȃ��Ƃ��V�����N��̎ؗp��ł��Ȃ��Ɣ��肷�邱�Ƃ��ł���B ���́A���F p���p�Ff �Ƃ����Ή��ɁA���́u�O�����̖@���v�̕З��`�����Ƃ��̎p�������Ă���̂����A�����O�����̖@�����Ȃ������Ƃ������A�p��ɂ�����ؗp���^�̓�����ƕ����E���ʂ��邱�Ƃ͋ɂ߂č���ɂȂ�B�p��� flat ���Aplat �������Ƃ�����A���������ǂ�����Ďؗp��Ƌ�ʂł��邾�낤���H��͂�u�O�����̖@���v�͈̑�Ȃ̂ł���B�����҂̃O�������������Ȃ鑸�h�ƌ��Ђ����������͔̂[���������Ƃł���B �u���C�Ή��͋K���I�ł����v��M�p����A�p��̋N���Ɋւ��čX�Ɉȉ��̌��_�����Ƃ��ł���B �P�D�t�����X�ꂪ�p�ꂩ�番���Ƃ������́i�قځj�ے肳���B �p��� /f/ �ƃt�����X�� �� /v/f/p/ �̂R��ނ̎q�����Ή����Ă��邪�A����̓t�����X��̎q�����p��ł̓q�g�c�ɍ��������\���������������j�B�������A���̋t�̃v���Z�X�͐���������B����ĉp�ꂩ��t�����X�ꂪ�����Ƃ������͐������������B ���j�@���́A���̘_�@���̂��̂͐��������A�p��� /f/ �ƃt�����X�� �� /v/f/���Ή�����Ƃ����̂́A��̌�Ⴉ��͌����Ȃ��̂Łi�U�҂Ȃ̂Łj�A ���_�͍����Ă��邪�ԈႢ�ł���B�p�F�@f ���@���F�@p �ƁA���F�@p ���@�p�F�@f �̂ǂ���̉��C�ω��������Ƃ��炵�������ׂ�ƁA�O�҂̉��C�ω��͐����ɂ����̂ŁA�p�ꂩ��t�����X�ꂪ�����Ƃ͍l���ɂ����Ɛ��_����̂��Ó��ł���B �Q�D�U�҂̓���������ʂł���B �t�����X��� /f/ �ɑ��A�p��� /f/�� /w/ ���Ή����Ă��邱�ƂɂȂ邪�A����͉��C�Ή������炷��Ƃ�͂�L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�O�҂́Afeu : fire �A��҂́A femme : woman �̑Ή����瓾��ꂽ���̂����A�ǂ��炩����A���邢�͗�����������ł͂Ȃ��Ɛ��肳���B���͋��ɓ�����ł͂Ȃ��U�ҁi���l�̋j�Ȃ̂����A���ꂾ���̃f�[�^���猋�_�������͓̂���B �܂��AOhne���ł��邪�A���{��Ɖp��ł́A�K���I�� p > f �ƑΉ����Ă���̂Ŗ��Ȃ����A�t�����X��ɂ��ẮA���{��� /p/ �ɑ��� /v/f/p/ ���Ή����Ă���B���̕s�K�����������ł��Ȃ���A���Ȃ��Ƃ����̑Ή��̂����̂ǂꂩ�A�����͑S�Ă��U�҂̓�����Ƃ������ƂɂȂ�B �������āu�T�����C�v���u�V�����@���G�v�ɂȂ����Ƃ����I�[�l���̈�p�͕��ꋎ��B�����炭Ohne���́A�u�w���C�@���ɗ�O�Ȃ��x�ȂǂƂ����̂́A�E�������邢�̓I�[�X�g���l�V�A��r����w�ȂǁA�A�W�A�̌���ł̂ݎ����ꂽ���̂ł����āA���[���b�p�̌���ɓK�p�ł���ۏ͂Ȃ��v�Ǝ咣����ł��낤�B ���̂悤�Ɂu���C�Ή��͋K���I�ł���v�Ƃ����@���́A�K�Ɏg���u�^�̓������v��⿂�������̂ɋɂ߂Đ��Ȍ��͂�����B�����ɐݒ肵�����z���E�ɂ����錾��w�҂̉ˋ�̘_������A�������̏d�v�ȁu���P�v�邱�Ƃ��ł���B�i�Ƃ������A�ȉ��ɏq�ׂ邱�Ƃ͔�r����w�́u�펯�v�Ȃ̂����A�]���̓��{��n���_�ł͂��̏펯�������Ζ�������Ă����B�j ���ݎؗp�̉\�������錾��ǂ����́u��荪���I�ȊW�v��_����ۂɂ�
���e�Ō�������\��ł��邪�A���{��ƒ��N����r�����ꍇ�A�ؗp��ƌÂ��N����L���铯������E���ʂ���̂́A���������i�Ƃ��������ۂɂ���Ă݂�Ǝv���m�炳��鎖�ɂȂ邪�j�A���`�ɓ���B�Ⴆ�A
�Ȃǂ́A�T�^�I�ȁu������b�v�ł���A���N��Ōꖖ�ꉹ���Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�������Ό�`�E�Ӗ����قƂ�Ǔ����ł���B�M�҂͂����͎ؗp��Ɣ��f���u���[���v�W��_����ۂ̍����ɂ͎g���Ȃ��ƍl����B�i���`�������ׂĂ��ؗp��ł���Ƃ͒f��ł��Ȃ��B������̂́u�^�́v������ł���\��������B�j��̗�Œ��ڂ����̂́A���{�� /u/�ƒ��N��/o/ �̑Ή��ł���B����Ɠ����ꉹ�̑Ή��������A
���A�ؗp��ł���\�����������ɂȂ邪�A�u������b�v�Ƃ͌�����u�F�v�Ɓu���i�ԁj�v���ؗp��ƒf���ł��邩�ƂȂ�Ɠ���B�u���Â�����v�ɂ����Ă͓��{���/u/ �ƒ��N��� /o/ ���ʂ̑Ή������������������A���̂Q����ؗp��Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B���Ȃ݂ɁA�M�Ҏ��g�́A��ɏq�ׂ�悤�ɁA�ꉹ���L���C�ɑΉ�����̂́A��r�I�V��������̎ؗp�ɂ����̂��ƍl����B ������ɂ��Ă��A�p������̔�r�Ⴊ�����悤�ɁA���C�Ή������w�������Ƃ��Ďؗp��Ɠ���������邱�Ƃ��A���N��Ɠ��{��́u���m�ȊW�v��c�����邽�߂̑����ł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�ގ�����ނ�݂ɗ��Ă������Đ����ɂ͒H�蒅���Ȃ��B �Ƃ��������_�́A����܂œ���������̔�r�Ɏ��g����w�҂͊F�����Ă���i���j�̂����A�O�����̖@���ɑ�������悤�ȓs���̗ǂ����C�Ή������ł��Ȃ��̂œD���Ɋׂ�̂ł���B�߂������ɕM�Ҏ��g�̎��݂��Љ�悤�Ǝv���B �b�����摖���Ă��܂����B ��r����w�̌��E�ɂ��� ��́A�u���C�Ή����͗���ɂȂ��v�Ƃ����b���ł������B����́i�ꓪ�j�q���Ɋւ��Č��������ł���B�ł͕ꉹ�͂ǂ����낤���H�p���̑Ή��ꃊ�X�g���Čf���ĕꉹ�̑Ή��������B�i�����L���Ŏ����Ă��͂��܂���P����Ȃ��̂Ŋ����ĒԂ�̂܂܂ɂ��Ă����B�j
���F�Ŏ������U�҂����ꍞ��ł���̂ŁA�]�v�ɂ�₱�����Ȃ��Ă��邪�A���F p���p�Ff �̑Ή����������������Ɣ��f���āA�����̋U�҂�r���ł����Ƃ��Ă��A�h�C�c����Q�Ƃł����A�����p��ł�������ꉹ���ڂƌĂ�钷�ꉹ�̑�ω��i�ٍe�Q���j�̒m�����Ȃ��A�Ãt�����X��ŋN������d�ꉹ���̃f�[�^���Ȃ��ɁA��̕ꉹ�Ή��������特�C�@�������o�����Ƃ͂����Ȃ�V�˂̓��@�͂������Ă��Ă��i�����炭�j�s�\���Ǝv����B �p��ƃt�����X�ꂪ���Ă��牽�N�o�߂��Ă��邩�ɂ��Ă͌�Ō������邪�A�M�҂͎����I�ɖ�R��N�ƍl����B �u��r����w�̎˒��͂T�`�U��N�v�ƌ������A��r�ł��錾�ꂪ�Q�����Ȃ��A�Ì�̃f�[�^��������Ƃ����������̉��ł́A�T�`�U��N�͓��ꃀ���ŕ���N�オ�R��N������A���Ȃ��Ƃ��ꉹ�ɂ��Ă͌����ȉ��C�Ή��������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�ł������j�B ���j�@���ꂪ�A��ɏq�ׂ��悤�ɁA���{���/u/ �ƒ��N��� /o/ �v���L���C�ɑΉ�������̂́A�����W����������؋��Ƃ��ẮA�������ƕM�҂��^�����R�ł���B �u�L���˒��T�`�U��N�v�́A�ꑰ�̂悤�ɌÂ�����̎������L�x�Ɏc�����Ă���A�����̓E�����ꑰ�ɂ�����t�B�������h��̂悤�ɁA�u��b�̗Ⓚ�ۑ����v�Əd����`�ω��̔��ɏ���������̑��݂Ƃ������K�^�ɏ�����ꂽ�ꍇ�ɂ��Č����鎖�ł͂Ȃ����낤���B �����A�E��������̂����t�B�������h�ꂪ���ł��ă��b�v��ƃn���K���[��݂̂������c�����Ƃ���A�q���͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ��Ă��A�p���̏ꍇ�Ɠ��������ʑc��ɂ�����ꉹ�V�X�e���̍č\�͌���Ȃ��s�\�ɋ߂��Ǝv����i���\�Q�Ɓj�B
�]���āA�u��r����Q����ԂɌ����ȉ��C�Ή����ݒ�ł��Ȃ�����ɂ́A���҂Ɍn���W���������Ƃ��Ă����̕���N��͂T�`�U��N�ȏ�v�ƋC�y�ɂ͒f���ł��Ȃ��B ���N��̂悤�ɁA15���I�ȍ~���炵���ڍׂȃf�[�^���Ȃ��A���ӂɓ�������ƌn���W�����肻���Ȍ��ꂪ�Ȃ������������̉��ł́A�i���Ȃ��Ƃ��ꉹ�Ɋւ���j���C�Ή����̐��x�͒��������A�����u�L���˒��v�͂R��N�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v����B ����āA�ꕔ�̘_�҂̌����u��r����w�̎�@�́A���{��̌n������_����ۂɂ͖��ɗ����Ȃ��v�Ƃ�������ΊJ������̂悤�Ȍ����́A����Ӗ��ł͐������ƕM�҂͎v�����A�������A�q���̗�͉��C�@���̈З͂����ł��邱�Ƃ�������B ���C�Ή����Ȃ��ɗ��j�E��r����w�͐��������Ȃ��B �u����N��w�v�̗L�p���ɂ��� �Ăщ��z���E�̘b���ɖ߂�B �p��̋N���ɂ��Ă̂S�̉����A �P�D�@�t�����X�ꂩ��̕���� �Q�D�@�p��E�t�����X�ꓯ�����@�i���ʑc����j �R�D�@�u���e�����������@�i���m�̌���N�����j �S�D�@ �̂����A�S�͔ے肳�ꂽ�B�܂��t�����X��̉p��N�������������������ł��邱�Ƃ��A���C�����猋�_���ꂽ�B �������A�ؗp��������Ƃ����I���W�i���̃\�V�[�����͔ے肳�ꂽ���A�p��͂����ƌÂ�����Ƀt�����X�ꂩ�番���Ƃ����u�C���\�V�[�����v�����ꂽ�Ƃ���A�����ے肷�邱�Ƃ͉\���낤���H �����I�ɂ͕s�\�ł���B�p��̃t�����X�ꂩ��̕�����Â�����ɐݒ肷��Ƃ����̂ł���A�P�ƂQ�͎����I�ɂ͓������ł���B�����A�P�ƂQ�̈Ⴂ�́A����N��̈Ⴂ�Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł���B�Ⴆ�A�u�C���\�V�[�����v�̘_�҂��A�p�ꂪ�t�����X�ꂩ�番���̂͂P�P���I�̃m���}���l�̐����̎��ł������Ǝ咣�����Ƃ���B����A�u�p��E�t�����X�ꓯ�����v�̘_�҂́A����N���������i�Ⴆ�j�S�`�T��N�O�Ǝ咣�����Ƃ���B����Ȃ�A�ǂ��炪����������_���邱�Ƃ͂ł���̂ł͂Ȃ����낤���H ����w�I�f�[�^�������画�f���悤�Ƃ���Ȃ�A��͂�ǂ����Ă�����̕ω����x�ɂ��čl�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���̖����n�߂Ė{�i�I�ɘ_�����̂��A�č��l����w�҂̃X���f�B�b�V���ł���B�ނ̊w���́u����N��w�v�iGlottochronogy)�ƌĂ��B�M�҂́A���̂悤�ȒP���Ȑ��������ʂɑ��Đ�������n�Y�͂Ȃ��낤�Ɗ��S�ɕs�R�̖ڂŌ��Ă������A���ہA�����̌���w�҂��u����N��w�v�̎咣�ɂ͉��^�I�Ȍ���������Ă���Ǝv����B�������A�l�Êw��l�ފw�̃f�[�^�Ɣ�r����w��̒m����˂����킹�邽�߂ɂ́A���̐��ɗ���Ȃ��Ɓu�N��v�Ƃ������ʂ̃��m�T�V�������ł��Ȃ��̂ł���B ������_���ƌ��߂��Ȃ��ŁA�����Ă݂邱�Ƃɂ���B �{�e�ł́u����N��w�v���A���ȏ��ɍڂ��Ă���̂Ƃ̓`���b�g������g����������̂ŁA���̊�b�ƂȂ��Ă��郊�N�c�ɂ��āA���������ς킵����������Ȃ����������Ă����B�����̂Ȃ����́A���_���ɔ��ł�����Ē��������B �u����N��w�v�̃��N�c�@ �u����N��w�v�������̂́u�P��̒u���v�ł���B���������Ƃ����Ȃ��̂ŔO�̈גf���Ă������A��`�ω��ɂ��ďq�ׂ����̂ł͂Ȃ��B�@�Ⴆ�A�u�ԁv�́Apana ���@��ana ���@hana �ƕω�����������͓����P��̉��C�ω��ł���B����A�Ⴆ�Atumuri ���@kasira ���@atama �̂悤�ɁA�P�ꂪ�u��������Ă��܂��̂��u�P��̒u���v�ŁA�u����N��w�v�́A��b�̒u�����x�ɂ��ďq�ׂ����̂ł���B ��b�́u�u���v�́A�I���W�i���̒P��Q�́u�����v�Ƃ����߂ł���B �P��̏������ۂ��L�q����ȒP�Ȑ��w���f�����l����B�g�߂ȂƂ���ŗގ��������ۂ����߂�ƁA��w�̍u�`�ɏo�Ȃ���w�����̎��ԕω��A��ЂɏA�E�����V�l�Ј��̔N�����Ƃ̎c�����Ƃ������Ƃ��낪����Ղ��Ǝv����B ��w�̍u�`�ŁA�ŏ��̂����̏o�Ȑl�����������ɂ͐l�����Ȃ��Ȃ鑬���͑傫�����A������x���Ȃ��Ȃ��Ă���ƌ�������x���Ȃ��Ă���Ƃ����̂́A�悭�o�����邱�Ƃł͂Ȃ��낤���B���̂悤�Ȍ��ۂ�������邽�߂ɁA�o�Ȃ��Ă���w���̂����̂�����̊����̐l���̎҂��u�`���甲���Ă����Ɖ��肵�Ă݂悤�B �Ⴆ�A�ŏ��T�O�������w�����P�P���łT�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���B�P�P������̌������͂P�O���ł���B�l���������Ă����āA�Ⴆ�P�O���ɂȂ������ł��A���������i�P�O���j�ł��Ȃ��Ȃ�Ɖ��肷��A���̎��_�ł͂P�����P�P���Ŕ����邱�ƂɂȂ�B�T���ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�ɂ͂P�O����0.5���ƂȂ邪�A����͗L�蓾�Ȃ��̂ŁA�Q�P���łP���������邱�ƂɂȂ�B ���ۂƍ����Ă��邩�͕ʂƂ��āA��b�̏����i�u���j������Ɠ��������ɏ]�����̂Ƒz�肷��̂����A����𐔎��ŕ\�킷�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B ���� t ���o�߂������Ɏc�������P��̐��� R(t)�Ƃ��A�������燙t�o�߂������ԁ@t+��t �ɁA�P�ꂪ�ǂꂾ���u������邩�́A�o�ߎ��ԁ@��t �ƁA���� t �ɂ����Ăǂꂾ���P�ꂪ�c�����Ă��邩�ɔ�Ⴗ��Ɖ��肷��B���Ȃ킿�A��t �̊Ԃɒu�������P��̐��́A�@ R(t+��t)- R(t) = -��R(t)��t �ƂȂ�B���͔��萔�ł���B����́AdR/dt=-��R �Ƃ��������������ɂȂ�A���̉��́AR(t)=R0exp(-��t)�@�ƂȂ�B ������Ro�́A�����O �̎��̒P��̐��ł���̂ŁAr(t)=R(t)/Ro = exp(-��t) �́A��b�c�����ƂȂ�B �����܂ł́A�܂��A�P�������邩�ȁ[�Ƃ����C�͂��邪�A���ߎ����f���Ƃ��Ă͈����Ȃ��Ǝv���B���́A����̒u���������߂郿�����ׂĂ̌���ň��Ƃ��邱�Ƃł���B�������肵�Ȃ��Ɩ��m���������Ȃ��Ė��ɗ����Ȃ��̂Ŏd���Ȃ��̂ł���B �Ƃɂ����������肷��ƁA����`�Ƃa���c�ꂩ�番�Ă��N�o�߂������ɂ́A����`���a���c�����́Aexp(-��t)�ƂȂ邪�A���҂ł̒P��̒u���������_���ȓƗ����ۂƂ݂Ȃ���ꍇ�ɂ́A����`�Ƃa�̒P�ꂪ��v����m���i�����j �qAB�́A���̊|���Z�A RAB = exp(-2��t) �ƂȂ�B �]���āA����`�Ƃa���r���ĒP��̈�v���� r �ł���ꍇ�ɂ́At=-ln(r)/2/�������̎��Ԃ�����o�߂����ƎZ�o���鎖���ł���B �X���f�B�b�V���͐F�X�Ȍ���̌�b�u�������͂����o���A���������P�O�O�O�N�łW�P���̌�b���c������Ǝ咣�����B����ƌ���̎c�����@r(t) �� r(t) = exp(-t/4750) �@�@t: �N�\�� �ƂȂ�B�����E�H�w�n�̐l�ɂ͂Ȃ��݂̐����Ǝv��������u���̎��萔��4750�N�B��T�O�O�O�N���o�߂���Ƒc��Ƃ̑��ւ͂قڎ����Ă��܂����ɂȂ郏�P�ł���B ����N��w�����ۂ����܂�ɒP�������Ă��邱�Ƃ͒N�̖ڂɂ������ŁA��̚g���Ō����A�ǂ̑�w�A�ǂ̍u�`�ł��A�w�����u�`����ʂ��Ă��������͋G�߂ɂ���炸���s�ςƉ��肷�郏�P�ł���B ���̉���G�ɂ��Ă����Ɛ����ȋc�_�����悤�Ƃ������݂����邪���j�A�M�҂��v���ɂ́A�ǂ����u���炸�ƌ����ǂ������炸�v�Ȃ̂�����A���_�G�ɂ��Ă����܂���ɂ��Ƃ͎v���Ȃ��B ���j�@�Ⴆ�A" Time Depth in Hisitorical Linguisitics" �i2000) ed.�@C. Renfrew, A. McMahon and L. Trask ���̘_���W�ɂ͌���N��w�ւ̔ᔻ�A�����̕�āA�N���I�[����ɂ����镶�@�\���̕ω����x�Ɋւ���_���Ȃǂ��f�ڂ���Ă��ĂȂ��Ȃ��ʔ����B �u����N��w�v�̎g�p���@�̊g���ɂ��� ��ɃE�_�E�_�Ɛ�������ׂ��̂́A����N��w�̎g�p�@���g������������ł���B����w�̋��ȏ��ɍڂ��Ă���̂́A��̌�����r�������̈�v�� r �� r= exp(-2��t) �Ə�����̂ŁA��v�� r ���番��N�� t �� t =-ln(r)/2/�� �ƌv�Z�ł���Ƃ������ʂ̂ݎ�����邱�Ƃ������B���������̎��̂܂܂��ƁA�c�ꂩ�番�������N�����o�߂�������Ԃ̔�r�ɂ����g�����Ƃ��ł��Ȃ��B �M�҂Ƃ��ẮA��̋c�_�ŁA����p��ƃ��e�����q�b�^�C�g��A�����́A�W���I���{��ƒ������N��Ƃ̌�b��v������ɂ������̂ŁA����N��w�̎g�p�@���g���������̂ł���B �c�ꂩ�番�� t1�o�߂�������`�� t2 �o�߂�������a���r�����ꍇ�̌�b��v���@�qAB�́A RAB = rA*rB= exp(-��t1)*exp(-��t2) = exp(-��(t1+t2)) �ƂȂ�B���̒l���痼����́u��������N��v teff �Ƌ��߂��Ƃ���ƁA RAB = exp(-��(t1+t2)) = exp(-2��teff) �Ȃ̂ŁAteff= (t1+t2)/2 �ƂȂ�B ���ʂ͒P���ŁA�c�ꂩ�番��1��N���ꂽ���ꓯ�m���ׂ��ꍇ�ɂ́A���҂�(�����j����N��́A(1000 + 1000) / 2 = 1000�N�ƂȂ�B����͓�����O�B �c�ꂩ���N���ꂽ����ƂR��N���ꂽ����̏ꍇ�ɂ́Ateff=(1000+3000)/2���Q�O�O�O�N�ƂȂ�A���҂́u���������v����Q�O�O�O�N�������̂Ɠ�����v���������Ƃ����̂���̌��ʂ̈Ӗ��ł���B �p��̓Q���}����h�ɑ�����B�Q���}���ꂪ�c�ꂩ�番���͍̂�����Q�T�O�O�N�O�Ƃ����B�t�����X��̓��e���ꂩ�番�A�X�Ƀ��e����̓C�^���b�N��h�ɑ������A�C�^���b�N��h���c�ꂩ�番���̂́i�c�_�̗]�n�����鏊�����j�A�a�b�Q�O�O�O�N���ƍl���Ă����B �p��̈c�ꂩ��̕���N�� t1 ��2500�N�A���e����̂���͈c��̒a�����a�b4000�N�Ƃ���At2 = 2000�N�ƂȂ�̂ŁA���҂̌�b���r����A������́A���������A���Ă��� (t1+t2)/2 = 2250�N���ꂽ����ǂ����Ɠ�����v���������n�Y�ł���B ���̂悤�ɑc�ꂩ��̕���N�オ�������Ă���e�팾��Ԃ̌�b��v���ׂ邱�Ƃɂ���āA����N��w�̗L�������`�F�b�N���悤�Ƃ����̂��M�҂̈Ӑ}�ł���B �u���e����̔����v�͉p��n���_�ɉ��������炷���H ����͍ĂёO�̉��z���E�ł���B ���E�̌���w�҂������������I�̑唭��������B �C�^���A�̌Ñ��Ղ��琼��N�ɏ����ꂽ�Ɛ��肳��郉�e����̕������������ꂽ�Ƃ��Ă݂悤�B �Q�O�O�O�N�O�̃��e����̎����́A�p��ƃt�����X��̋N���Ɋւ��ǂ̂悤�Ȏ�|�����^���Ă���邾�낤���H�ȉ��ɔ�r�\��������B
�܂����������̂́i������ƃV���W���������j�A���e����ƃt�����X��Ƃ̌����ȗގ����ł���B���f�ɖ������̂����邪�A��b�̈�v���͂V�R���ɂ��B����B�i�����ԈႢ�����邩������Ȃ����A�吨�ɉe���͂Ȃ��낤�B�j �܂��A�t�����X��ƃ��e����̊W���ǂ��l���邩�ł���B ���ɗ�����̋��ʑc�ꂪ���݂����Ƃ��āA���e����̑c�ꂩ��̕���N��� t1�A�t�����X��̂���� t2 �Ƃ���B��b��v���V�R������v�Z����ƁAt1+t2=�P�T�O�O�N�ƂȂ�B �Ƃ��낪�A�������ꂽ���e����͂Q�O�O�O�N�O�ɂ͑��݂��Ă������P�ł���Bt1, t2 �̓}�C�i�X�ł͗L�蓾�Ȃ��̂ŁAt1=0, t2 = 1500�N�Ƃ��邵�����͂Ȃ��Bt1=0 �Ƃ����̂́A���e���ꎩ�g���t�����X��̑c��ł���Ƃ��������Ӗ������B �܂�A�t�����X��́A����T�O�O�N���Ƀ��e�����c��Ƃ��Ēa�������Ƃ������_������N��w���瓱������B�������������v�Z����o�ė���ƂȂ�ƁA����N��w���Ȃ��Ȃ��̂Ă����̂ł͂Ȃ��낤�Ƃ������ɂȂ�B�M�҂̓��}���X��̗��j�ɂ��đS�R�m�����Ȃ��̂����A�V�[�U�[�̃K���A�������a�b�T�O�N�Ȃ̂ŁA�������琔�S�N�o�������_���A�t�����X��c��a���Ƃ����͔̂[�����������Ǝv����B�i200�`300�N���炢�̌덷�͂���ȃV���v���ȉ���Ɋ�Â��c�_�Ȃ̂Ŗڂ��Ԃ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�j ����Ńt�����X��̌n�����͉������Ă��܂����B �ł́A�p��ƃ��e����̊W�͂ǂ��Ȃ�̂��H ��b�̈�v���́A�M�҂̎Z��ł͂S�O���ŁA�t�����X��Ƃ̂���i�R�O���j���啝�ɃA�b�v�ł���B���������҂̊W�́u�������v�̓t�����X��Ƃ̏ꍇ���������ƃN���A�[�ɂȂ��Ă���B�p��ƃ��e������ׂ�ƁA fish ���@piscis�@�ł��邪�A���F�@poisson �ɔ�ׂ�Ό�`�����Ă���B heart ���@cordis �i���F coeur) star ���@stella �@�i���F�@etoile) ear ���@auris �i���F�@oreille) �ł���B�ꉹ�̑Ή��ɂ��Ă��A����Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��K�������ł������ȋC�����Ă���B #18 eat/ed-�A #25 sit/sed-�A#26 stand/ sto �Ȃǂ́A�c��@*ed / *sed/ *sta: / �̌�`�������Č����ė��Ă���B �Â�����ɑk��Ɨގ���������w�A����ɂȂ�Ƃ����̂́A�������Ή��̏؋��ł���B����A�t�����X��Ƃ̔�r�ŁA���C�Ή��������Ɂu�������v�Ɣ��f���ꂽ�A�p�F�@woman ���@���F�@femme ��A�p�F fly ���@���F�@voler �ɂ��ẮA���e����̌�`�����Ă�����ɗގ��������P����Ă��Ȃ��B����͑Ή����U�҂̏؋��ł���B ����Ɂu�������v�̂́A
�̂悤�ɁA�p�F f ���@���F�@p �����łȂ��A�p�F h ���@���F k �A�p�F�@k ���@���F�@g �̑Ή��������悤�ɁA�p��̖��C���ɑ��ă��e����̔j���A(h < k, f < p) �A�p��̖������ɑ��ă��e����̗L������ (k < g) �Ή����Ă���Ƃ����u�O�����̖@���v�̑S�e���A�܂��s���S�Ȃ�����A��薾�m�Ȏp�Ō���Ă��Ă��邱�Ƃł���B ���̍L�͂ȋK������������A�p��ƃ��e����̔�r�̐��x���i�i�ɉ��P���邱�Ƃ��ł���B�t�����X�l�ɒ��炭�����I�����i�����炭�j�����Ă����h�C�c�l���A��r����w�ɂ������ɖG�����̂������ł��悤�Ƃ������̂ł���B�Ȃɂ���A�����B�̌��ꂪ�Q���}����h�Ƃ������e����ƃ^�������������h���`�����鎖�����������P�ł���B ����A�p���l������قnjÑ㌾��̉�ǂɍv�������ɂ��ւ�炸�A���قǔ�r����w�̔��W�Ɋ�^���Ȃ������悤�Ɏv����͕̂s�v�c�ł���B��͂��p�鍑�̗]�T���낤���H �Ƃ������͂��Ă����A�b�����ɐi�߂邱�Ƃɂ��悤�B �ł́A�p����܂��t�����X��Ɠ������A���e���ꂩ�琶�܂ꂽ�̂��낤���H �����ōĂсu����N��w�v�̓o��ł���B �p�ꂪ�t�����X��Ɠ��������e�����c��Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂Ɖ��� (t1=0) ����B��b��v�����S�O�����ƕ���N�� �͂S�S�O�O�N�ƂȂ�B�����p��̒a���͂a�b�Q�S�O�O�N���ƂȂ�B�������������ꂽ���e����̕����͐���N�B������X�ɂQ��N�ȏ���O�ł���B����́A�p�ꂪ���e���ꂩ�璼�ڕ����̂ł͂Ȃ��A�p��E���e���ꋤ�ʑc�ꂩ�痼���ꂪ���Đ�����������������B ���e����Ɖp�ꂪ���ʂ̑c�ꂩ�琶�����Ƃ���ƌv�Z�̕��@������Ă���i���}�j�B�I�����N�����_�Ƃ��đc��w����̃��e����̕���N��� ���A�p��̂���� �� �Ƃ���ƁA���{���{�Q�O�O�O�N���S�S�O�O�N�ƂȂ�B 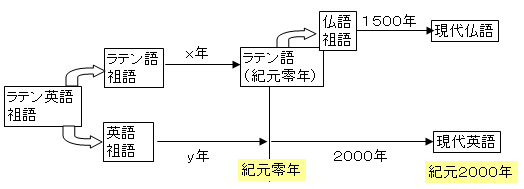 ��b��v������́A����N��̍��v�l�����o�Ă��Ȃ��̂ŁA�e���ꂪ�a�������N������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���ɂ������Ƃ���A�����P�Q�O�O�N�B�a�b�P�Q�O�O�N���ɉp��ƃ��e����͋��ʑc�ꂩ�番�����ƂɂȂ�B ���e����̈c�ꂩ��̕���N��́A�i�����炭�j2000�N�A�p��͂Q�T�O�O�N�Ȃ̂ŁA�u��������N��v�́A��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�Q�Q�T�O�N�Ɨ\�z����邪�A����́A��b��v������́u��������̕���N��v��4400�N���Q���Q�Q�O�O�N�Ƃ������������B���\�ȒP�����ɂ��ւ�炸�A�Ȃ��Ȃ��ǂ���v�ł���B ���z���E�ɂ�����p��n���_�̌��� ��̉��z���E�̐ݒ�ł́A�u�^�ǂ��v���e���ꂪ�������ꂽ���߂ɐ����ɂقƂ�Nj߂����� �P�D�@�t�����X��̓��e�����c��Ƃ��Ēa�������B �Q�D�@�p��̓��e����ƋN���������関�m�̑c�ꂩ�番�Ăa�b�P�T�O�O�N���ɒa�������B �ɒH�蒅�����Ƃ��ł��ă��f�^�V���f�^�V�ƂȂ����B�������A�M�҂̍ŏ��̖��ݒ�́A�u�������ɁA����p��ƃt�����X�ꂵ���f�[�^���Ȃ��ꍇ�ł��A�p��̌n�����Ɋւ��Đ����ɒH�蒅�����Ƃ��ł��邩�ǂ����v�ł������B ���e������������肾�����̂́A�u����N��w�v�̗L�����������邽�߂̑[�u���������P�����A�ŏ�����u����N��w�v��M�p���ĉp��ƃt�����X��ɓK�p�����Ƃ���ƁA���҂̕���N��́A��b��v���R�O������A�Q�W�U�O�N�ƂȂ�B�����A���҂̕���͂a�b�X�O�O�N���ƂȂ�B�c�O�Ȃ���A���e���ꂩ��̕����O��Ƃ����p��a���̔N��A�a�b�P�T�O�O�N�Ƃ͍���Ȃ����A��ɏq�ׂ��悤�ɁA��b�̈�v�����瓱�����N��l�́A��r���錾�ꂪ�c�ꂩ�番���N��̍��v�l�ł����Ȃ��̂ŁA����̐�ΔN��̎Z��͓���̂ł���B ���������Ȃ��Ƃ��m��I�Ɍ�����̂́A11���I�̃m���}���l�̐������ɉp�ꂪ�t�����X����a�������Ƃ������͔ے�ł���Ƃ������ł���B�����A11���I�̃t�����X�ꂩ��p�ꂪ�����Ƃ���A���҂̌�b�̈�v���͂U�W���łȂ���Ȃ�Ȃ��B �������Đ����c�����̂́A �P�D�@ �Q�D�@�p��E�t�����X�ꓯ�����@�i���ʑc����j �R�D�@�u���e�����������@�i���m�̌���N�����j �S�D�@ �̂����A�Q�ƂR�ł���B �R�͈��̍����N�����Ƃ��݂Ȃ����Ƃ��ł���B�Ⴆ�t�����X��Ɠ����ł���\���̂���R�O���̌�b�����ׂČÂ�����̎ؗp��Ƃ݂Ȃ��āA�c��V�O���͕ʌn���̌���ɗR��������̂ƍl���邱�Ƃ͏\���\�ł���B���������p��̓t�����X��Ƃ͕ʌn���̃Q���}����h�ɏ������Ă��郏�P�ł��邵�A�Q���}���c��̊�b��b�̂�����R�O�������N���ƌ����Ă���̂ŁA����͂���őS���I�O��̌����Ƃ������P�ł͂Ȃ��B ��������̉\���������o���ƁA����N��w�͑S�����͂������Ă��܂��B���{�ꍬ���N�������l����M�҂Ƃ��Ă͍��������Ƃł���B ���ǁA����N��w�͌��������ے肷��̂ɂ͎g���邪�����W�̗��ɂ͎g���Ȃ��B���ǁA���ݎؗp�̉\���������̌���̔�r�����ł́A �P�D�@�p��̓t�����X��Ɠ��� �Q�D�@�p��͌Â�����Ƀt�����X��c�����j����̎ؗp�ꂪ���������ʌn���̌���ł��� �̂ǂ��炪���������m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i���F�@���̐ݒ�ł̓��e����͔�������ĂȂ��Ƃ���̂ŁA�u�t�����X��c��v�ƕ\�����邵���Ȃ��B�j ��b��r�ɂ���ĉp��ƃt�����X�ꂪ�����ł��邱�Ƃ𗧏���ɂ́A��͂�T���X�N���b�g��Ƃ��q�b�^�C�g��Ƃ��A�ł��邾�����҂Ƃ͒n����N������ꂽ�u��O�̌����v�ɓo�ꂵ�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�q�b�^�C�g��Ɖp��ł́A���Ɏ����悤�ɁA1�Q�ꂪ�����Ƃ݂Ȃ����B�i�u���z�v�������ꂩ�͎��M���Ȃ��B�j�q�b�^�C�g��̓A�b�J�h���V�����[���ꂩ��̎ؗp�����ɑ����̂����A��b��b�ɍi��A���������������i12/40=30%)�œ����ꂪ������B
�b����Ă����̈��������قȂ邱���R�̌���ɓn���b��b�̂��ꂾ���̈�v���A���ݎؗp�Ő�������͖̂������ƍl������Ȃ��B�p��A�t�����X��A�q�b�^�C�g��́A���ʑc�ꂩ��a�������ƍl����̂��Ó��Ƃ������ƂɂȂ�B�i�T���X�N���b�g��Ƃ̑Ή������ׂĂ݂悤���Ǝv�����������h�E�ɂȂ����̂ł�߂��B�j �ȏ�q�ׂĂ����悤�ɁA��̌���̔�r�����Ō݂��̌n���W�m�ɂ��鎖�͔��ɓ���B�����Ȃ��Ƃ��R�̌��ꂪ�Ȃ��Ɛ��m�ȋc�_�͂ł��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��x�_���R���Ȃ��ƈ֎q���Ђ�����Ԃ��Ă��܂��̂Ɠ����ł���B �I�[�X�g���l�V�A��r����w�̎����I�ȑn�n�҂ł���n�D�c��������o������ ���A���X���_�����h�̗̈���ɑ傫���O�p�`��`���āA�t�B���s���k���̃^�K���O��A�X�}�g���������̃g�o�E�o�^�N��A�W�����������̃W�������3�����I�сA�����R�̌���̑��ݔ�r����}�����E�|���l�V�A�c����č\�����̂́A�܂��ɂ��́u�R�_�x���̌����v�ɂ����̂ł���B ���N��Ɠ��{��̔�r�ł��u��O�̌���v���K�v�ł���B�ꂾ���̔�r�ł͐����ɒH�蒅�����͓���B ������u������v�▞�B��Ȃǂ̃c���O�[�X���ꂪ�u�~�b�V���O�E�����N�v�ƂȂ鎖�����҂��ꂽ���P�����A�O�҂͎c���ꂽ���������܂�ɒf�ГI�ł������������Ɋ�Â����߂ɉ��C�Ή���ݒ肷�邾���̐��x�������Ȃ��B��҂͍��܂ő����̃A���^�C��r����w�҂��J�͂��Ă����ɂ�������炸�傫�Ȑ��ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B �k���_���Ȃ��ɖڂ�������Ƃǂ��Ȃ邩�A�Ƃ����̂��M�҂̖ژ_�݂ł���B ���_ �S�`���S�`���Ƃ�Ƃ߂Ȃ������q�ׂĂ��܂����̂ŁA�_�_���{�����Ă��܂����B�{�e�̎�v�ȖړI�͖`���ł��q�ׂ��悤�ɁA����N��w�̗^����N�オ�ǂꂭ�炢�M�p�ł��邩�������邱�Ƃł������B �p��E�t�����X��E���e����E�q�b�^�C�g��̊�b��b��v�����狁�߂��u��������̕���N��@tS�v�ƁA�c�ꂩ��̕���N�ォ��v�Z���@(t1+t2)/2�@�ŋ��߂��A�u��������N�� teff�v���r�����\�������B����N��w�̉��肪��������ΈقȂ���@�ŋ��߂���̐����͈�v����n�Y�ł���B
�A�������ŁA�c�ꂩ��̊e����̕���N��� �p��F�@�@�@�@�@2500�N �t�����X��F�@3500�N ���e����F�@�@2000�N�@�i�f�[�^�͋I�����N���̂��́j �q�b�^�C�g��F�@2300�N�@�i�f�[�^��BC1700�N���̂��́j �Ƒz�肵�A�c��̒a����BC4000�N�Ƃ��āA���e����̒a����BC2000�N�Ɖ��肵���B�����̐����͂��Ȃ�̕��������������ƍl����ׂ��ł���B �q�b�^�C�g��Ɋւ��Ă͌���N��w���狁�߂��������E�\�̂��̂����傫���o��̂́A���̌���ł͊�b��b�ւ̎ؗp��̐Z���������̌�����������Ƒ傫�����߂Ɍ덷���傫���Ȃ邽�߂ł���B �����ł͎����Ȃ��������Q���}������Ɍ���N��w��K�p����ƕ���N�オ���j�ߒ����琄�������N������o�Ă��܂��̂����A����̓Q���}�����ꂪ���������̌�h�ɔ�݂��ɖ��ڂȃR���^�N�g��ێ�����������������Ȃ��B1000�N�łW�P���Ƃ�����b�c�����́A���Ȃ范������b�̒u��������������ɂ��ē��Ă͂܂鐔���Ǝv����B ���Ȃ݂ɁA�{�e�ōs������b��v���̌v�Z��40�ꃊ�X�g�Ɋ�Â����̂ł��邪�A�P�O�O�ꃊ�X�g���g�p���Ă��A�傫�ȍ��͏o�Ȃ����͊m�F�����B�Ⴆ�A�p��ƃt�������X��̈�v���́A�{�e�ł͂R�O���Ƃ������P�O�O��ł͂R�R���A�p��ƃ��e����͂S�O���Ƃ������A�P�O�O�ꂾ�ƂR�W���A���e����ƃt�����X��͂V�R���Ƃ������A100��ł��������V�R���ł������B�q�b�^�C�g��ɂ��Ă͌덷���傫�����Ƃł����邵�A�T�{�b��100�ꃊ�X�g�̍쐬�͍s��Ȃ������B ���e�̗\�� �����܂ł����_�Ƃ��������ꂩ��̋c�_�̏����ŁA���ꂩ�炪�悤�₭�{�ԂȂ̂����A���z���E�̘_���̕`�ʂ����߂��Ă��܂������A����N��w�̌����ɂ�������n�}�b�Ă��܂����Ԃ��₵�Ă��܂����B�����͂����܂łƂ��Ă������A �u���{�ꂪ�퐶����̏��߂ɒ��N�ꂩ�番���Ƃ������̉ۂ�����N��w���g���Ę_����Ƃǂ��Ȃ邩�H�v �ɂ��ĐG��Ă����B �퐶����̎n�߂ɓ��{�ꂪ���N�ꂩ�番���Ƃ���B�ޗǎ���̓��{��i�W���I�j�ƒ������N��i�P�T���I�j���r�����ꍇ�A�ǂ̒��x�̌�b��v���������܂�邾�낤���H �P�[�X�P�D�@�퐶����̊J�n���]�����ʂ�ɂa�b�T�O�O�N�Ƃ����ꍇ �c��i���a�b500�N�ɂ����钩�N��j����̗���̕���N��́A���ꂼ��A �Ñ���{��F�@t1= 500+800=1300�N �������N��F t2 = 500+1500=2000�N �ƂȂ�̂ŁA��������N��́@teff = (t1+t2)/2= 1650�N�ƂȂ�B����N��w����\�z������b��v���́A�T�O���ƂȂ�B ������u��k�͂�߂Ă����v�Ƃ������炢�ɗL�蓾�Ȃ������ł���B�Ƃ���ΑO�Ԉ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�a�b�T�O�O�N����_�Ƃ��钩�N�ꂩ��̓��{�ꕪ����͂P�O�O���L�蓾�Ȃ��B�i�ڂ����͎��e�ŁB�j �P�[�X�Q�D�@�V���ɏ]���퐶����̊J�n���a�b�P�O�O�O�N�Ƃ����ꍇ ��������N��́A�P�[�X�P�̐�����500�N�lj����ā@teff= 2150�N�ƂȂ邪�A����͒��x�A�p��ƃ��e����́i��������́j����N��Q�P�W�O�N�Ƃقڈ�v�����B����N��w����\�z�������b��v���͂R�X���ł���B��b��v���S�O������������Ƃ͂ǂ��������̂��A�p��ƃ��e����̌�b��r�\���Čf����B
���ꂭ�炢�Ñ���{��ƒ������N�ꂪ���Ă���A���̐�����������\��������Ƃ������ł���B�ӊO�Ɣ����ł���B��X�́A�u�����v��m���Ă���̂ŁA�p��ƃ��e����̌�b��v�����S�O�����Ɗm�M���Ȃ��Č�����̂ł��邪�A���̕\�������画�f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁA�p��́h�h�h�A�hhead�h�A �heye�h���{���Ƀ��e����� "ego", "caput", "oculus" �Ɠ������̔��f�͓���B�h�C�c��̃f�[�^���g����Ȃ�A�����͂��ꂼ��"ich", "Haupt", "Auge" �ŗގ��͂��Ȃ薾�m�Ȃ̂����A�p��͂���������`�ω����������̂ł���B�hsun �h�ɂ��Ă��Ō�̎q��������Ȃ��B�m���炵���Ή���������̂�12��A���ɂ����30���ł���B �����ȉ��C�Ή������߂�ƁA���m�Ȍ�b��v�������߂�̂�����Ȃ�B���C�Ή������[�Y�ɐݒ肷��U�҂��������闦���傫���Ȃ�B�������Y�܂����̂ł���B ���N��Ɠ��{��̔�r�͂܂��M�҂ɂƂ��Ă͏����s���Łu���������v�Ȃ̂����A�����͏�肩�������t�l�ł���B����ꂽ���P�܂��A���{��ƒ��N��͂ǂꂭ�炢���Ă���̂�����������B ��芸�����A����́A�`�m�i�I�[�X�g���l�V�A�j��ɂ��Ă�����N��w���K�p�\���ǂ����ɂ��Ă��`�F�b�N���A���{��Ƃ`�m�c��̊W�ɂ��Č���N��w���牽�������邩�ɂ��čl�@���悤�Ǝv���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 4/12 ���e
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
