| �u���E����̂Ȃ��̓��{��v�i���{���Ȓ��j��ǂ� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�W�N�R�� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����N
�O�e�Əd�����邪�A���{���̎咣��v��ƈȉ��̒ʂ�ł���B
���̃O���t�́A��v����i���邢�͌ꑰ�j���Ƃɓ��{��ƈ�v��������̐������ŁA��v���Ȃ������̐����w�ŕ\�킵�Ď��������̂ł���B���Ƃw�𑫂��ĕK�������P�O�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂́A�P���ɂx�����E�m��������ł��Ȃ����ڂ����邩��ł���B 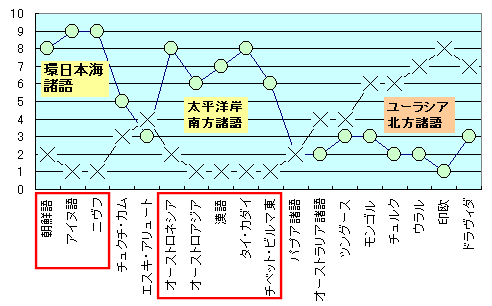 ���{��Ɨאڂ�����ӏ�����i��������{���́u���{�C����Q�v�ƌĂԁj�A���N��A�A�C�k��A�j���t��i�M�����[�N��j�Ƃ̗ގ������ЂƂ��팰���ŁA����Ɍp���ŁA�������Ƃ̗ގ����������B������ƈӊO��������Ȃ����A�A���^�C�n����ł��郂���S���A�`�����N�A�c���O�[�X��Ƃ̗ގ��x�͒Ⴂ�B�Ƃ������A�قƂ�ǁu����I�v�ƌ�����p�^�[���������Ă���B�i�������Ȃ� �� �������B�j �O���t�E�̂U����Q�i���邢�͌ꑰ�j�A�h�����B�_����c���O�[�X����́A������m�X�g���e�B�b�N���ꑰ�̃����o�[�ł���B�i�m�X�g���e�B�b�N���ꑰ�ɂ̓A�t���J�E���ߓ��̃A�t���A�W�A�ꑰ���܂܂��B���{���̃f�[�^�ł��A�t���A�W�A����͖��ĂɁA���[���V�A��������Q�̓����p�^�[�����������A�����ł͏ȗ������B�j �m�X�g���e�B�b�N���ꑰ�̑��݂́A��ʂ̌���w�҂���͔F�߂��Ă��Ȃ������ł��邪�A�����̏�����܂Ƃ߂Ē��ꑰ�Ƃ��Ĉ������݂ɂ́A���̂悤�ȗތ^�w�I�l�@���������Ȃ�̍��������邱�Ƃ�����B �m�X�g���e�B�b�N�ꑰ�̘_�҂̒��ɂ́A���{��E���N��E�A�C�k�ꂪ�\�������o�[�ɓ���Ǝ咣����҂�����B�O���[���o�[�O�̂�����u���[���V�A���ꑰ���v�����{��E�A�C�k��E���N����\���v�f�Ƃ���B�������A�O���t���番��悤�ɁA�����u���{�C����v�́A���[���V�A�嗤�n������ł͂Ȃ��A�ނ�����������Ɠ����p�^�[�����ގ����Ă���B �f�[�^�̕\���͈͂��A�����J�嗤�܂Ŋg�債���̂����̃O���t�ł���B�ώG�ɂȂ�̂œ�ď�����͗������B���{���̌����u�������m���ꌗ�v�̑��݂𖾗Ăɂ��邽�߂ɁA�G�X�L���[�E�A�����[�g/�`���N�`�E�J���`���b�J�̖k������ƃ��[���V�A������������ɔz�u�����B 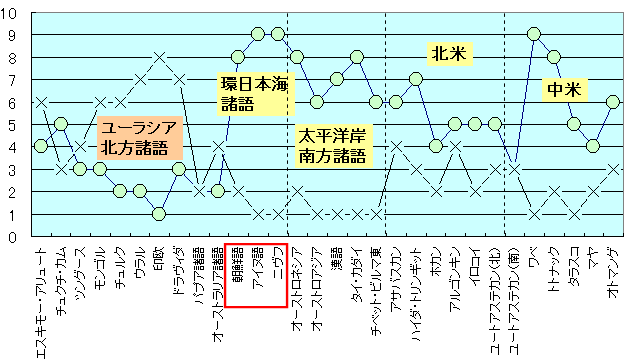 ���ď���̓f�[�^�̕��U���傫�����A���[���V�A������͂����Ɠ��{��Ƃ̗ގ������傫���B���{���狗������������ɏ]���ā��̐��͉E������Ɍ������A�w�̐��������Ă���悤�Ɍ�����̂��A�Ȃ������Ƃ��炵���v����B�����̌��ʂ���A���{���́A�ȉ��̂悤�Ɍ��_�t����B �u�Ƃ�����A���{��̉������n���̊O���ɒT���̂ł���A���̎����͐������[���V�A�����ނ��듌��A�W�A�A����ɂ͂܂������m�̂͂邩�ޕ��A�A�����J��Z���̌���ւƌ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{��̕�قƂȂ����h�����{�C���ꌗ�h�́A�����m�����͂ނ�������͂邩�ɍL��ȁh�������m���ꌗ�h�̈ꕔ�ɑ��Ȃ�Ȃ���������ł���B ( p. 184) �A�����J�嗤�̌���ɂ��Ă͍X�ɏڍׂȌ������K�v�Ǝv���B�A�����J�嗤�̌��ꐔ�́A�P�O�O�O�Ƃ��Q�T�O�O�Ƃ������A�n���W���܂Ƃ߂��ꑰ�̐��́i���Ƃɂ���Č������قȂ邪�j�P�T�O�ɂ��Ȃ�B�����̋ɂ߂đ��l�Ȍ��ꂪ�A�ތ^�p�^�[�������L����܂Ƃ܂�������Q�Ƃ݂Ȃ����邩�ɂ��ẮA�����炭���Ƃ͉��^�I�Ȍ����������̂ł͂Ȃ����Ǝv�������j�B �������̌n���W�ɂ��Ă͏��������Ċm�肵�Ă��Ȃ����A��b���܂߂����݂̗ގ��������݂��邱�Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂�Ƃ���ł���B�A���A����͌n���W����������Ƃ������́A�����Ԃ̌���ڐG�ɂ���Đ��������ʌ��ۂƉ��߂���ێ�I�Ȍ������L�͂Ǝv����B ���j�@�q�Ƃk����ʂ��邩�Ƃ��������^�C�v�̕��ނɂ��āB�k�D�L�����x���́@"American Indian Languages (1997)"�ɏЉ��Ă���e�C���f�B�A���c��̍č\���ꂽ���C�Ɋ�Â��āA�M�Ҏ��g�Ńf�[�^���W�v���Ă݂��B�ʔ������ƂɁA�����̃f�[�^�Ɋ�Â����{���̂��̂ƂقƂ�Ǔ������ʂƂȂ����B�i��Ă͍č\���ꂽ�ꑰ�������Ȃ��̂Ńf�[�^���s�����Ă���B�j�@���{���̃f�[�^���ƁA���Ăł́A�k�Ƃq�̂Q��ނ̗������g������̊����������A�P���������Ă���B��������{���́A�X�y�C���l�ɂ�钷���ɓn��A���n���̂��߂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���(p.91)���A�c��Ō���ƁA���ď���ɂ����镡�������̏o���p�x�͌������Ă���B�����k���Ă��i�����炭�P�O�O�O�`�Q�O�O�O�N�O���炢�j�A�A�����J�嗤�ɂ́A�q�Ƃk�̋�ʂ����Ȃ����ꂪ�����ƌ������͂ł������ł���B
���{���A�C�k�ꂪ�A�����J��Z���̌���Ɨގ����Ă���ƌ����ƁA�˔��q���Ȃ��g���f�����Ɏv���邩������Ȃ����A�A�����J�嗤�̌���Ƒ����m���ݕ��̌��ꂪ�߉��W�ɂ���Ƃ��������g�͖ڐV�������̂ł͂Ȃ��B�k�ăC���f�B�A���̌���ƃV�i�E�`�x�b�g��Ƃ̗ގ���^�ʖڂɌ��������̂́A���́A�d�D�T�s�A�ł���B�����Ƃ��A�ނ͂��̂悤�ȓ˔�Ȑ������ɂ��邱�Ƃ�����A���̃A�C�f�A��e���������ւ̎莆�̒��Ō��ɗ��߂��B�T�s�A�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �u�����������o�����i�f�l����i�A�T�o�X�J����Ȃǂ��܂ޖk�ăC���f�B�A���̌���Q�j�ƃV�i�E�`�x�b�g�ꑰ�Ƃ̊Ԃ̌`�Ԃƌ�b�̗ގ����w���R�x���Ƃ����̂Ȃ�A�_�̑��苋�������̐��ɂ����邷�ׂĂ̗ގ������R�ƕЕt�����Ă��܂����낤�B�v �u�`�x�b�g��̌�u���A"ma" (���Ɂj�ƁA"du"�i�ꏊ�F�@�`�Ɂj�́A�Ƃ��ɃA�T�o�X�J����ƃe�B���M�b�g��ɑ��݂��A�������A�������Ƃ��Ďg���Ă���B�i�����j�������́A�`�x�b�g��ł́@s- �Ƃ����ړ�����L���邪�A�e�B���O���b�g��ł́Asi- , li- ���B�`�x�b�g��ł͕ꉹ��ցi�ω��j�Ŏ������\������邪�A����̓e�B���O���b�g��Ɠ������B�i�Ⴆ�A�u���v�̌��`�F�@byed,�@�ߋ��`�F�@byas�A �����`�F�@bya�@�Ȃǁj ���́A�������Ă���̂��낤���H�@���Ȃ��Ƃ��A���ɂ́A�e�B���M�b�g��́A�ׂ̃V�I�E�A��������`�x�b�g��ɂ����Ǝ��Ă���Ƃ����v���Ȃ��B�v �i�P�X�Q�O�N�ɃT�s�A���N���[�o�[�Ɉ��Ă��莆�F�@L. Campbell "American Indian Language" p.286-287 �̈��p���A���p����ȗ������ď����Ӗ��B�����͈��p�҂ɂ��B�j ���ẮA�������j�E��r����w��������n�߂����ɂ́A���悤�ȑs��ȉ����ɖ������āA�O���[���o�[�O���u�v���j�����P��i�c��ł͂Ȃ��I�j�Ɠ��{��̊W��T�낤�Ǝ��݂����̂ł���B���̌o�܂́A�{�g�o�� Part III �u���ɂ̋N�������߂��v�ɋL�������A��Ɉ��p�����@L. �L�����x�� �̒����ŃO���[���o�[�O�����O��I�ɔᔻ����Ă���̂�ǂ�A�L�����x�����g�����������ȏ��i "Historical Linguistics �@-An Introduction-" 2004�N�ɑ��ł��o��) �ŗ��j����w�̎�@��������肵�Ă��邤���ɁA���̂悤�Ȏ��݂́u�ϑz�v�E�u�g���f�����v�̃^�O�C�ƌ��Ɏ������B ���j�@�O���[���o�[�O�� "Languages in the Americas" ���ŋߓǂݒ����Ă݂��i�Ƃ��������߂��j���A�u�R�W�c�P�ꌹ�̃I���p���[�h�v�Ƃ����C������B����ł́A�L�����x���̂悤�Ȍ����Ȋw���̊w�҂����𗧂Ă�̂������Ȃ��Ǝv���B ���悤�ȁu�l�I����v������̂ŁA���Ƃ��ẮA���{�����`���I�Ȕ�r����w�Ƃ͈قȂ�A�v���[�`�ŁA���Ăd�D�T�s�A���������A�A�����J��Z���Ƌ��嗤����̌q������u�_�Ԍ�����v�i�u�ؖ��v�ɂ͒������ƕM�҂͎v�����j�f�[�^���������Ƃ����͔̂��ɋ����[���v����B ��荇�����u�����m���ꌗ�v�̑��݂�F�߂�Ƃ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�Ɍ`�����ꂽ�������ɂȂ邪�A���R�A�����S���C�h�̊g�U�E�ڏZ�o�H�f�������̂ł͂Ȃ����ƍl������B��������ǓI�ɂ͂���ŗǂ��Ƃ��Ă��A���{��A���邢�́u���{�C����v���ǂ̂悤�Ȍo�܂œ������Ɨގ�����L����Ɏ��������ƂȂ�ƁA���������A���߂͓���悤�Ɏv����B �����łЂƂ܂�����w�𗣂�A�l�Êw�E�l�ފw���画�����Ă��邱�Ƃ����Ă��������B �����S���C�h�̈ڏZ�E�g�U�o�H�ɂ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@(2008 03/15��) �ȉ��̋L�q�́A��ʌ����̉�������j�ɏ�����Ă��邱�Ƃ��A�M�҂̗����Ɋ�Â��ėv���̂����A�s���̂��߂悭����Ȃ����Ƃ������B�����A���㏑���������K�v�ɂȂ�Ǝv���B�i���������Q�l�ɂ����{�����ƂȂ��Ă͂��������Â��B�j ���}�ɂ����āA�ԂŎ������̂́A�A�t���J���o���l�ނ��S���E�ւǂ̂悤�Ɋg�U�����̂�����G�c�����������̂ł���B�ߔN�̕��q�l�ފw�̒m���ɂ��A����œ���A�W�A�ƃI�[�X�g�����A�ɓ��B���������S���C�h�́A�A�����J�嗤�ɂ����B�������A�l�Êw�E�`���l�ފw�̏؋��ɂ��A�������S���C�h�����ڃA�����J�ɓ��B�����킯�ł͂Ȃ��A�V�x���A�Œa����������n�K���^�̐V�����S���C�h�i�ŕ\���j���A�}�����X��ǂ��ĕX�������x�[�����O�C����n�����Ƃ����̂�����炵���B �������A�A�����J��Z���̂c�m�`�͂��Ȃ葽�l�ŁA�������S���C�h�̈�`�q�������p����h���A�����J�嗤�ɓ��B�������Ƃ��m���炵���B�Ƃ���A�V�������S���C�h�̍��������Ȃ�k���Ő��������ƂɂȂ�Ǝv����B�V�����S���C�h�̏o���ɂ��ẮA�������S���C�h������n�ɓK������悤�ɕψق������̂Ȃ̂��A����Ƃ������A�W�A�o�R�i���̓_���j�ŃV�x���A�ɂ���Ă����A���Ȃ̂��A�悭����Ȃ��B�i�Ƃ������A�����ƒ��ׂĂȂ��B�j 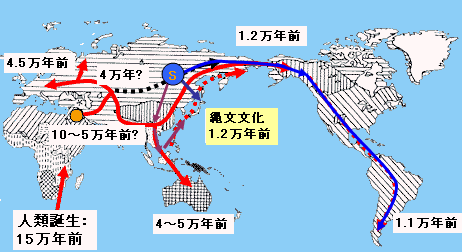 ����A�V�����S���C�h�̈�`�q�������p����h���A�V�x���A��쉺���āA���������������{�����ɓ������ēꕶ�l�̑c��ƂȂ��������A�قڊm���̂悤�ł���B�i�̖��j�@�A���A�ꕶ�l�̌n���ɂ��Ă��A�P���ɖk���n�Ƃ͒f���ł��Ȃ��悤�ł���B�`���I�ɂ́A�ꕶ�l�͖��炩�ɋ������S���C�h�ŁA����I�ȓ����������Ă���B �V�x���A�����V�����S���C�h�̕ʂ̈�c�́A�����嗤���o�čŏI�I�ɂ͓���A�W�A�܂œ��B���A�������S���C�h��Z���̌�����쒀�������̂Ǝv����i���F�̖��j�B�t�B���s���̈ꕔ�Ɏc��l�O���g�A�I�[�X�g�����A�̃A�{���W�j�A�p�v�A�j���[�M�j�A�̌��ꂪ�A�����m�ݏ���̂��̂Ƒ傫���قȂ�����p�^�[���������̂́A����炪�������S���C�h�̌���̎q��������ƍl������B�A���A����͋쒀���ꂽ���������S���C�h�Ƃ̍����ɂ���āA���̈�h�̌`���ɂ͂��Ȃ�̕ψق����������̂Ǝv����B �ꕶ�l�́A���⎕�Ȃǂ̌`�����画�f����Ɠ���n�A�c�m�`��l�Êw�̒m������͖k���n�Ɩ����������ʂ��o�Ă���B �A�C�k�l�̌n���ƂȂ�ƁA�X�ɂ悭����Ȃ��B�`�����炷��Ɠꕶ�l�ɋ߂��B�X�ɁA�`�s�k�E�B���X�ۗ̕L���A���̌`��Ȃǂ͉���̐l�Ƌ߂��B����炩�炷��ƃA�C�k�͓���n�Ǝv����̂����A�c�m�`����́A�ꕶ�l�Ɠ������k���n�Ɣ��肳��邻���ł���B ���̖�������������ɂ́A��������k���܂Ői�o�����������S���C�h���A�V�����S���C�h�ƍ����������Ӓn��ɉ����o����āA���̈�h�����{�i�����j�◮���ɈڏZ���Ă��ēꕶ�l�ɂȂ����ƍl����̂��Ó��Ǝv����̂����A���������邾���̃f�[�^�͂Ȃ��悤�ł���B ���q�E�`���l�ފw��l�Êw�̒m���������Ă��A�ꕶ�l�̌n���Ɋւ��āA�܂��Ĕނ�̌���ɂ��Ċm���Ɍ����邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�ł���B�m���炵���̂́A�����m���ꌗ�́A�V�����S���C�h�̌���̓����f���Ă���̂��낤�Ƃ��������炢�ł���B�ꕶ�l��A�C�k�l�̌��ꂪ����n���k���n���ȂǂƂ������́A�i������O�����j�����獜��c�m�`�ׂĂ�����Ȃ��B���ǂ̂Ƃ���A����̂��Ƃ͂����܂Ō���w�Ō��_���o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����ŕM�҂ɂ͔��ɋ����[���v��ꂽ�f�[�^���Љ�Ă����B �i�u���{�l�͂邩�ȗ��v�@ -�}�����X�n���^�[�@�V�x���A����̗�����-�@p.146-147) �����̏t�H�퍑����A�R�������ɐĂƂ��������������B���̍��̎�s�u�ՃV�v�i�������\���ł��Ȃ��B�T���Y�C�Ɂu���v�O�ɓc�ł���B�j����o�y�����l����m�c�m�`�i�~�g�R���h���A�c�m�`�j���͂��A���������ōs��ꂽ�B�̎悳�ꂽ���̔N��́A�t�H�퍑����i�Q�T�O�O�N�O�j�ƑO���i�Q�O�O�O�N�O�j�ŁA��r�̂��߂Ɍ���l��m�c�m�`�����͂��ꂽ�B ����l��m�c�m�`�́A�i���R�̂��ƂȂ���j���㒆���l�̂��̂ƕς��Ȃ��z�����̂ɁA�O����̂��̂���́A�Ȃ�ƃL���M�X�l�A�E�B�O���l�ȂǁA�����A�W�A�l�Ɨގ������z�������ꂽ�B���ꂾ���Ȃ炳�قNj����Ȃ����A�퍑����̂��̂́A�Ȃ�ƁA���[���b�p�l�W�c�ɋ߂��z��ɂȂ��Ă��������ł���B ���̌��ʂ���F�X�Ȗϑz��`�����Ƃ��\�Ǝv���邪�A�������̌����҂ł��鉤�펁�́A�u�����̑����̍l�Êw�҂��狭�����ɂ����Ă���v�����ł���B���̌�A���́u�唭���v���ǂ��Ȃ����������͂��邪�A���ׂĂȂ��B���̌��ʂ���A�R�������̏Z�����Q�T�O�O�N�O�ɂ͈�A�����̓`�����N���b���Ă����ƌ��_����̂́A�u�j�L�v��u�����v�̋L�q���炷��ƁA���܂�ɑ�_�ɉ߂���Ǝv����B�M�҂Ƃ��ẮA�u�c�m�`�̃f�[�^�͉L�ۂ݂ɂł��Ȃ��v�����P�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B ���j�@�ȏ�̋L�q�� �u�����S���C�h�̓��v�@�����I���@(1996) �u�������͂ǂ����痈���̂��v�@�����_�F�@�����V���Ё@(1998) �u���{�l�͂邩�ȗ��v�@vol 1-2 �m�g�j�o�Ł@(2001) �u�ꕶ�_���v�@�����T��Y�@�u�k�Ё@(2003) �Ȃǂ��Q�l�ɂ����B ����w�ɘb����߂����Ƃɂ������B �����m���ꌗ���A�V�����S���C�h�̑�ړ��ɂ���Č`�����ꂽ�Ƃ��āA�P������N�̒����ɓn���Č���̗ތ^�I�������ۑ����ꂽ�Ƃ����̂́A�ꌩ�A�₩�ɂ͐M���������C������B�Ƃ͌������A�����ȉ��̂悤�Ȏ����l���Ă��܂��̂ł���B ������Ɩϑz �V�x���A�ɂ́A��͂ł���n�����i�I�r�j�����߂Ƃ��āAAtobj, Aobj , Barobi, Kobj, Tymkob���@�ȂǁA�ꖖ�� Obj ��L����͂��������݂���B�C���N�[�c�N�̒n���w�ҁA�V���X�^�R�[���B�b�`�́A�P�X�Q�U�N�ɂ���������Ƃ��āA���ăV�x���A�ɂ́A���ł��Ă��܂������m�̌��ꂪ���݂��A���̌���ł́@�u���v���邢�́u�́v���Ӗ�����P�ꂪ�@"ob��"�������̂��낤�Ɛ������������ł���B�i���F���@�u�؍���̌n���v�@p.18��葷�����j ����A�O���[���o�[�O�ɂ��A�u���v�u�́v�u�J�v���Ӗ�����C���f�B�A������ɂ�
�Ȃǂ�����i�ꕔ�݈̂��p�@"Languages in the Americas" J. Greenberg p. 265�j�B��ɃO���[���o�[�O���́A�u�������ꌹ���v�ƈ��������������A����͂܂Ƃ��ȕ��ނɑ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B ����A�A�C�k��ɂ́A�u���t�v�����́u���v�ƍč\�����A"*pE " ������A���������N��́u�J�v�́A"pi"�ł���B�@(�A�C�k��̍č\�`�́AA. Vovin "A Reconstruction od Proto-Ainu"�ɂ��B) �ۛ��ڂŌ���Aobj/api/pE/pi�@�͎��Ă���ƌ����悤���A�����炭�A�O���[���o�[�O��O��I�ɔᔻ�����A�k�D�L�����x���t���Ȃ�ȉ��̂悤�ɔ��_����Ǝv����B
����ތ^�n���_�͉������̂��H ���āB ���������A���{�����������ތ^�I�����������Ă��Č���̌n���W��_���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��낤���H�ł��Ȃ��Ƃ����̂������ł���B�����[�I�Ɏ����̂��A���{�����g���������A�`�x�b�g����̎���ł���B���{���ɂ��A�`�x�b�g��͓����Ɛ����ňقȂ����p�^�[���������B(p.188�̕\���j
�`�x�b�g��́A�V�i�E�`�x�b�g�ꑰ����M����A������Ɨމ��W�ɂ���n�Y�����A���Ɠ��Ńp�^�[�������Ă���B����́A�������ꂪ�������[���V�A����Q�Ƃ̐ڐG�ɂ���ĉe���������߂Ƃ���B�]���āA���{�������o���� �u����̊�{�I�Ȑ��i���`������v�������ގ����Ă��������ł́A����̌n�������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����`�x�b�g����̌n���́A�`���I�Ȕ�r����w�̎�@��p���Ĕ��肷����Ȃ��̂ł���B �]���āA���{�C����Ƒ����m�ݏ��ꂪ�����p�^�[�������L����̂́A���҂�
���́u���{�C������܂Ƃ߂��v�Ƃ����̂��A�]���ɂȂ������V�������_�ł���B ���{���̒�����ǂ�ŕM�҂��l����V���ɂ����̂́A���{��ƃA�C�k��̊W�ɂ��Ăł���B�M�҂́A���{��ƃA�C�k��̊Ԃɂ͌�b�̗ގ��Ⴊ�Ȃ��Ƃ���A���{��̋N����_����ۂ̎Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƌ��ߕt���Ă����̂����A���N��ƃA�C�k��̊�b��b���ׂĂ݂�ƁA�u�H�I�v�Ǝv�킹��ގ��Ⴊ������������B��ɋ������u���v�͂��̈��ł���B����͖ʔ����Ǝv�����̂����A�����l�Y�́u���{��̌n���v��ǂݕԂ��Ă݂���A���Ɏw�E����Ă��鎖�ł������B(p. 104)�@�ȑO�ɂ͌������Ă����̂ł���B ���{��A�A�C�k��A���N����Z�b�g�ɂ��ē������Ɣ�ׂ�Ɩʔ����̂ł͂Ȃ����ƁA���݁A�l���Ă���Ƃ���ł���B�i�j���t��܂ł͎肪���Ȃ��B�j�l�@�̌��ʂƂ������o�܂ɂ��ẮA������ʍe�ŏq�ׂ�\��ł���B ���{�����g���A�l�̑㖼���ɂ��āA���̂悤�Ȏ��݂��̑�U�͂Ŏ��H���Ă���B�������A�M�҂�����Ƃ���ł́A���������_�|���ƒf�I�Ǝv����B ���{���ɂ��l�̑㖼���̔�r�ɂ��� �J��Ԃ��ɂȂ邪�A���{��������{��̋N���Ɋւ��ĐV�����m�����Ƃ���A
���̐l�̑㖼���Ɋւ���c�_�́A��̂P�ƂQ�������鎎�݂Ǝv���邪�A�������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B���{���́A�u���{�C����v�̐l�̑㖼�����ȉ��̂悤�ɍč\����B(p. 254)
�M�҂́A���{��̂P�l�̂��Aka �ɑk�鍪���͉����Ȃ��ƍl����B���{���́A���_����肵�āA �i�Ñ���{��́@�u�A�v�A�u�I���v���瓱�����j�@�ua-/o- �Ƃ�����q���[���̂��̌`�́A���łɑ����̌���ł��̗Ⴊ����ꂽ�悤�ɁA���^�{���̂P�l�̑㖼��������Â���ꓪ�q�� k- �̏����ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ������肪�e�Ղɓ������B�v(p. 241) �Ƃ���B����͋����ł���B���l�ɁA���N��̂P�l�̑㖼�����@ka �ɑk�鍪�����Ȃ��B�Q�l�̂ɂ��ẮA�Î��L�Ȃǂɏo�Ă���C�}�V���Ai-ma-si �Ƌ���āAma�@���Ì`�Ƃ���Bi �Ɓ@si �������Ӗ����邩�̌��y�͂Ȃ��B���i�i���W�j�A�C�}�V���炷��A��l�̑㖼���� si �Ƃ���̂��Ó��ƕM�҂ɂ͎v����B�A�C�k��A���N��̓�l�̂��@ma �������Ƃ����������S���Ȃ��B�i�������ɁH��t���Ă��邪�B�j �Ȃ��������������ȋc�_�����邩�ƌ����ƁA���_���ŏ����猈�܂��Ă��邩�炾�Ƃ����v���Ȃ��B���{���́A�����암���瓌��A�W�A�A�C���h�����܂ōL���鏔����̐l�̑㖼���V�X�e�����ȉ��̂悤�ɕ��ށE�č\����B
���̕\������ƁA�Ȃ����{������̂悤�ɓ��{��̂P�l�̂ƂQ�l�̑㖼�����č\����������������ł��낤�B ���{���́A��l�́i�����Ƒ�����܂ސl�́E�u��X�v�j�Ɋ�Â����O���[�v�����������ɁA���{��E���N��́A�`�Q�ɁA�A�C�k��E�j���t��́A�a�Q�ɑ�����Ƃ���(p. 246)�̂����A�M�҂̌����ł́A��������č\�������{��̐l�̑㖼���V�X�e���́A/ana/si/bə/�ł����āA��̂ǂ̌�Q�Ƃ����S�ɂ���v���Ȃ��B �a�Q�̂P�l�̂� n- ���������������߂ɁA�����I�Z�A�j�A��̌�` (inau) ���Q�Ƃ��Ă��邪�A�����I�Z�A�j�A��Q�̕���́A���s�^�������a�������N��̂a�b�P�T�O�O�N��啝�ɉ���n�Y�͂Ȃ��A�V������`�ł���B�ォ��a���������̂��A�Ȃ���������O���炠��������̕��ނɎg����̂��낤���H�����I�[�X�g���l�V�A��̕�l�̂ɂ��Ă��A[k]ita �Ƃ��đc����@*ta �Ƃ��Ă���B�ꕔ�̌���� k ���E���������̂�����Ƃ��Ă��c��͂����܂ŁA*kita�ł���B���ɋ����ł���B ������ꂪ�A��L�̂悤�ȂQ��i���j�ꑰ�ɂ܂Ƃ߂���Ƃ��������i���Ȃ��Ƃ��ꕔ�̊w�ҊԂł́j�L�͂Ȃ̂ŁA������u���{�C����v�̕��ނ��Ή����������Ƃ������{���̈Ӑ}�͕M�҂ɂ������ł��邪�A����ł́u�v���N���X�e�X�̐Q��v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ǝv����B �܂��A���{���ł́A���{��Ɨމ��W���������ꑰ�́A�J���{�W�A��⃔�F�g�i���ꂪ��������I�[�X�g���E�A�W�A�ꑰ�ƁA�~���I�E���I�ꑰ�����̂������̂Ƃ������ɂȂ邪�A�M�Ҏ��g�́A���̌����ɏ]�����Ƃ͂ł��Ȃ��B �A�C�k�ꂪ�������i�ꑰ�j�ƊW����Ƃ������͑O���炠���āA���R���Y�́A�I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�i�a�Q�j�N�����A�`�D�u���������̓I�[�X�g���A�W�A�ꑰ�i�`�Q�̃����E�N���[���ƃ����_��������킹�����́j�N�����������Ă���B �A�C�k�ꂪ���N����܂߂ē���A�W�A�̌���Ɨމ��W�ɂ���Ƃ������́A����Ȃ�̍���������ƁA�M�҂��l����̂ŁA����A�ʍe�Ō������邱�Ƃɂ������B�i���m���Ȓ@����ƂȂ�̂́A�u�������������Ǝv���B�j ���{�����瓱�������{��̋N���́H ��̑㖼���Ɋւ���c�_������ƁA���{���́A���{�C����́u������v���A���ׂē���A�W�A����ɗR������Ƒz�肷��悤�ł��邪�A����������Ǝv����B ���{�C����Ɠ������̎�ȈႢ�́A�r�n�u�Ȃǂ̌ꏇ�ł��邪�A����́A��͂�A���^�C����Ƃ̐ڐG�ɂ���Đ������ƍl����̂��Ó��Ǝv����B���{���́A���{��̃A���^�C�N�������u�S���I�O��̊w���v�ƌ��ߕt����̂ŁA�ꏇ�̖��ɂ͈�،�������ł���悤�Ɏv����B �M�҂̍l���́A���ǁA����I�v�f�̏�Ƀ��[���V�A�I�v�f�����Ԃ����ē��{�ꂪ�`�����ꂽ�Ƃ����A�g���ő��R���ɂȂ��Ă��܂��̂ł��邪�A���{��̋N���͌Â����邽�߂Ɍn�����s���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����̂́A���ɓI�ɂ͐������ƕM�҂��l����B�ł́A���{��̋N���́A�I�v�̎��̗���̈Èł̒��ɉB����Ă��܂����̂��낤���H�M�҂́A���߂�̂͂܂������Ǝv���B �ł́A�˔j���͂ǂ��ɂ���̂��H �ꕶ����ɁA�i�A�C�k��������āj�u�����{��v�ƌĂѓ��錾�ꂪ���ɋψ�ɕ��z���Ă����Ƒz�肷��̂́A������������������Ǝv����B��{�I�ɂ́A��̏W�������c��ł����ꕶ�l�́A��������b�Ƃ��������̌Ǘ������O���[�v���U�݂��Đ��������`�����Ă������̂ƍl������B���l���̌Ǘ��W�c���U�݂�����Ԃ�����N���p������A�I�[�X�g�����A�E�p�v�A�j���[�M�j�A�E�A�����J�嗤�Ɍ�����悤�ɁA�݂��Ɍn�����s���Ȍ��ꂪ��ʂɕ��Ă��܂��\���������Ǝv����B�i�ꕶ����ɂ́A�y��̌`���Ȃǂ��炵�āA���Ȃ��Ƃ��A�X�̕��������������Ƃ����B���`�����A�������̈Ⴂ������̈Ⴂ���Ӗ�������̂ł͂Ȃ����B�j �������A�ޗǎ���ɂ́A���Ȃ��Ƃ���B����֓��n���܂ł́A�������͂�����̂́A�قڋψ�ȁu���{��v�ƌĂׂ���̂��A�a�����Ă������Ƃ͊m���Ǝv����B�����A���{��̋N���͔��ɌÂ����A���ꂪ���݂̓��{��ɒ��ڌq���錾��ƂȂ����͔̂�r�I�V�����̂ł͂Ȃ����낤���H�v����ɁA���{��������I�ɂ��퐶����ɒa�������Ƃ������ł���B�N���͌Â����a���͐V�����A�����Ɋ��H�����o���]�n������̂ł͂Ȃ����낤���H ���{�����A���{��Ɂu���ρv��������������퐶����ɋ��߂Ă���B(p. 178-179) ���N��Ɠ��{��Ƃ̊Ԃŋ��L���ꂽ��A�̌�����V�̌��ʁA�i�����j�A����ŃA�C�k���j���t��ɑ�\�����Â�����w�ƁA�����Œ��N��E���{��ɑ�\�����V��������w�����ݏo����邱�ƂɂȂ����B���̐V��������w�̏o���́A�i�����j�A����܂Œ����Ԋ��{�C�������Â��Ă����Ǝv���鏬����̖��W��---�����炭���l�����O�̖k�ẴJ���t�H���j�A��k���C�݂ɕC�G����悤�ȏ�---����ς������B���ʂƂ��āA���N�����Ɠ��{�̑啔���́A�h�V�Ί�v���h�̔g�ɏ�����A���̂Q�̐V������ɂ���āA���S�ɕ����s�����ꂽ�̂ł���B�@ �����̌�����V�Ƃ��̊g�U�̒��S�́A�����炭���N�����ɂ������B���̒n���I�������猩�āA������܂߂�������ʂŁA�嗤����̉e�����ł����ڂɎĂ�������ł���B�������A�k���Ɉʒu���Ă����A�C�k��́A���̊g�U�̑�g��h�����ĖƂ�A���{�C����̌Ñ���`����A���̏�Ȃ��M�d�ȏؐl�ƂȂ����̂ł���B �M�҂ɂ́A���{�����u�V�Ί�v���v�Ƃ�������g�����Ӗ�������Ȃ��B�ꕶ����͐V�Ί펞��ɋ敪�����B�퐶���������V�Ί펞��̊J���Ɖ��߂��Ă���̂��낤���H�������A�퐶�͐��펞��ł���B �����炭�A���������̂́A�퐶����Ɏn�܂�����p�������J�����c�_�k�̃Z�b�g�����N�������o�R���ē������������_�@�Ƃ��āA���̌���̋ψꉻ������ȃX�s�[�h�Ői�s�����Ƃ������Ǝv����B�����������Ƃ����Ȃ��̂ʼn��߂Ēf���Ă������A���{���́A�퐶����ɓ��{�ꂪ���N�ꂩ�番���ƌ����Ă��郏�P�ł͂Ȃ��B�����܂ŁA�`���ɏЉ���悤�ɁA ���{�ꂪ�A�퐶���㏉�߁i��a�b�T�O�O�N���j�����m�̑������i�Ⴆ�A���N���^�~����j���番�Đ������Ƃ����̂́A��r����w�̏펯���炵�ėL�蓾�Ȃ��B �Ƃ����̂����{���̎咣�ł���A�M�҂���ł͂��̎咣�Ɏ^������B�A���A�u������v�̂悤�����m�̑������ɂ�錾��̒u���������������\���͔ے肵�Ȃ��B�u������v�ɂ��ẮA���{���̓c���O�[�X�n����Ƃ͍l�����A��͂����n����Ɖ��߂���_�ɂ����ĕM�҂ƍl�����قȂ�B ����̗\�� �ȏオ�A���{���̒�����ǂ�ł̕M�҂́u�S�ʓI�Ȋ��z�v�ł���B�e�_�ɂ��ẮA�X�ɕʍe�Ř_���������Ƃ��F�X���邪�A�����ŕM�Ҏ��g�̌����_�ł̍l�����܂Ƃ߂č���̕��j�ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃɂ���B ���{��͂`�m��Ɛ[���W������A�A���^�C����⒩�N��Ƃ̗ގ��́A����ڐG��ؗp�ɂ���Đ������\�w�I�i���邢�͏�w�I�j�Ȃ��̂��Ƃ����M�҂̍l���́A���{���̎������f�[�^�ɂ���ĕ⋭���ꂽ�ƍl����B���{��͐[�w�ł́A����̌���ƌq�����Ă���ƕM�҂͍l����B ���܂ŁA�M�҂͈�т��āu����̌��ꁁ�`�m��v�Ƃ�����Ɖ����ɉ����Č������s���Ă����B�`�m��͂Ȃ�ƌ����Ă����{�Ƌ������߂��C�m�����̂��̂ł��邵�A�c�ꂪ�L�b�`���ƍč\�ł��Ă���̂����݂ł���B�M�҂Ƃ��ẮA���������ǂ����܂Œǂ��l�߂邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��邪�A����ł́A���{��͂`�m�c�ꂩ�璼�ڕ����Əؖ��ł����̂��ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��ƍl����B ���{�ꂩ�璩�N��̗v�f�A�A���^�C�I�ȗv�f�����A�X�ɁA�`�m��̗v�f�����Ă��A�܂����̉��ɉ����悭����Ȃ��w���B��Ă���Ƃ����̂��A���܂łɓ����M�҂́u�����v�ŁA����䂦�ɁA�s���l�܂�������Ă����̂ł���B ���{��̌n���͉����Ƃ�����A���ǂ͂P���N�O�́u�V�����S���C�h�c��v�ɑk��̂�������Ȃ��B����ڐG��ʂ��đ����m���ݏ��ꂪ���̏�ɂ��Ԃ���A�X�ɒ��N�������o�R�����������[���V�A�I�v�f���킳���āA���{�ꂪ�a�������B���R���̂悤�ȁA�I�[�X�g���l�V�A�E�A���^�C�����N�����ł������d��Ȃ��v�f�����{��ɂ���Ǝv����̂́A��͕s�\�Ȋ�w�����݂��邩�炩������Ȃ��B �Ƃ���A���{��́u�n���_�v��_���邱�Ƃ͋ɂ߂č�����A���{��a���́u�N���_�v�ɂ��ẮA���ꂪ���X�퐶����̂��Ƃł���Ȃ�A��r����w�̎�@��p���邱�Ƃɂ���āA������x�܂ł͉𖾂��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���Ƃ����̂��A�M�҂������Ă���u��]�v�ł���B �u�`�����s���ȏꍇ�͐�ǂ��g�傹��B�v �����̊i���ł���B��ɂ��q�ׂ������{�����������u���{�C����v�Ƃ����}�N���Ȏ��_��������āA�M�҂�����ȏ�̕��͕͂s�\�Ɣ��f����Ƃ���܂ł́A���{��́u�N���v�Ɋւ���l�@���p�����Ă������Ǝv���B ����̗\��ł���B ���܂ŕM�҂́A�u�N��v�Ƃ����̂��̂��قƂ�Ljӎ������ɍl�@���s���Ă����B�������A���{��̒a���́A�ꕶ�Ȃ̂��퐶�Ȃ̂����傫�Ȗ��Ƃ������ɂȂ�ƁA��͂�N��Ƃ����v�f�ɂ��čl������Ȃ��B�ƂȂ�ƁA����w�̗��ꂩ��́u����N��w�v�Ȃ���̂ɐG��Ȃ��ł͂����Ȃ��B �`���ɏЉ�����{���̑��̎咣�A ���{�ꂪ��앶���̓����A���Ȃ킿�A�퐶���㏉�߁i��a�b�T�O�O�N���j�����m�̑������i�Ⴆ�A���N���^�~����j���番�Đ������Ƃ����̂́A��r����w�̏펯���炵�ėL�蓾�Ȃ��B���{��̌n����肪�Ïʂɏ��グ���܂ܕs���ł���̂́A���{��̋N�����A��r����w�̗L���˒��ł���U��N�`�V��N���O�ɑk�����߂ł���B �́A���{��̋N����_�����ŃL�`���Ɨ}���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ���{���̊�{�̃|�C���g�ł���B���̎咣�͎�Ƃ��āu����N��w�v�Ɋ�Â��̂����A����́A���̎咣�̐���ɂ��āA��������B��{�O��̍Č����ł���B �M�҂͍��܂ŁA�u����N��w�v�Ƃ����w���ɂ͉��^�I�������̂����A�������Ă݂�ƁA�Ȃ��Ȃ��ʔ����u�I���`���v�ŁA��������n�}�b�Ă��܂����̂ł���B �Ō�ɁA���{���v�搶�ɂ͎ӈӂ�\�������B�F�X�Ǝ��炩�ᔻ�I�Ȏ��������Ă��܂������A���ɖʔ����A�����ɕx�h���I�Ȓ����ł���B�M�҂����̖��ɂ��āA�V���Ȏ��_����čl���Ă݂悤�Ƃ����C�ɂȂ����̂́A���̒����̂������ł���B�P�X�Q�X�N���܂�Ƃ��邩�瑊���Ȃ�����ł��邪�A�����ւ̎��O�E��M�ɂ͓���������v���ł���B���������A��w���������ނ��ē��{��ɂ��Ę_�����{�������ƁA�A�b�Ƌ����u�g���f�����v�������肷�鎖���������A����͂܂����������̐����h�Ƃ��������ł���B�i���X�A�s���߂����͂��邯��ǁB�j �M�҂̋L����ǂނ悤�Ȋ���Ȑl�ɂ́A�����ǂ������߂��邪�A����w�̒m����������x�Ȃ��ƁA������Ɠ�����ȁ[�Ƃ����C������B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 3/19 ���e
|
