| 「徹底検証! 日本語タミル語起源説」(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 音韻頻度分布の比較 タミル語の語幹は、 C1VC2 という形をしています。ここでC1、C2は子音、Vは母音です。C1がなくて母音で始まる語、母音だけの語形も存在します。 ここでは、それぞれの音がどういう特徴を持った頻度分布を持っているか、日本語と比べどこがどう違うのか、大野説ではどのような音韻対応を設定しているのか、について説明します。 (1)母音の出現頻度分布 まずは、話しが簡単な母音から検討することにします。 タミル語は、日本語と同じく、「アイウエオ」の5母音体系です。英語やフランス語を勉強して数多い母音の発音で苦労したヒトの中には、これだけで「おお! 日本語と同じではないか!」と素直に感心してしまう方もいるかもしれませんが、世界に5母音体制の言語はけっこうあります。 「けっこうある」どころか、ある統計では「アイウエオ」の5母音体系が、世界の言語で最も一般的なのです。一方、古代日本語では、少なくとも表記上は、8母音システムでした。(これには異論も多くあり、私も8母音説は採りません。) 大野説では、古代日本語は、a, i, u, o2 の4母音体系で、i2, e, e2, oは派生母音とみなす考えのようです。 大野説では、母音に関して、
という音韻対応を主張します。著書にはハッキリとは書いてありませんが、乙類のe と i は、二重母音から二次的に発達したと考えるようです。 この音韻対応表と両言語の母音頻度分布から、比較の際に母音が偶然に一致する確率を計算することができます。 (以下の記述は、わずらわしければ飛ばして下さい。) 頻度分布と偶然による一致率について: 両方の言語で音韻が偶然に一致する確率は、各音韻の出現頻度と音韻対応則で決まる。言語i の音韻 vの出現頻度をPi(v)と書けば、偶然一致率Aは、頻度の積の和、 A=Σ(i,j) P1(vi)P2(vj) で求まる。積の範囲(i,j)をどう取るかは、音韻対応則で決まる。 例えば、a,i u の3つしか母音がない言語を比較する場合、3つの母音の出現頻度がすべて同じで、a,i,u → a,i,u と対応する場合、偶然一致確率Aは、単純に頻度どうしを掛け算して足せば良く、 タイプ I 頻度分布がすべて等しい場合
となり、当たり前だが、偶然一致確率Aは、0.33、要するに、3分の1となる。 a,i, u の内、特にある音韻の出現率が大きく、その傾向が両言語間で一致する場合、 タイプ II 両言語で a がともに大きな頻度を有する場合
となって偶然による一致確率は増加する。しかし、その逆の場合、 タイプ III 言語Aでは a が頻度大、Bでは u の頻度が大きい場合
一致率は、必ず3分の1よりも小さくなる。 要するに、両言語で音韻の頻度分布が似ていると、偶然に一致する確率が大きくなる、という事です。(当たり前でしたかね?!) 日本語とタミル語の場合はどうなっているかと言うと、私が調べた所では、語幹の第一母音の出現頻度は以下のようになってます。
(ここではi2,e2の甲乙を同じ欄に一括しました。) どちらも「ア」がかなり優勢な頻度を示しており、偶然一致確率が大きくなるタイプです。 上の表の解釈については論ずべき点が色々とありますが、大筋とは関係ないので省略します。 上の頻度分布と音韻対応から頻度の掛け算の和、 A=Σ(i,j) P1(vi)P2(vj) を計算して母音の偶然一致率を求めると、37%になりました。 これはけっこう大きい数字です。大野説では必ずしも上の音韻対応は厳密には守られてないので注)偶然一致率は実際の比較作業では、更に大きくなっているものと思われます。 注) 例えば大野説では、日本語の「月」 tuku/i がタミル語の tinkal と同源と判定されている例がありますが、この場合は、i →u、 a→u というように、上の表とは異なる対応になっています。 (2) 語頭音の頻度分布 次に、語幹の最初の音(語頭音)の頻度分布を調べてみます。語頭音の頻度分布は、言語の特徴を良く表わします。この問題については、「匈奴は何語をしゃべっていたか?」で取上げた事があります。 語頭音の頻度分布を比較すると下のグラフのようになりました。なかなか興味深い結果です。 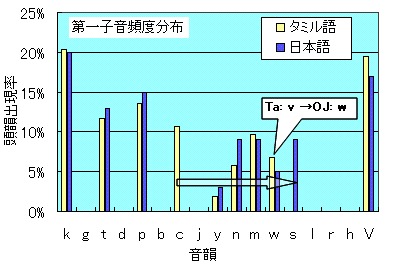 タミル語のvを日本語のwに対応させて図示しました。右端のVは母音(Vowel)です。 タミル語には、s音がない替わりに/c (ts)/ 音があります。この音を、グラフ中に示した矢印のように日本語のサ行に対応させると、タミル語と日本語は、ほぼ完璧に頻度分布が一致します。 (当然、大野氏も、タミル語の/c/に(基本的には)日本語のサ行を対応させています。) 両者の一致はなかなか驚くべきものがあります。 大野説の擁護者は、頻度分布の類似を、日本語とタミル語が同源である事の証拠のヒトツと考えるかもしれませんが、頻度分布が似ていると、偶然による一致率も増加するので、これは「諸刃の剣」なのです。言語の同源関係を証明するには、音韻構造は、むしろ似てない方が都合が良い場合が多いのです。 さて、ここからが問題なのです。 サ行について、大野氏は更にダメ押しで、以下の音韻対応を設定します。 日本語のあるものには、語頭の s音が脱落した語が存在する(アヲとサヲなど)。また、タミル語でも語頭の c音が不安定で、他のドラヴィダ語と比べると語頭の c 音が脱落した語が見られる。そこで、
しかし、これは「ちょっとズルイのではないか?」と私には思えます。 確かに、日本語で、「稲」が「シネ」になったり、「雨」が合成語で「春雨」(「ハルサメ」)となったりしますが、だからと言って、「日本語の母音始まりの語が、すべて、かつては/s/で始まった可能性がある」あるいは「タミル語の母音始まりの語が、すべて、かつては/c/で始まった可能性がある」と仮定するのは納得いきません。というか間違いだと思います。 このような比較が「虚構的」である事を、下の2例で説明します。 ケーススタディ (その1): 日本語 sakal ⇔ タミル語 akal 大野氏の 日本語 「明く」 aku ⇔ タミル語 「夜が明ける」 akal (DEDR: #8) 「離れる」 sakaru ⇔ タミル語 「離れる」 akal (DEDR: #8) を見ると首を傾げざるを得ません。(「一粒で2度おいしい」?) 大野氏の考えに従うと、
実は、DEDをちゃんと読めば分かる事なのですが、タミル語の語頭音 c の脱落が実証あるいは推定される場合には、その語は、辞書の c の項に記載される決まりになっているのです(一部例外もありますが)。例えば、タミル語の数詞「6」は、a:ru ですが、コンダ語で sa:rung という語形があって、タミル語の語形は、 cが脱落したものと判断されるので、DEDでは、c で始まる語として扱われています。 DEDは、名前の通り、Dravidian Etymological Dictionary (「ドラヴィダ語語源辞典」)なので、タミル語の語頭に c があろうがなかろうが、ドラヴィダ語全体で判断して語頭に c があったと判断される場合は、c の項に記載されるという事なのです。 では、タミル語: 「離れる」 akal はどうかと言うと、 辞書の a の項に載っているのです。つまり、バロー・エメノーの判断では、 akal は c が脱落した語形ではないのです。 他のドラヴィダ語に cakal はありませんし、c の他の項を見ても、類似語とおぼしき語は発見できません。従って、cakal は存在が確認されない「幽霊語」なのです。「幽霊」の存在を前提とした比較は科学的とは言えません。 なんか、「重箱の隅」をつつくような話しをしていると思われるかもしれませんが、上に述べたようにタミル語で母音で始まる語は非常に多く、それがすべて、無条件に、日本語のサ行単語と比べられてしまうのでは、偶然の一致を排除するのは困難でしょう。 大野氏が「日本語の起源」巻末に挙げる、「日本語 s - タミル語 母音始まり」の対応として19例が挙げられていますが、この内、a:y (小さい)と uppu (塩)の2語において c の脱落が確認できるだけで、他の17語は語頭に c をかぶせた実証されない「幽霊語」に変身させられ、日本語のサ行単語と「同源」と判定されているのです。決して「重箱の隅」のような細かい話しではありません。 このような「一点突破、全面展開方式」はヤ行音でも「全面採用」されています。 上の頻度分布をもう一度見て頂きたいのですが、日本語のヤ行単語を説明するには、タミル語のy- で始まる単語の数がチト少ないのです。この問題を、大野氏は、次のように「解決」しています。
こうして、タミル語の母音始まりの単語は、日本語の
確かに、大野氏の言うように、タミル語で母音始まりの単語のあるものは、古代語でy-語頭音を有していました。しかし、DEDには、どの語が古代語ではy-音で始まっていたのかが、ちゃんと記載されているのです。ところが、大野氏は、y-語頭音が証明されない語にも、y を被せた「幽霊語」を作って日本語のヤ行音単語と比べるのです。 ケーススタディ (その2) タミル語: a:cu ⇔ 日本語: 「痩せる」 タミル語 a:cu は、DEDでは#287に対応する語で、「小さい」「みすぼらしい」「細かい」「少量の」「減る」などの意味を持ちますが、この語が古代語で y 語頭音を有していた事は実証されません。しかし、大野氏は、このタミル語にy-を被せて、*ya:cu とし、日本語「痩せる」(yasu)と同源とします。 このような語が全部で15語挙げられています。 「日本語の起源」に挙げられた300語の対応例のうち、約10%は、このような「幽霊語」を使ったものと判断されます。 (3) 第二子音の頻度分布 最後に、第2子音C2の頻度分布ですが、以下のようになっています。
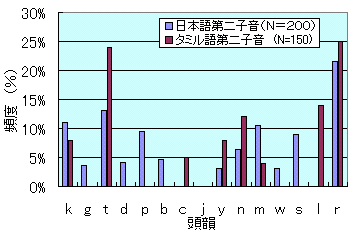 第二子音は、日本語とタミル語でかなり異なります。 タミル語では t、n、l、rの頻度分布が非常に大きくなっていますが、これはドラヴィダ語が有する音韻的特徴を考えると必然的な現象なのです。 今まで表記の簡略化のためにタミル語特有の音韻を無視して来たのですが、タミル語あるいはドラヴィダ語は、3種類の t 、4種類の n、2種類の rとl を区別します。
上の表の1列目の文字をクリックすると、発音が聞けるようにしておきました。(残念ながら流音の音声サンプルは手に入りませんでした。) 私、実は、何回も聞いたのですが、聞き分ける自信は全くありません。プロの言語学者になるには良い耳を持たないとダメなのですが、残念ながら私は落第です。 l、r、t、n はいずれも、発音する時の舌の位置(調音点)が近い音韻ですが、タミル語では、これが更に、反り舌音や、歯音や、歯茎音といったもっと微妙な音の出し方の違いでもって区別されているワケですが、これは、タミル語に限らないドラヴィダ語全体に共通する、最も顕著な音韻的特徴となっています。こういう言語は世界でもあまり例がないそうです注)。 上のグラフで、タミル語の l、r、t、nの頻度が大きいのは、こういう反り舌音やら歯音やらが日本語ではヒトツの音韻に融合したとみなされるために、複数の音韻の頻度を加算したものになっているからです。 上のグラフでは、l と r を区別して表示してますが、大野説では、更に両者が、日本語では、ラ行音に融合したと考えます。すると、日本語の r に対応するタミル語の音韻の頻度は、合計で約40%になり、日本語との違いは更に大きくなります。 もし語頭音の頻度分布の一致が日本語とタミル語の同源関係によるものだとすれば、なぜ第二子音では頻度分布がこんなに異なるか説明できないといけませんが、それは不可能でしょう。 中間のまとめ: 以上、タミル語における音韻の頻度分布と、大野説における音韻対応の設定について長々と説明してきました。 大野説の擁護者は、「音韻対応のさせ方に問題があると言っても、高々全比較例の10%ではないか、まだ90%の強力な比較例がある以上、大野説は安泰」と主張するでしょう。 その通りです。 大野説の本丸はまだ無傷で残っています。 次の節では、これまでの検討結果を元に、タミル語と日本語の偶然一致率を推定する方法について述べ、大野説本体の可否について検討します。 注) ドラヴィダ語と似た音韻構造の言語について ズベレヴィルの著書には、ドラヴィダ語のような音韻構造を持った言語が世界に稀である趣旨の記述があるのですが、オーストラリア北東部のPitta−Pitta語はドラヴィダ語に良く似た音韻構造を持っています。
t、n、l が4つ、rが2つあってこれはドラヴィダ語よりも凄い。 面白いのはこれだけ多くの歯茎音が集中して存在するのにドラヴィダ語と同じくs、z、や š がない事です。 ドラヴィダ語とオーストラリアの言語が系統的に関係あるハズもないので両者で発達した並行的な現象という事になります。 更新記録: 第一稿 2004年5月23日 作成 注)を追記 2004年8月1日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||