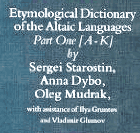|
アルタイ語族説から見た日朝両言語比較 (その1?) (2009/12/27, 2010/01/03) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシアの言語学者、S.ストラスティンの雄大なアルタイ語族説を日朝両言語の比較の観点から再検討することを試みた。 予備検討は、2年前からやっていたネタだが原稿を書き始めると、例によって予定が狂ってきた。筆者はアルタイ語族説は信じ難いという見解だが、この説が規模雄大にして「非常に面白い!」のは間違いない。しばらくハマッてしまうかもしれない。 2010年1月3日: かなり大幅に追記。本稿のテーマについて結論を下した。 はじめに 久しぶりの更新(なんと1年半ブリだ!)なので、筆者の頭の整理を兼ねて、前回の復習からはじめたい。日本語と朝鮮語の比較において問題となったのは、語中の /r/t/d/s/ の多重対応だった。基礎語彙における比較表を少し修正して以下に示す。(OJは上代日本語 Old Japaneseの略)
この現象を説明するヒトツの解決策は、日本語に古形が保たれているのに対して、朝鮮語では /r/t/d/s/ がすべて/r/ に合流してしまったとする事である。しかしこれに並行して、下表に示すように、日本語 /t/に対して朝鮮語 /t/が対応する例がある。朝鮮語で語中の -/t/- が /r/に変化したとする単純な考えは、うまくいかない。
上の比較は、日朝両言語を比較する際の定番だが、厳密に言うと、有気音化した/th/と/t/が対応するもの (a)〜(c)と、そうでないもの(d)〜(g)の二つのグループに分かれる。 前から何度も言っているように、朝鮮語の有気音(激音)の起源は難しい問題で、少なくとも一部については、語末の -k の痕跡ではないかと考えられている (金芳漢: 「韓国語の系統」 p.221 「石」;to:rh の語源に関して。) とすると、「畑」: path の h は 再構形 *patVk (V は不明の母音)における語末子音 -k の痕跡で、日本語の patake2 のke2と比較できる可能性が出て来る。しかし、patake2 は*pataka-i で、2音節を基本とする日本語の語構成からすれば、pata-kai という複合語(ka は”場所”を意味する「カ(処)」か?)と考えるのが妥当のように思われる。 疑問はあるが、/th/ が *tVk に遡るという説を採用すれば、上の Kor:/th/ ⇔ OJ:/t/ の対応は、すべて/t/⇔/t/ の対応とみなすことができる。 一方、日本語の /s/ は朝鮮語の/č/(= t∫) もしくは/s/に対応しているように見える。
日本語のサ行音の少なくとも一部が、古くは[t∫] のような破擦性を持っていたらしいことについては多くの論拠がある。筆者は、サ行音は[t∫] と摩擦音 [s] が合流したものと考える。上の表の内、水色の欄のものは、同源であることが明確で、朝鮮語からの借用語の可能性が高いと思われるが、/č/s/ が日本語でサ行音に対応するのは、筆者の想定と一致する。 表 III の対応をレギュラーとするなら、表 I -#74「星」の対応、Kor:pyə:r と OJ: posi はイレギュラーと言うしかない。 ゴチャゴチャしてきたので整理すると、以下のようになる。繰り返すが、問題は、このような多重対応をどう処理するかである。比較言語学は理由なき多重対応を認めない。
このような場合における比較言語学の定石は(両言語が共通祖語に遡るという仮定が正しければ)、表に示したように、各対応に応じて異なる音韻を祖語に設定することである。「作り物」という雰囲気をかもし出す為に「祖語」の音韻を敢えて大文字で表記してみた。 両言語が同源関係にない場合には、通常、比較する語彙を増やすと必要とされる祖語の音韻の数も増えてしまって、祖語の復元(比較言語学では再構と呼ぶ)に失敗することになる。 しかし数学や物理と違って、何をもって「成功」あるいは「失敗」とみなすかは、やや主観に依存するところがある。過去に日朝共通祖語の再構を試みた論者(S.マーティンや長田夏樹)はいたが、大方の言語学者の賛同が得られるものではなかった。筆者も、彼らの説は著しく説得力に欠けていると判断する。(長田氏の説はちょっと面白い特徴を備えているので、いずれ機会があれば紹介したい。) そもそも、今まで行われてきた比較言語学では、(筆者の知る限りでは)、わずか2言語の比較から祖語の再構を試みたものはない。2言語比較から祖語を再構しても、その妥当性の検証方法が明確ではないからである。(アメリカンインディアンや南米、あるいはパプアニューギニア諸語ではそういう例があったかもしれない。) 前にも述べたことがあるが、椅子を支えるには支点が3点必要なように、祖語の再構には少なくとも3つの言語が必要である。言語が3つあれば、言語Aと言語Bからの再構形の妥当性を、言語Cで検証することができる。 前稿では、「第3の言語」として、オーストロネシア祖語を持ち出して、日朝両言語の関係に新たな光を当てる事ができるか試みた。それなりに興味ある結果が出てきたとは思うが、多重対応のいくつかは説明不能に終わった。今回は、アルタイ祖語の番である。 アルタイ語族説については、以前に アルタイ仮説の『試金石』 という記事を書いた。本稿執筆の前にかなり修正を加えたが、そこで下した結論、「アルタイ語族説不成立」という筆者の判断は、今でも変わらない。筆者としては、今回の試みは最初から失敗が予想されるので、イマイチ気が乗らなかった。しかし、学説史の紹介が本HPの目的のヒトツである。アルタイ語族説の検討を抜きにした日朝言語の比較は、やはり片手落ちというものだろう。 加えて、筆者は、以下でその一端を紹介する壮大なアルタイ語族説を展開したS.スタロスティンを初めとする、いわゆるモスクワ学派の言語学者たちに、大いなる敬意を抱いている。そして2005年、志し半ばにして急逝してしまったスタロスティンを惜しむ気持ちもある。 日朝両言語の比較に対して、アルタイ語族説が解明の光を投げかけるものであるかという観点から、アルタイ語族説の妥当性を再度検証してみることにした。 以下に挙げる比較例は、モスクワ学派の言語学者たちが公開しているHP、「バベルの塔プロジェクト」に(ほぼ)全面的に依拠したものである。(但し、一部は筆者自身の好みにより変更した箇所がある。) 方針の決定 音韻対応をまとめた表 IV を再掲する。(但しKorとOJの順番を入れ替えた。)
問題は、黄色で示した、「イレギュラーな対応」をアルタイ語族説で説明できるかどうかである。スタロスティンは「できる」とする。左の列に示した「祖語」の音韻は、日朝2言語の対応から仮設されるものである。少し修正する必要があるが、これに対応する音韻体系が、チュルク諸語(トルコ語が所属する語族)、モンゴル諸語、ツングース諸語の比較からも導出される。つまり(マクロ)アルタイ祖語によって日朝両語間のイレギュラーな対応が説明されると、スタロスティンは主張する。 実は、上の音韻対応の一部については、既に上記「アルタイ語族説の『試金石』」という稿で論じた注)。 注) 前稿においては、主要なネタ資料「言語学大辞典」(世界言語編)に従い、チュルク語族に属するChuvash 語をチュヴァシュ語と表記した。今回は、「アルタイ語のはなし」(池田哲朗)に従い、チュワシュ語とした。 例に挙げたのは「石」の対応である。
再説すると、日本語の「石」を isa としたのは、砂子(いさご)= isaNko のように合成語に見られる語形を古形と推定したことによる。アルタイ諸語との比較で、アルタイ: *d > OJ:y は比較的信頼性があると思われる対応である。(アルタイ祖語の語頭子音 /t/- に対して日本祖語 /*d/- が対応する問題については後述する。) チュワシュ語はトルコ語と同じチュルク語族に属する言語だが、なぜかこの言語のみがチュルク諸語の中にあって/š/が/l/になっていて、モンゴル・ツングース語と同じ対応を示す。このチュワシュ語の位置づけを巡ってアルタイ語族説を唱える学者とそれに反対する学者との間で、「比較言語学者の南北戦争」と呼ばれた激しい論争が繰り広げられた。 さて。 ここで注目されるのは、Kor: /r/⇔ OJ: /s/ がアルタイ祖語の /L2/ という音韻に対応していることで、これは、表 IV のR2に対応する。つまり、日朝両言語のイレギュラーな音対応が、アルタイ祖語の音韻/L2/によって説明できる。 学説史からすると、アルタイ祖語の/L2/ という音韻は、トルコ・モンゴル・ツングース諸語間の不規則な音対応(トルコ語のみで [sh] となる)を説明するために設定された音韻で、日朝両言語の比較とは何の関係もない議論から導かれたものである。にも関わらず、もし本当に、アルタイ語族説によって Kor: /r/⇔ OJ: /s/ の対応も説明できるとすれば、それは偶然の産物とは考えにくいので、アルタイ説自身も、日朝両言語の対応も、共に妥当性が補強されて万々歳となるワケである。 前稿「アルタイ仮説の『試金石』」では、アルタイ仮説全般に関わる問題について紹介したが、本稿では、日朝両言語に見られるイレギュラーな対応が、果たしてアルタイ仮説によって「エレガントに」解明されるかに焦点を絞って検討する。 ここで視野を広げて、ストラスティンが設定した音韻対応について紹介しておく。 アルタイ祖語の音韻体系と各言語間との対応はかなり複雑なので、ここでは、本稿に関係する音韻に限定して示す。全体については、英語版 WikipediaのAltaic Languageの項を参照されたい。(下表では一部の発音記号を変更した。また、祖語の表記を大文字のアルファベットで示した。/R2/R/の対応については筆者の暫定試案込みでWikipediaのものと異なる。多分、後に修正する必要あり。)
パッと見で複雑さに圧倒されるかもしれないが、よくよく眺めると、なかなか面白い。本稿に関連して簡単に分ることは、朝鮮語とアルタイ祖語の対応が非常にシンプルなのに対し、日本語はかなり複雑なことである。表 I について述べた想定、日本語(の元になった言語)では古形が保存されたのに対して、朝鮮語では音韻が合流しているのではないかという予想に対応する。(ツングース語もかなり簡素である。) 日本語の 語中の -/t/- に対して、朝鮮語の -/r/-が対応するパターンが4通りもあって複雑である。これは、日朝両語が日朝共通祖語を経由してアルタイ祖語に遡るのではなく、それぞれ独自にアルタイ祖語から分岐したことを示唆する。もし、スタロスティン説が正しければ、日朝共通祖語の再構からは真実は見えない。 それどころか、もしこの音韻対応が正しければ、仮に朝鮮語とツングース語から共通祖語を再構できたとしても、そこからも日本語の語形を導くことはできない。日本語は、音韻構造は単純だが、音韻対応の観点からするとアルタイ祖語(或いはチュルク祖語)まで参照しないと、祖形が見えない構図になっている。(というように、この表を眺めているだけでもなかなか面白いのである。) 更に上の音韻システムで興味を引くのは、有気閉鎖音の系列(上の例では/Th/)が導入されていることである。朝鮮語において、/T/も/D/も語中では -/r/- に変化したことになっているので、語中の/t/は、すべて、/Th/を継承したものという事になる。 表 II において、日本語の /t/ に対して、朝鮮語 /th/ が対応するものがいくつかあったが、これがアルタイ祖語の音韻 /Th/の反映だとすると面白い。しかし、対応表を見て分るように、朝鮮祖語に有気音(激音)は設定されておらず、あくまで後世に現れたものと考えるようである。(ストラスティンも /K/の /h/への弱化から有気音が2次的に生じたと考えるようだ。) 真に近代的なアルタイ語族説は、N.ポッペによって試行されたが、ストラスティンはポッペの音韻システムを拡張して不規則対応の解消を試みるとともに、朝鮮語と日本語を取り込んだマクロアルタイ仮説を推進した。有気音を取り入れたのはその一貫だが、もしかしたら、マクロアルタイ説を更に大拡張したノストラティック超語族も視野に入れてのことかもしれない。筆者もかつてはハマリかけた壮大な仮説だが、到底、筆者の手の届くものではないとあきらめた。 しかし、このようにかなり複雑な音韻システムを祖語を設定しても、イレギュラーな対応が完全に除去されているワケではない。筆者が一番気に食わないのは、アルタイの/T/D/に対して、日本語で /d/t/ が多重対応していることである。上に挙げた「石」の例で、 アルタイ /t/- に対して、日本語 /*d/-が対応するのがその一例である。語頭の/*d/-は文献に現れる形ではヤ行になるので、この違いは大きいにも関わらず、多重対応の条件が定まらないのは大きな欠陥と言わざるを得ない。 さて。 表に見られるように、OJ:/t/r/ と Kor:/t/r/ の対応が複雑なのに比べ、/L2/を継承する OJ:/s/ とKor:/r/ の対応は単純である。そこで、この音韻対応の検討に的を絞るというのが本稿における「趣向」である。 具体的には以下のことを実行する。 1. 語中の日本語:/s/と朝鮮語:/r/が対応すると思われる語を探す。 2. その音韻が、アルタイ諸語あるいはチュルク諸語間の比較を検討して本当に/L2/に対応するか検証する。 要するに、「石」に見られるような「エレガントな」音韻対応例をもっと探し出して、アルタイ祖語の音韻 /L2/の「実在性」(あるいはその有効性)を検証しようということである。 筆者は、「真実はディテールに宿る」と考える。方針が決まれば、あとはひたすら語例を収集するまでである。 個別検討 (アットランダムに気の向くまま10語を選んでみる) どうせ検討するなら、なるべく興味を引く語を選びたい。まずは、今まで散々出てきた、「星」を取り上げる。 1. 「星」 Kor: pyə:r ⇔ OJ: posi (HH; poの甲乙不明。筆者は *po2si ではないかと思う。) まずはチュルク語の語形を見るところからスタート。
L2という音韻は、他のチュルク諸語では[š]=sh なのにチュワシュ語だけが [l] になる事から設定されたものである。なので、チュルク祖語にL2を設定できない! ストラスティンのコメントによれば、L2にDが続くときには、L2はL になってしまう、本来はL2が再構されるとのこと。しかし、L2が実証されないことに変わりはない。 それはともかく、語頭子音が yで p とは全然違うではないかと疑問に思うかもしれない。これについては以下のように論が展開される。モンゴル諸語の比較、
から、*podu を導き(これは、モングオール語の語頭が /f/であることによる)、更にチュルク諸語との比較から *pul-du(n) を想定する(dunは接尾辞)。語中に l があった事は、モンゴル諸語内データからは実証できない。語頭子音の対応、チュルク: /Y/⇔モンゴル/H/ は、アルタイ祖語では /Ph/に遡ると設定されている(下表参照)。
筆者からするとこれは不可思議な対応で、「ホントかいな?」と思ってしまう。この対応の妥当性について調べ始めるとキリがないので、ここでは「ああそうですか」と認めておく。かくして、仮定に仮定を積み重ねて、チュルク・モンゴル語から *PhoL2 らしき語形を再構する。 一方、ツングース語だが、祖形が、*xo:si-kta で、一見、「ホシ」に似ているのだが、ツングース語の /x/ を /p/に対応させる事はできない。 従来、日本語=アルタイ系とする論者は、「星」(posi)を、モンゴル語の xodun や、ツングース語の xo:si と関係付けようと試みてきた。語形としてはツングース語が一番似ている気がするが、/x/を/p/に対応させるのは難しいと筆者も思う。 一方、モングオール語の fo:di も日本語に似ているが、第2子音が合わない。長母音は何かの子音が消えた代償だとすれば、祖形は確かに *poC-di(n) だったと言えるのかもしれない。ここら辺りの議論はモンゴル語に関する深〜い知識が必要で、到底筆者の知識が及ぶところではない。 評価: これまでの記述から分るように、アルタイ祖語が、*PhoL2 のような語形だったとする論拠は限りなく頼りない。ツングース語との対応も付かない。残念ながら、不調なスタートである。 追記 (2010年1月5日): 2007年に、モンゴル祖語は *HoLDu ではなく、 実は/D/自身がアルタイ祖語の /L2/ に対応するという新説が出ていた。スタロスティンのHPに掲載されているが、まだ詳しくは読んでない。これが正しいとすれば、モングオール語の fo:di は、*poL2i のような語形に遡ることになり、少し説得力が増すことになる。(しかし、それだと長母音が現れる理由が説明できない。) 2. 「刺す」 Kor:sar (H) 「矢」 ⇔ OJ: sasu (LL) ⇔ トルコ料理:「シシカバブ」の「シシ」(串)! 岩波古語辞典の「さち」(= 狩りや漁の道具・弓矢や釣り針)の項には「朝鮮語 sal (矢)と同源」とあるが、ストラスティン説では、sal(r) を「刺す」と対応させる。 (1)チュルク語
チュワシュ語が -l- 、その他で š なので、メデタクL2を再構できる。トルクメン語を参考に長母音を立てる必要がある。取り敢えずここまでは順調。 (2)モンゴル語: 残念ながら語中のLは実証できない。 -dun は接尾辞。(というのがストラスティン説だったが、2007年のMudrak 説では、d は L2 に対応する。)
(3)ツングース語: 意味がトルコ語と似すぎているのがかえって怪しい。借用語かも?
評価: アルタイ祖語 *Si:L2a (「刺す」もしくは「歯」) 子音の対応には、文句を付けようがないが、チュルク語の長母音がツングース語や朝鮮語に現れないのは疑問。そもそも朝鮮語の長母音 V: は、V1CV2 > V3: というように、子音の脱落によって生じたものかもしれない。問題は母音がうまく対応しないことである。日本語の sasu を祖語から導くには si:l2a > sa:l2i > sasi (LL) のように、音韻転移を仮定しなければならない(朝鮮語も同じ)。加えて、アルタイ祖語の長母音には高声調(H)が対応して欲しいところだが、低声調である。しかし話しとしては、「シシカバブ」のシシが日本語の「刺す/挿す」と同源というのはなかなか面白い。 3. 「しし」(肉) Kor: sΛr(h) (H) 「肉・肌」 ⇔ OJ: sisi (LL) 「いのしし」「鹿」の古語「かのしし」 それなりに有望な比較と思われ、スタロスティンはアルタイ祖語 šiaL2i (LL)を立てる。しかし、肝心のチュルク語に同源語が発見されない。L2は日朝両語からの再構なので、本稿の趣旨に沿ったL2実証データにはならない。 4. 謗る(そしる) Kor: ha:r (謗る) ⇔ OJ: sosi-ru (HH; 上代語?甲乙不明) (1)チュルク語
L2の再構に問題なし。これも長母音。 (2)モンゴル語: どうも意味が合わない
(3) ツングース語: 語例が少ない
評価: アルタイ祖語 *sio:L2 モンゴル・ツングースの語義対応がイマイチ納得できない。スッキリした比較とは思えないが、一応認めておくとする。しかし、これも母音の説明が難しいと思う。ちなみに、朝鮮語で語頭が h- なのは、*si > hi の変化による。但し、なぜ母音が a なのかの説明が難しい。 5. (日が)射す Kor: sΛr (L; 燃やす。火を起こす) ⇔ OJ: sasu (LL) 岩波古語辞典によれば、「さす」とは「自然現象において活動力・生命力が直線的に発現し作用する意。」で「(日が)射す」「(指で)指す」「(針を)刺す」「閉す」「(注ぎいれる)注す」「(火を点じる)点す」がすべて同源とする。(すべて「さす」と訓まれる。)この解釈が正しければ、この比較は妥当性が欠ける。 (1)チュルク語
(2) モンゴル語は、虹の意味で、ツングースはエヴェンキ語にしか語例(意味は炎)がない。 評価: チュルク語内での、L2再構はできない。モンゴル・ツングース諸語との比較からもL2を想定するのはかなりの無理がある。そもそも上に述べたように日本語の「射す」が「燃える」や「輝く」という語義だったとは筆者には思えない。非常に説得力に乏しい。 6. 枷(かせ)/かし(くい) Kor: kar (H)/ka:r (足枷・首枷) ⇔ OJ: kase/kasi (*L) 足枷・首枷の「かせ」は「かし」(kasi)の転(岩波古語辞典)。「かし」は、元は (1)「舟を繋ぎとめるために水中に立てるくい」で、後に、(2)川岸の船荷を揚げ下ろしする場所の意味に転じ、(3)そこに立つ市場を意味するようになった。時代劇に出て来る「河岸(かし)で一杯やる」などというのは(3)の意味である。 この語源説が正しいとすれば、朝鮮語の「枷」との語義の一致はなくなってしまう・・・ように思えるのだが。 (1)チュルク語: チュワシュ語の語例がないのでチュルク語内の比較からはL2を再構できない。 トルクメン方言が長母音なので、祖語も長母音としなければならないハズだが、そうなっていない。コメントには長母音形は別の単語(帯)からの類推とあるがイマイチ納得できない。日本語の低声調に合わせたのだろうか。
(2)モンゴル語:
(3)ツングース語:
評価: アルタイ祖語 KhiL2a (L) 「枷」 朝鮮語の「枷」の語義に対して、日本語の「枷」(かせ)の語義は「杭」に遡るので、意味が一致しないと判断されるところだが、アルタイ諸語の語義を見渡すと、元は家畜を繋ぐ縄もしくはそれを繋ぐ木を意味したものが枷の意味に転じたように思われる。 それが、島国の日本で「舟を止める杭」に意味が変化したのだとしたら、それは非常に面白いことではある。 しかも日本語において、杭を意味する「カシ」が枷になったのだから、モンゴル語の「止め木」が他言語(チュルク、朝鮮語)で「枷」になってもおかしくないワケである。 チュルク・モンゴル・ツングース諸語からL2を再構するのに(意味の違いはあるが)大きな問題はないように思われる。むしろ問題は、アルタイ祖語の *khil2a > kisa から kasi を導くには#2の「刺す」と同じく音韻転移(メタセシス)を仮定しなければならない事である。音韻転移が日朝両語で共に生じていることからすると、日朝両語は特別な関係にあると見なければならない。 7. 社(やしろ) Kor: tyər (H; 寺) ⇔ OJ: yasi-ro2! (アク不明) これは一見してトンデモ説である!yasi-ro2ではなく、ya-siro2 (屋+代)とする説が「時代別国語大辞典上代編」に載っている。(「神の来臨するとき、祭りに際して神を迎える仮の小屋を設けたが、その屋を設けるための土地(代)がヤシロと称せられた」) さすがに、スタロスティンも朝鮮語のtyər に対応する日本語が、tera < *tiara で仏教伝来と共に伝わった借用語である事には同意すると思うのだが、tyər ⇔yasi をダブレットと解釈するのだろうか?チュルク・モンゴル語では、この語幹は「隠れた」「秘密の」という意味だが、日朝両語にこのような意味があるとはとても思えない。 アルタイ諸語から *Da(?)L2a (隠す)を再構して日本語の yasiro2と比較する説は、元々、R.A.ミラーが唱えたものだが、村山により批判されている。 8. 升 Kor: mar (H; 升 18Kg) ⇔ OJ: masu (LL;上代語になし) 残念ながらチュルク語にはこの語形がない。 モンゴル語では、モンゴル文語に malu (容器、籠)、カルムック方言に mal があるのみで語形の広がりがない。ツングース語では、満州文語に、mali/malin (量る/目方)、ナーナイ語に mialaqo (粉の計量)があるが、やはり語例が少ない。 筆者が思うに、朝鮮語の mar は、後世におけるモンゴルもしくはツングース語からの借用語で、日本語の masu は同源ではないと思われる。古代日本語における文化語はみんな朝鮮語から持ってきたものだろうという思い込みからすると、mar とmasu を同源としたくなる気持ちは分るが証明は難しいと思う。 9.走る Kor: pΛrb (踏む、足跡を付ける) ⇔ OJ: pasu (LL) (1)チュルク語:
(2)モンゴル語: この語では語中のLが生きている。
(3)ツングース語:
評価: アルタイ祖語 PheL2o (歩く、走る) 語頭子音の出現パターンからすると、アルタイ祖語の /Ph/になるハズというのだが、ハラジ語の語形が分らないのでチュルク語内部で/*p/を再構することができない。(ハラジ語の語頭に h− があれば、 *p- が推定される。)チュワシュ語の第2子音からはL2を再構できないので、各語に意味の繋がりがあることは認めるが、信頼性に欠ける。
これに関連して、Kor: par (H;足)と pasu が比較されることがある。スタロスティン説では、par はツングース祖語の *palga(n) (足、足の裏)と同源で、日本語の pagi (脛)と対応させる。しかし、朝鮮語 pΛrb (踏む、足跡を付ける)の語尾 -b が接尾辞だとしたら、この語は par (足)の派生語かもしれない。 一方、日本語の「走る」は、「ヒトツの方向に勢いよく飛び出す」の意で、かならずしも「走る」「歩く」の意味ではない。朝鮮語の pal とツングース語の語形・語義の顕著な類似に比べると、日本語の pasu は語形・語義とも遠いように思われる。脛 (pagi < *pa'agi RH) は確かにツングース起源かもしれない。 10.競ふ Kor: kyəru (現代語のみ; 競う) ⇔ MJ: kisopu (上代語になし) アルタイ祖語: GaL2i を立てるが、チュルク語の語形がないのでL2の根拠は上の日朝両語の比較のみ。しかもそれが古い文献には現れないとなると、全く信頼性に欠けると言わざるを得ない。トルコ語辞典に košu(競争)という語があるのだが、これではダメなのだろうか?(分らんなー。) ↑ 10語でいったん中断と思っていたが、あまりにヒドイので追加することにした。 11. 重さぬ Kor: kΛrp (L; ペア、並ぶ、倍) ⇔ OJ: kasa-nu (HH) (1)チュルク語: チュワシュ語の対応がおかしい。L2の再構はできない。
2)モンゴル語:
(3)ツングース語:
評価: アルタイ祖語 KhoL2ba (ペア、結び付ける) 朝鮮語の語形は確かに、モンゴル・ツングースと関係がありそうだが、*kaL2p のような語形が日本語で kapu とならずに、kas- で現れるというのはガテンが行かない。ということは置くとしても、チュルク語とモンゴル・ツングース語の語形の違いが分らない(チュルク語に -b がない)のと、やはりチュワシュ語からL2が導けないのが痛い。いっそ、チュルク語抜きにして、日本語の kurabu と比べた方が見込みがありそうな気がする。 分析と暫定結論 (09年12月27日時点) けっこう骨の折れる作業である。スタロスティンの説を鵜呑みにするのはイヤなので、一応、トルコ語・古代トルコ語・ツングース比較辞典・韓国語辞書などを調べて確認するので時間が掛かる。(もっとも確認をサボった語もけっこうある。ストラスティンの挙げる語形が発見できないこともしばしである。) 最初の「石」を含めて12例を検討した。検証結果をまとめる。
/L2/という音韻は、チュルク諸語内において、チュワシュ語とその他の諸語との対応から導かれる。/L2/がチュワシュ語との比較で実証されるから、例えば、šiš (串)というトルコ語を、エヴェンキ語のsila-wun (焼き串)に対応させる事ができるというのがアルタイ比較言語学の「正式手順」である。 アルタイ仮説を「信じる」立場からすると、たとえチュワシュ語を参照できなくとも、トルコ語で /š/、モンゴル・ツングース語で /l/に対応する語が見つかれば、/L2/を再構することに問題はないのだろうが、音韻法則を厳密に適用すれば、上記の比較例12語のうち、9語については/L2/を再構できないので、比較の妥当性は毀損されていると言うべきである。 日本語 /s/ と朝鮮語 /r/ の比較に照らして喩えると以下のようなことである。もし日本語に朝鮮語と同じく /r/で対応する方言があったとしたら、あるいは逆に、朝鮮語に日本語と同じく /s/ で対応する方言があったとしたら、この音対応(OJ: /s/⇔Kor: /r/)は著しく説得力を増すハズである。ところが、そういう都合の良い方言はないので、この対応に疑問が持たれるワケである。チュワシュ語を参照できないという事は、比較の要となる語形が発見できないということである。 問題なく/L2/が再構できるものは3語あるが、#2の「刺す」は、母音の対応が苦しい。「シシカバブ」の「シシ」(串)と「刺す」が同源なら面白いと思うが、音韻転移を仮定しないといけない。#4の「謗る」にしても、各語の意味対応が説得力に欠ける。そもそも、#5、#7のように強引な比較が他でも目に付く。 結局のところ、まともな比較は「石」の1語だけになってしまう。この例にしても、isi < *yisa < *disa というかなり強引な音変化の仮定に基づいている。 本稿の目的は、Kor: -/r/- ⇔ OJ:-/s/- の対応をアルタイ語族説から説明できるか検討することだったが、上の語例を見る限り、「エレガント」かつ「クリアー」な説明は得られそうもない。(残念!) 以上の結果から、暫定的に、Kor: -/r/- と OJ:-/s/- の対応は不正規で、両言語との同源関係を証明するには使えないと結論しておく。と同時に、(マクロ)アルタイ語族仮説の脆弱性があらためて示されたものと考える。 一方、上の表で緑色で示したが、ツングース語と朝鮮語の類似はかなり顕著なのではないかと思う。しかしその類似を安易に日本語に延長できないというのが本稿の結論である。 次回の予定 現在、A. Vovin の "Koreo-Japonica A Re-evaluation of a Common Genetic Origin" を読んでいるが、なかなか進まない。もう少し、アルタイ説を検討して遊んでみようかという気もしている。アルタイ説を信じるか否かは別として、この説を検討することで日朝両語の関係が浮き彫りになりそうな気がしている。 日本語と朝鮮語の関係を論じる前に、朝鮮語の激音の起源がアルタイ仮説の観点からどう説明されるか考えてみたい。 追記(009/12/29) 上記著書のA. Vovin がS. Starostinのアルタイ語源辞典(Etymological Dictionary of Altaic Language)をケチョンケチョンに批判した論文に対して、Starostinの同僚が反論を加えた論文がWebに掲載されている。モスクワ学派の骨肉の争いである。現在、読み返しているところだが、これがなかなか面白い。次回はこれをネタにしようと思う。 語例の追加と結論 (2010/01/03) 上表に3語追加した。 追記 (2010年1月5日): 2007年に、モンゴル祖語は *HoLDu ではなく、 実は/D/自身がアルタイ祖語の /L2/ に対応するという新説が出ていた。スタロスティンのHPに掲載されている。これに合わせて「星」のモンゴル祖語の箇所を変更した。但し、チュルク語でL2が検証されない問題は変わらない。
以下にはチュルク語の比較を中心にメモを記しておく 12. 「襲う」: 語義に問題あり。朝鮮語がない! 現代トルコ語の ešik は、「敷居」・「入り口」の意味で、「覆い」の意味を持つのは、Karakhanid方言のみというのが弱い!
13.「勇む」: これまたチュワシュ語にL2が確認できない
14.「他所」: Kor: tarΛ-da (LH) 違った ⇔ OJ: *do2so2 > yo2so2 (HL) 「他所」(よそ)は、「かけ離れていて容易に近寄り難い場所、またはそのような関係の意」(岩波古語辞典)で、朝鮮語の「違った」とはさほど意味は離れていないと思う。
ここで行き詰まった。 チュルクとモンゴルもしくはツングースのペア、及び日朝のペアでともにL2が確認できそうな語彙はさほど多くない。この他にも気になる語がいくつかあったが、あまりに意味が異なったりしていて真面目に検討する気にならなかった。 音対応の妥当性を検討するには、サンプルとしてはこれで十分だと思う。結局、筆者がそれなりに説得力があると考える比較は、以下の3例である。
これをもって、なにかが証明されたと主張するのはムリだと筆者は考える。もっと語例を稼ごうとした場合に引っ掛かるのが以下の5例である。 A.Vovinの批判とG.スタロスティンの反論と筆者の見解 検討した語のうち、#5〜13の4語は、下表にまとめたように「チュワシュ語の対応が不正規」という問題があった。/L2/は、チュワシュ語で /l/ 、トルコ語を始めとするその他のチュルク語では全て/š/であるハズなのに、チュワシュ語でも /š/になってしまっているという問題である。 最後の#6は単にチュワシュ語の語形がないために/L2/がチュルク語内で実証されない。(非常に興味深い比較ではあると思う。) もしこの5例で/L2/が確認されていれば、筆者としては、専門家がどう言おうが、アルタイ仮説の信憑性のグレードを大幅にUPしたいところだ。(「確信」にはまだ遠いところだが。)
A.VovinのEDAL批判の論点は多岐に渡るが、そのうちのヒトツは、私が上に挙げたものと実質的に同じである。 Vovinの批判に答えて、反論したのがG.スタロスティン(S.スタロスティンの親族?)である。その全文 "In Defense of the Comparative Method, or The End of the Vovin Controversy" (「比較言語学の手法を弁護して、もしくはVovin論争の終わり」)をスタロスティンのHPで読むことができるが、ここでは上の論点に絞って紹介する。(論文のp.33辺りの記述。) 要するに、/L2/がチュワシュ語で /l/で現れるのは、/L2/が語末にあるか、もしくは子音が後続する場合に限られており、母音に挟まれた場合は、/š/になるのが正規対応なので問題ないというものである。上の語例は、いずれも動詞の語幹で、実際の語形においては母音が続くために/š/になっているのだとする。 なんでも、EDALの編者の一人 O. Mudrak の博士論文で扱われた対応らしい。(Vovinはロシア国内でしか見られない論文を引用してお茶を濁すのはケシカランとイチャモンを付けている。) 以下はそれに対する筆者の見解である。 そもそも、/L2/や/R2/という音韻が実在したことを示す直接的な証拠は、8〜9世紀にハンガリー語に借用されたボルガル語(チュワシュ語の前身とされる)と、チュルク諸語、モンゴル・ツングース諸語との比較だった。(この話題については、以前に書いた「アルタイ語族説の『試金石』」参照のこと。) 前稿に挙げた比較表をチュワシュ語、チュルク祖語を加えて再掲する。
上の語例を見ると、/L2/の対応を示す語例#6,7において、/L2/はまさに母音に挟まれている。しかもハンガリー(ボルガル)語で、[ly]となっている。この事実こそが、/L2/の実際の音価が、[ly]であると推定する根拠となっている。(この議論は、/R2/においても当てはまる。) もし、O. Mudrak らの主張するように、ボルガル(チュワシュ)語において、/L2/が母音間で [š] になったとするなら、それを借用したハンガリー語でも、[sh]に類似した音が出て来ないといけないハズである。従って、Mudrak 説は誤りとしか考えられない。 当然ながら、筆者はO. Mudrak氏の博士論文を読んでない。読んでないが、いやしくもアルタイ諸語の専門家が、筆者のような素人でも考える事を考慮していないハズはなかろうと思う。しかしこの問題をどう処理して良いのか筆者にはサッパリ分らない。(いっそ、メールを出して問い合わせてみようかと思っている。) 結論 (2010/01/03) おりしも、NHK特集の再放送「日本と朝鮮半島2000年」を教育チャンネルでやっていて、横目でTVを見ながらの執筆である。NHK総合の方では、さっきまで元SPEEDの上原多香子がトルコで本場のベリーダンスに挑戦という、けっこう色っぽい番組をやっていた。(こちらも時々見てたw) 今は、「蒙古襲来の衝撃」をやっているところである。トルコからモンゴル、朝鮮半島、日本まで、なんというアルタイ繋がりだろうか。アマノウズメが天の岩戸の前でベリーダンスを踊っている情景が浮かんできたり、モンゴルに朝鮮半島が占領されている間に朝鮮語に入ったモンゴル語がどれだけあるのか、ちゃんと調べは付いているのだろかなどと思ったりした。 確かに、内陸ユーラシアと日本との繋がりにはロマンがある。しかし、それはそれ、これはこれである。 未練は感じるが、アルタイ祖語の音韻/L2/を根拠に Kor: -/r/- と OJ:-/s/-の対応を説明するのはムリというのが筆者の結論である。 少なくとも、「星」や「匙」のような語彙に関しては、前稿で述べたようにオーストロネシア祖語(正確にはマラヨ・ポリネシア祖語 PMP)から、 PMP: *bintu'qen (star) 日本語: > pintə' > *pə'nti > *pə'si (泉井則) > po2si (HL) 朝鮮語: > *pidə' > pirə' (r 音化) >piə'r (breaking) > pyə'r PMP: *sendu'k と *su'(n)du (ともに spoon/ひしゃくの意味) 日本語: *sendu'k > *sazu' (泉井則) > sazi (LH) 朝鮮語: *su'(n)du > *su'ru (r 音化) > sur (H) という具合に、MKor: r ⇔ OJ: s/z の「対応」が生じたとする方が、語義・音対応の観点からは理にかなっているように思われる。朝鮮語で、ある時期に *d > r の変化が起きたのは十分有り得る。上で見たように、日朝の「星」の起源がアルタイ系だとは筆者には思えない。 (注: オーストロネシア祖語の母音は /a/i/u/ə/ の4母音システムに再構されており、/ə/は米国式では /e/ と表記される。) 但し、言語の起源・系統を問題にするなら、マラヨ・ポリネシア祖語(PMP)の成立はせいぜいBC2500年くらいなので、上記の2語はPMPからの借用語とみなされべきと考える。(日朝両言語がPMPから派生して生じたという考えは、分岐年代が新しすぎて有り得ないと確言できる。) 再び次回の予定 (2010/01/03) 長々と論じた割りに結論が乏しいのはいつものことである。 日本から一気にトルコまで射程を伸ばしたのはいささか欲張り過ぎだったかもしれない。 もうしばらくアルタイ説を検討する。 次回のネタは考え中。 更新記録 2009/12/27 初稿:久しぶりの新規更新。 2009/12/28 修正。日朝再構形を立てたのは、R.ミラーでなく、S.マーティン。 2010/01/03 大幅に追加。 2010/01/05 少し修正(「星」のモンゴル祖語に関する記述)。 2010/01/11 少し修正&追記 2010/01/18 「勇む」を「いそし」に変えた代案をを追加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||