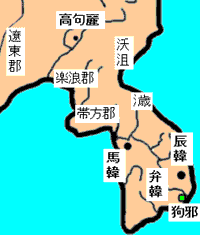1ページ目はこちら 「男」、「女」、「人」とその派生語の語源 説明の都合で、「人」から論じることにします。 #18 「人」 その1 「ヒト」(pito2)については、私も村山説に従い、 pi-to2と分解し、*to2 がオリジナルの「人」の意味と考えます。 pito2(HL)は、「彦」/piko(HL?)/「姫」pime(HL)/ と同じ構成の語と思われます(括弧内はアクセントの高低)。これら3つの語に共通する前接辞の pi(H) は後述するように一種の尊称で、「日」(pii:HL)だと思われます。「火」は乙類 pi2 で音は違うし、アクセントがLLなので異なる語です注)。 注) 「日」 pi (HL)の語源について: 「日」については、「火」といっしょに、後で取り上げる予定なのですが、”Fire”は基礎語彙番号が#82なので、登場するのはズーッと後になります。結論だけ先に言っておくと、pi 「日」は、恐らく 昼(piru :HL)と同源です。オホヒルメムチ(天照大神の別名)に現れる ヒルメ (piru-me) は、「ヒメ」の異形で、こちらが古形を保存していると考えるのが妥当でしょう。 piru は、おそらく中期韓国語の pïr「火」と同源で、更に、アルタイ諸語で「火」もしくは「赤」を意味する *pul と同源と考えられます。「火」の項でも検討しますが、「日」はアルタイ系、「火」はAN系です。 pikoは piku に遡り、実際に尊称だった事は、「魏志倭人伝」の「官名」や「王名」の一部に、卑狗 (piku) , 狗古智卑狗(kukotsi-piku) などが見られることから推定されます。(参考ページ: 「卑弥呼の謎」) おそらく、「ヒト」は「日を祭る者(達)」という原義だったと思われます。自分達の属する、祭祀を共にする部族集団を他の部族集団から区別する、エンブレム的な語だったのではないかと推測します。ヤマト勢力に服従しない勢力は「マツロハヌ」者と呼ばれたワケですが、これは「日を祭らない人々」という意味だったのでしょう。 私は、九州におけるヤマトの敵対勢力である「熊襲」も、kuma-tso2 と分解され(so2は、正確には tso2 と発音されていたと推定されます)、tso2は古代近畿方言の to2 と同源の「人」を表す語だったと推測します。実は、tso2の方が、AN祖語の推定音 *Cau に近いのです。台湾原住民のツォウ族の「ツァウ」も「人」の意味です。 また、九州には「隼人」(ハヤト)と呼ばれる人々がいて、ヤマト勢力と対向していたのが後に服属したとされます。 彼らは、「クマ」や「ハヤ」を祭る種族だった可能性があります。私は「クマ」と「ハヤ」もAN語で解けると考えるのですが、ここではこれ以上この問題に立ち入る事はやめておきます。 チョット脱線: 更に、(これは村山も指摘している事ですが)魏志辰韓伝に、この地域の言語は、「亡命してきた中国人の言語の影響のために馬韓と異なっている」とあり、その例として 「自分の事を『阿』と言い、互いに呼び合う時は『徒』という」 等が挙げられています。これは、「我」=a 、「徒」=do/to という事で、古代日本語の「我」=a 、「人」=to2 と似ていて、興味を惹きます。
周知のことだと思いますが、一応、魏志時代の地域区分を示しておきます。 もしも上に挙げた語が本当にAN語と関係があるのなら、プロト韓国語にもAN語が混合していた事の証拠になります。 しかし、金芳漢の「韓国語の系統」では、辰韓の言語は他の領域と比べ大きな言語差はなかったものとし、河野六郎の説を継承して、上の「阿」や「徒」などを原文通りに戦乱を逃れてきた中国人から借用された中国語だろうと解釈しています。 とは言っても、中国の郡制が敷かれた楽浪・帯方郡があった地域よりも南韓のほうが中国語の影響を強く受けたというのはイマヒトツ納得しがたいところがあります。 2〜3世紀における朝鮮半島の言語がどのようなものだったかは難しい問題なのですが、弁韓地域で古代日本語と類似した言語が話されていたかどうかについては、ほぼ否定できると思います。 魏志に挙げられている弁韓12ケ国の内、3つの国名が「凍」で終わっているのですが、これの中古音は tung で語末子音 -ng を有しています。このような子音終わりの漢字音は、倭国の地名にはほとんど使用されていません注)。弁韓の言語の音韻体系は日本語のような母音終わりのものではなく、後世の韓国語に近いものだったと推定されます。 注) 倭国の国名がほとんど母音終わりの漢字で表記されていることは、森博達氏の「三世紀倭人語の音韻」( 「倭人伝を読む」 中央公論社 中公新書 1982年)で論じられています。 そもそも「なぜ韓国語と日本語は似て非なるものなのか?」、これは非常に難しい問題です。私は最初、日本語と韓国語の違いは、アルタイ系言語とAN系言語の混合率の差によって生じたのだろうと考えていたのですが、そんな簡単な問題ではなさそうです。韓国語の系統問題は、日本語よりも、もっと難しそうな気がします。このHPで韓国語と日本語の関係を(今のところは)ほとんど取り上げないのは、この理由によります。 まずは最も見込みのありそうな日本語とAN語の関係を徹底的に洗っておいて、それから日本語と韓国語の比較を検討するのが順番ではないかと思います。系統が不明な言語を別の系統が不明な言語と比較しても、得られるものは少ないと考えます。 とは言っても上の「日」のように、論証の補強になると考えられる場合、「吾」や「徒」のように興味を惹く事例がある場合には、適時、韓国語との比較を取り上げることにします。 日本語とAN語の比較に話しを戻します。 #18 「人」 その2 古代日本語に「人」を表わす語として、「ヒト」の他に wo があったことが、 「女」= wo-mina 「翁」= wo-kina 「叔母」= wo-ba 「叔父」= wo-di と性別に関係なく wo が使われている事から推定されます。「ヲ」(wo) は、上代日本語では「牡・雄」の意味ですが、上の一連の語は、「ヲ」が元は「ヒト」の意味だった事を示唆します。 注) 村山はこの他、wotome/wotoko からも「人」=wo が抽出できるとしていますが、これは多分誤りと思われます。wotome/wotokoは、woto+(me/ko)と分解され、wotoは「若くなる」wotu という動詞の語幹と考えられます。 一方、オーストロネシア祖語にも、*tau とは別の「ヒト」を意味する語、 *uRang がありました(表記はCANDによる)。この語は、インドネシア語では規則的な音韻変化で orang に変化しました。「オラン・ウータン」がインドネシア語で「森の人」の意味である事は良く知られています。 *uRang における、Rと再構される音韻は、インドネシア語では r に変化しましたが、日本語では、語中では消失、語頭では yに変化したと考えられます。このRという音は、オーストロネシア比較言語学において論議が多い難しい音韻で、他の言語でも複雑な音韻対応を示します。フランス語の「ルージュ」(rouge)の r のような音(喉の奥で発せられる、うがいの時に出るような音)ではないかと推測されています。 R音が日本語で消失したとすると、 *uRang (人)は、 uRang > uang > wo (ua → o は規則変化) となり、日本語の wo に規則的に対応します。 これとほとんど同じような音韻変化をしたと思われる語としては、 根・起源・血管・筋: *uRat > ua > wo: (緒 HH) があります。(Rはタガログ語では g に変化し、根・起源・血管: uga't という語になりました。) これに対応する語彙を、私はフィリピンの言語に見つける事ができませんでした。フィリピン諸語では、2−3語源が不明な語形がありますが、「人」を意味する語は、すべて tau 系の語形を有しています。 日本語には、「人」を表すAN語が2種類、取り込まれたことになります。これは一体どうしたことなのでしょうか?この問題については、以下に述べる検討も踏まえて後ほど考察する事にします。 #16 「女」 「女」を意味するAN語には、 1. *baHi 2. *ba-baHi 3. *binay がありました。(Hは台湾語から再構される音で、フィリピンやインドネシア諸語では消えてしまったので、以下の説明では適時省略して表記します。) 上の語の内、*baHi が基本形で、2はその部分重複形です。「部分重複」はAN語における有力な派生語形成法です。 デンプウォルフは binay と再構したのですが、その後の研究で、binay は、基本形 baHi からの派生語である事が判明しています。 AN祖語は、接辞を使った派生語の形成が極めて生産的な言語で、前接辞・後接辞のほかに、接中辞なるものがありました。binayは bai に接中辞-in- が付いて、 bai > b-in-ai > binay という語形変化で生じました。興味深いことに、上の各語形のそれぞれに対応する日本語が見付かります。 3. binay の対応語 上に述べたように、オーストロネシア諸語では、「オラン・ウータン」(人・森)と、基本的には「名詞」+「修飾語」という語順を取ります。 「女」= wo-mina = 「人」+「女」 は、これと同じ構成になっており、後世の日本語と比べると語の構成法が異なっています。そういう意味で、この語は「プロト・日本祖語」にも遡る、非常に古い形を留めているものと考えられます。 この語は現在「オンナ」という形に変化して、現代語に生き残っています。「縄文語」という「キャッチフレーズ」をところどころでみかけますが、私は、「縄文時代から現在まで連綿と受け継がれてきた事が、最も確からしいと推定される語」は「オンナ」だと考えます。多分、その寿命は2500年を超えます。やはり「オンナは強い!」のです。 わき道: 「ヲグナ」「ヲノコ」「ヲキナ」の語構成について この推測を確認するには、mina の語源がAN語で「女」である事を示す必要があるのですが、その前に、似た語構成を有する、 「男子」= wo-guna < *wo-n-kuna 「男」= wo-no2-ko の解析を行っておきます。 woguna < *wo-n-kuna ですが、これから抽出される kuna は、村山説ではツングース祖語の「子供」*kunga に遡ります。間の -n- や、「ヲノコ」の no2 は、タガログ語の「リンカー」と呼ばれる文法要素 ng/na 、 Hapones na doktor 日本人の医者 Honda-ng kotse ホンダの車 (ここはトヨタでも良いのですが・・・) と同源と考えられます。即ち、woguna (男の子)は、 AN語(人 > 男)+AN語(〜の)+ ツングース語(子供) という構成であることになります。オリジナルのAN祖語: wo 「人」が「男・雄」に意味変化していて、語順が、「修飾語」+「名詞」になっています。従ってこの語は「オンナ」よりも新しい段階の語形と考えられます。 古事記では「ヲグナ」はヤマトタケルのミコトを描写する「ヤマトヲグナ」というように使われています。この語は後世、「ヲキナ」(翁: wokina)と老人を表す語に変化しました。「男子」を意味する語として「ヲノコ」「ヲトコ」が勢力を拡大したために、「ヲグナ」(woguna)は、wokina に姿を変えてしばらくは生き残ったのですが、現代日本語では死語になってしまいました。今では能・狂言という限られた世界でほそぼそと生きているだけです。 また脱線: 新しい語が優勢になると、元からあった語が意味を変えて生き残るというのは言語の世界では良くあることです。英語の deer (鹿) は、ドイツ語の Tier (動物)と同源で、元々は動物一般を意味したのですが、フランスからやってきた animal にその地位を追われ、鹿に意味を変える事によって生き残りに成功したのです。 再び 「女」= wo-mina について 「ヲミナ」は、「ヲグナ」と同じく、*wo-n-mina に遡ると考えられます。 AN祖語で「女」を意味する語のヒトツは、*binay でしたがこれは、上の*minaと比較されます。 「蛇」 hebi が hemi 「蝦夷」 emisi がebisu と通音もしくは語形変化したことを考えると、前接する 「リンカー: n」 の影響によって、 *wo-n-bina > *wo-n-mina > womina となるのは自然な音韻変化です。 「女」を意味する語の古形として、*mina があり、これからnが消失した語形、 mina > minya > mia > me (ia > e は規則的音韻変化: ki-ari > keri など) から、「女」: me < *mia が生じたものと考えられます。ちなみに東国方言では、「女」はmi でした。もしかしたらこちらの方が古形を保存している可能性もあります。 日本語には「女性名詞」や「男性名詞」の区別はありませんが、「ミナ」という音にはいかにも「女性」という響きがあります。(と思うのは私だけか?) ここで、またしても脱線: 「ヒナ祭り」はなぜ女の子の祭りか? 以下は私の「空想」です。 AN祖語起源の*binai という語が単独で現れるとすれば、日本語では *pina になるハズです(語尾の i の脱落現象については後述)。もしかしたら「雛」の語源は、「女の子」なのではないだろうかと考えます。そこで連想されるのは「ひな祭り」です。なぜ「ひな祭り」は「女の子の祭り」なのでしょうか? 「ひな祭り」の起源は平安時代にさかのぼり、小さな男女の人形を持って遊ぶ「ひひなあそび」と、紙で人型を作り、身の汚れをそれに移して海や川に流す儀式が結びついて雛祭りとなった、というのが通説とされています。 現在でも和歌山県や鳥取県に「ひな流し」の風習が残っているそうです。これからすると「ひな」は明らかに呪具です。現代日本語で 「ひな型」というと、「縮小モデル」というような意味に用いられていますが、「ひな」は、「女の子」=「女の縮小形」という意味だったのではないでしょうか。 素人の気楽さで更に想像を膨らませる事にします。「女を象った人型(縮小モデル)を作って異界に送り込む」という儀式がひな祭りの原型であるとすると、これから連想されるのは、縄文時代の土偶祭儀です。それは、女性(地母神)を象った土偶を破壊して土に埋め、豊穣を予祝・祈願する儀礼だったとされます。土偶は地母神の「ひな型」「縮小モデル」だったのではないでしょうか? 「母」と「父」の語源 「空想」はそれくらいにして話しを戻します。 AN祖語で「女性」を表わす語に、重複形に基づく *babaHi があります。タガログ語の babai (「女」、「女の子」)はこれを引き継いだものです。 日本語の「ハハ」(母)は、*papa > baba に遡ると考えられます。(「パパ」は古代では母だった!)これは、AN祖語に対して語尾の i が消失した語形と解釈されます注)。 注) 語尾 i の脱落現象について: 詳しい説明はここでは省略しますが、語尾の i が脱落する形の母音交替形が語幹を表示し、i が付くと形容詞や動詞が名詞化されるという形態法が古代日本語にあった事は、例えば、take2 < takai (名詞:岳・丈)とtaka (形容詞:高しの語幹)の関係や、動詞の活用における母音交替現象などから実証されます。babai は厳密な音韻対応では babe2 になるハズなのですが、それが baba > papa と現れるのは、 babe2 が語幹としてはおかしな形(このままだと形容詞・動詞の名詞化形)であるという、reanalysis (再分析)によるものと思われます。このような解釈ではツジツマの合わない語もあるのですが、取り敢えずこのように解釈しておきます。 更に厳密な議論をすると、正確には、AN祖語の *babaHi は、 *babaHi > babai (タガログ語と同じ) > paba と、第二子音は p ではなく、 b でないとリクツに合いません。古代日本語においては第一子音は無声音(清音)でないといけませんでしたが、第二子音にはそのような制約はありませんでした。(もっとも第二子音の b/p が古代日本語で語の弁別要素だったかは疑問がある所なのですが。) 参考になると思われる語形変化が安土・桃山時代に生じたと考えられます。 「母」は上代から室町時代末期までに papa > FaFa > Fawa と変化しました。(Fawaは、16世紀のキリシタン文献 faua から実証されます。)これは、語頭ではFが保存され、語中ではFがwに変化したという音韻変化に忠実な語形です。(参考: 「皮」 kapa > kawa ) しかし、「母」は 「父」・「母」=/titi/ ・ /Fawa/ と「父」とペアで使われる事が多かったために、「父」という重複形につられて w が再び Fに変音し、Fawa > FaFa という歴史に逆行する変化が起きました。やがてFはhに変化したので、現代語で「母」は /haha/ と発音されるのですが、厳密な音韻変化則が適用されたとすると、「母」は本当は /hawa/ でないとおかしいのです。 記録に残らない有史以前の段階で、「母」が /paba/ であった可能性はあるにせよ、ある時点で、上と類似した変化によって、「母」は /papa/ になったものと考えられます。 wo-ba (叔母)も wo+n+p/ba と分解され、ここから抽出される *ba は、女性を表わすAN祖語の基本形 *baHi に対応します。 叔母が出てきたので叔父についても述べておきます。 叔母 wo-ba 叔父 wo-di < wo-n-ti で対をなし、語構成としてはAN語的なので、叔父から抽出される ti/di もAN語起源と考えられます。di/ti の重複形が 「父」(titi) だと思われます。これも「空想」ですが、di は、AN祖語の 支配者: ha(n)di > andi と関係があり、更に、古琉球語で「王」を表す 按司 (anzi)の語源ではないかと考えます。あるいは 氏 (udi)との関係も考えられます。 関連する語のアクセントを比べてみました。
父の語頭はL声調なので、「父」が「血」と同源とする吉田氏の説は苦しいでしょう。(そもそも母音も合わない!)吉田氏の語源説は、私が見るところ「これで学者なの?!」と思わせるものが、非常に多い。 ウジ(氏)のジもL声調なのですが第二シラブルの声調が古形を反映されている保障は全くないので、これ以上突っ込んだ議論は難しいです。残念ながら「父」の語源は不明です。 結論 #16 「女」 というワケで、古代日本語の 1. 叔母 wo-ba 2. 母 papa/paba(?) 3. 女 wo-mina 3’ ひな? pina (実証困難) はそれぞれ、AN祖語の 1. *baHi 2. *ba-baHi 3. *binay に対応します。 #17 「男」 今回取り上げる最後の単語は「男」です。日本語では wo=「人」は、上に挙げた「女」「翁」という合成語に痕跡的に残り、「男」「雄」「牡」を意味する語になりました。「人」と「男」を表わす語が同じ語であることは他の言語でも良くあることです。 一方、オーストロネシア祖語には、「男」を意味する *laki がありました。 日本語の語頭にはラ行音は立たず、AN語の語頭音 *l は、tに音韻変化したと考えられます。 例 (*l > t の音韻変化) 外: lau > to2 ( au > o2 は規則変化) 戸: lua > to (ua > o は規則変化) 飛ぶ: l 絶える: layu > tayu 従って、*laki は、日本語で taki になるハズで、これは「健」「武」(take)に対応すると考えられます。AN語でも不完全重複による並行的な意味変化 laki (男)> lalaki (強い)があり、この推定を支持します。 日本神話におけるアダムとイヴである「イザナキ」「イザナミ」は恐らく、 iza-naki < itsa-n-naki < isa-n-taki < isa-n-laki iza-nami < itsa-no2-mi < isa-no2-mi に遡り、itsa はAN祖語の「一」= isa に対応し、 「イザナキ」=「一」「の」「男」= 「最初の男」 「イザナミ」=「一」「の」「女」= 「最初の女」 というオーストオロネシア祖語に遡る注)事は、村山、川本両氏が主張するところです。(語形変化は私の解釈によるものですが、他に色々なヴァリエーションが考えられます。) 注) 語順ですが、例えばタガログ語の場合、形容詞は普通、名詞の後に来るのですが、数詞・序数詞は、名詞の前に来ます。 従って「イザナギ・イザナミ国産み神話」はオーストロネシア起源と考えられるワケですが、実際、この神話に現れる各種のモチーフがメラネシア・ポリネシア諸島に伝わる創世神話と類似している事は、古くから神話学者の指摘するところです。 「スメラキ」は「スメラ」+「キ」か? 日本語では語頭にラ行音が来ないので、*laki は単独形では take (猛)に姿を変えざるを得なかったワケですが、合成語には *laki が現れる可能性があります。 諸祖・天神(常陸国風土記)あるいは天皇を意味する スメラキ sumera(o2)ki スメラミ sumera(o2)mi は男女一対の表現です。「スメラミ」の「ミ」は明らかに「女」の意味なので、国語学者は、「スメラ」+「ミ」と分解して、「スメラ」という語が抽出できると考えてきたワケですが、「スメ・カミ(神)」「スメ・ミマ(御孫)」「スメ・ムツ(睦)」という語があることからすれば、「スメ」を抽出するのが妥当と考えられます。 「スメ」(sume)の語源に関する考えは下の注に述べる通りですが、これがアルタイ系なのかAN系なのかは今のところ不明です注)。 注) sume の語源について: sume は、動詞「統ぶ」(subu)から、b〜m の音韻交替で生じたのではないかと考えます。 しかし「統ぶ」は下二段活用なので、sume はsume2 でないとツジツマが合いません。前ページで触れた me2 (目)から mi-ru (見る)が形成されたと同じ音韻変化が起きて sube2 > subi > sumi > sume と変化したとも考え得るのですが、ちょっとコジツケかもしれません。本来e2 であるべき表記が e1 になっている変則例は、sime2-su (示す) kape1-ru (返る)があります。どういう条件下でこのような変則変化が起きるのか不明なのですが、sube2 > sume2 > sume1 は有り得ない対応ではなさそうです。 もし「スメラキ」が「スメ」+「ラキ」と分解できるのであれば、 sume+raki < sume + *laki sume+rami < sume + nami < (m⇔nの音韻転移) sume + mina < sume + *bina というような語形変化が生じた可能性が出てきます。「女性形」のスメラミは、「男性形」のスメラキの影響で na > ra の音変化が起きて類似語形に収斂させられたと解釈されます。ペアになる語同士で、このような「干渉現象」が生じることは、上に「父」「母」の例を挙げて説明したとおりです。 英語の例: male(男・牡)/female(女・牝)はこのような「干渉現象」の一例です。かつて female はfemelle だったのですが、male/femelle とペアで使われる機会が多かったために、maleに引き寄せられて、female と語形変化しました。 「スメラキ」「スメラミ」の語源が忘れ去られてしまうと、これらの語は、「スメラ」+「キ」/「ミ」と再解釈されるようになります。なぜなら、日本語には語頭にラ行が立たないという原則があったために、「スメ」+「ラキ」・「スメ」+「ラミ」という語形分解は不可能だからです。 こうして「スメラ」〜「神聖なる支配者」という語が形成され、「スメラ・ミコト」という合成語が形成されたと考えられます。「スメラ」は「スメ」よりも後世に、「再解釈」(Reanalysis)によって生じた語です。 「スメラ」(sumera)は、「古代日本文明シュメール起源説(!)」、「日本ユダヤ同祖論(!!)」の「証拠」とされたり、モンゴルの「スメル山」(サンスクリット語起源)が語源(大野説)であるとか、各種トンデモ説の温床になってきた語ですが、私は以上述べてきた語源解釈が、(たとえ sume の語源が不明でも)、最も言語学的に首尾一貫性が高いと考えます。 更に、「カムロミ・カムロキ」というペアがありました。「カム」は明らかに「神」(kami2 > kamui)の「被覆形」で、「カムロキ」は「神」+「ロキ」と分解されます。従来の国語学者の説では、kamu-ro2(a)-mi/ki と分解し、 ro2(a) は、語調を整えるために挿入されたツナギ音と解釈せざるを得ないのですが、そうすると ki =「男」 という、他で実証されない語の存在を仮定せざるを得ません。 「スメラキ」「スメラミ」から「スメラ」を抽出する考え方では、「カムロキ」・「カムロミ」はどう処理するのでしょう? *laki という語形さえ認めれば、「イザナキ」「スメラ(ロ)キ」「カムロキ」「タケ(猛し)」という4語の語源をごく自然に、統一的に解釈できるワケです。 以上の結果をまとめます。 |