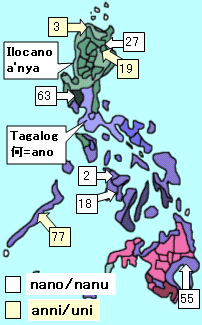1ページ 目はこちら。 各論2 疑問代名詞 基礎語彙100語に取り上げられているのは、「誰」と「何」の2語です。
#6 「誰」(タ・タレ) 「タレ」は、ta-reと分解され、後半の re は、「これ」「それ」「あれ」などの接辞「れ」と同源と考えられ、「タ」が語根です。 村山は指示詞に接続する "re" については、ツングース語の 「これ」 (エヴェンキ語): e-re (参考: 古代モンゴル語 「あれ」 te-re) と比較できるとしていますが、私の知る限りでは、「タ」の語源についてはアルタイ系ともAN系とも何もコメントしていません。 私は、デンプウォルフの再構形 [t']a[j]i とCANDに載っているR.D.Zorcによる i-sai の語根 sai と「タ」(ta)は同源の可能性があるのではないかと考えます。ここでは説明は略しますが(後述の予定)、デンプウォルフの t' と、Zorcの s は、ほぼ規則的に日本祖語の t に対応し、祖語の *sai は、 日本祖語で *tai 上代日本語で、「テ」乙類 (te2)になると考えられます。それでは「タ」が「テ(乙類)」に遡る可能性があるのかどうか? 「誰」の単独形は、例えば古事記歌謡#94、 「御諸に つくや玉垣 つき余し 誰にかも依らむ 神の宮人」 の「誰にかも」の万葉仮名が、「多爾加母」(タニカモ)なので、「誰」の単独形は、ta です。残念ながら、「誰」の古形が tai に遡る事は実証されません。デンプウォルフの再構形に拠った村山が*t'ajiと「タ (ta)」を比較しなかったのは、古代日本語に、te2 が確認できないためだったかもしれません。 ここであきらめずにオーストロネシア諸語の語形を見ると、以下のような語形が見られます。
大部分の言語では、祖語の -ai が残存するか、トバ・バタク語などのように前舌母音に変化した形になっていますが、その一方で、フィリピン南部とその南のスラウェシ島の言語(Gorontalo語)に ta/ta: という語形を示す言語があって注目されます。これを日本語の「タ」と比較できるかは微妙なところです注)。 注) むしろ私が注目するのは、チャモロ語の haye です。チャモロ語の h は、AN祖語のd に由来する場合があり、 *daye に遡る可能性があります。とすると、 *daye > taye > tae > taa という推移で ta が生じた可能性があります。チャモロ語とAN祖語との対応はけっこう難しいので更に検討を要します。 次にアクセントですが、日本語誰(タレ)の平安時代のアクセントは高・高(HH)です。上の表に挙げたSubanen 語のアクセントを見ると、第一シラブルにアクセントがあり、一応、アクセントは一致しているとみなす事ができます。 以上の結果を総合して判断すると、「誰」がオーストロネシア系の起源を有する可能性はあるが、どうも論拠(日本語と一致を示す語例)に乏しいと判断せざるを得ません。やはり△でしょう。 #7 「何」? 「何」は、上代日本語でも「ナニ」(nani) で現代語と同じです。万葉集に多数の用例があります。1000年以上も形を変えなかったのだから、たいしたものです。 時代は下って平安時代になりますが疑問詞としての用例に加え、反語的な問いかけにも使われました。 「花に飽かで何帰るらむ」 (古今集) 漢文に良く出てくる「どうして〜できようか、いやできない。」というヤツです。 上代では、このような反語的表現に使われる語として、「アニ」がありました。 例えば万葉集の#346では 「夜光る玉といふども酒飲みて情(こころ)をやるにあに若(し)かめやも」 と使われています。(どういうシチュエーションだか良く分からん歌ですが。) 疑問詞「ナニ?」は、「ナニ!」のように感嘆詞にも転用されますが、「ナニ!」の用例は中世からです。上代で確認される感嘆詞に、「アナ!」があります。以下は古事記の用例です。 更に其の天(あめ)の御柱を先の如く往き廻りき。ここにイザナギのミコト、先に「あなにやしえをとめを」と言ひ・・ 「あなにやしえをとめを」は「何とまあ、美しい娘だ!」と訳されますが、アナ(ana)は、先に挙げた、nani 、ani と関連した語と考えられます。 こうして上代には、
という語が確認されるワケですが、これらはいずれも語形が類似している上、アクセントも一致しており(「アナ」のアクセントは疑問があるらしいのですが)、同源語である可能性が高いと考えられます。 AN祖語で「何」は、apa と再構されるのがデンプウォルフ以来の定説になっています。"Austronesishces Woerterzeichnis (1938)" を見ると、apa という語形は、ジャワ、マレー、フィジー、サア、サモア諸語からの再構で、フィリピンの言語は再構に使われていません。 フィリピン諸語で「何」はどういう語形をしているかを簡単にまとめた結果を下図に示します。面白い事に、nanu 系とani 系のフタツの語形があります。
フィリピンの公用語であるタガログ語では、ano ですが、イロカノ語 aniaのように第2母音が高舌母音である言語と、語頭にnを有する言語が、ともにかなり広い範囲に分布しています。 WurmとWilsonが編集したAN祖語辞典(1975)では、フィリピン祖語として 「何」=*anu を設定しています。多分、nano などは、「前鼻音化形」 n/anu からの発展と考えるのでしょう。 古代日本語のnani は、フィリピン祖語の *anu の前鼻音化形 *nanu から生じたものと推定されます。 *nanu からnani で、後舌母音uが前舌母音 iに変わっていますが、これは前舌で調音される子音nの影響と考えれば自然な音韻変化です。(*anu > ani も同様) アクセントですが、フィリピン語では、タガログ語・イロカノ語ともに第2シラブルにアクセントがあり、日本語でもLHと後半が高声調で、一致していると見なせます。 日本語「何(ナニ)」(関連語アニ)がAN祖語ではなく、フィリピン祖語を起源とする事は、かなり確実性が高いと考えられます。 私の考えでは判定=○です。 村山説との比較 ここまで自分で考えて村山氏の著書を読み返してみたのですが、やはりプロは違います。見方が広い。 村山説の趣旨をまとめると、 タガログ語 ano < anu=a+nu 何? sinu = si+nu 誰? トバ・バタク anu 或る物 (something) ジャワ語 anu 同上 マライ語 anu 同上 インドネシア祖語 *anu 「或る物」が再構される。 タガログ語の例から、a = ”物”、 si = ”人”、 nu =不定代名詞 と分解できる。 日本語の nani も n+a+ni(< nu) という構成から成ると考えられる。 語頭の n は、台湾のアタヤル語の nanu を参考にして接辞と解釈する。 というものです。台湾、フィリピン、インドネシア諸語の語形をフルに使って立論されています。こう考えると、フィリピン語だけが日本語と類似しているという主張をする必要がなくなります。 ウ〜ム、なるほど、サスガと、うなってしまうのですが、台湾諸語の語形が日本語と類似する例は非常に稀なのが気に入りません。私としては、
否定詞 「イナ」 説明の都合上、私の考えを述べる前に、村山説を紹介します。 村山説: 「日本語の研究方法」(1974)で展開されている説 否定詞 「〜ず」を、 nsu = n +su(為) と分解し、万葉集#167 の「一に云う」の語形、「行方しらにす」を根拠に、nsu < ni + su と考える。su は、ツングース語(満州語)の se と同源と見る。 ni は、朝鮮語の否定詞 ani と関係あるとし、否定詞の古形を *ani と再構し、上に挙げた反語の副詞「アニ」と同源と見る。即ち、 ani : 疑問詞 → 反語副詞 → 否定詞 という変化を想定し、日本語の動詞否定形である「動詞未然形」+「〜ず」を、朝鮮語の以下のような表現、
と同形とみなす。 これもウ〜ムとうなってしまう説なのですが、私が上の村山説で気に食わないのは、 疑問詞 → 反語副詞 → 否定詞 という迂遠な経路で日本語の否定表現が生じたとする点にあります。日本祖語がツングース語の文法要素を基本にAN語を取り入れて成立したのなら、AN語あるいはツングース語の否定詞をなぜ使わなかったが分からない。否定表現というのはコミュニケーションにおける基本的な部分のヒトツと思うので、それが祖語の段階でこういうまどろっこしい過程で生じたというのはなんかシックリこないものがあります。 それでは、AN語の否定詞は何だったかというと、CANDには、qazi/diaq という語形が載っていて日本語(朝鮮語とも)とは合いません。 しかし一方、タガログ語では hindi 、Manobo語では indaで、フィリピン祖語(Zorc説ではフィリピン祖語の再構が可能と考える)では *he(n)di と、前のシラブルに鼻音が前置される語形であるのが興味を引きます。 -ndi の連続子音が、日本祖語で ni になる例を他に発見できれば、日本語の否定詞の ni や「イナ」(ina)が *hendi > *indi > ni > ina のような過程でフィリピン祖語から直接生じた可能性が出てくると思われます。しかし、母音の不一致や、ndi > ni の音韻変化が実証されない限りはちょっと苦しい感じがするのは否めません。 現時点での私の判定は?です。 暫定的結論と日本語は「混合言語か?」について 8つの語を調べ、
という結果でした。現在のところ、AN語の一致率8分の1=12.5%です。アルタイ語は8分の4で50%。 今回検討した語は文法要素だったので、アルタイ起源とみなされる語の率が多くなりました。仮に文法要素の多くがアルタイ系の語であれば、語彙のほとんどがAN語起源だとしても、その言語はアルタイ語と解釈すべきというのが言語学の一般論的見解です。 オーストロネシア語の例を挙げておきます。 パプアニューギニアに進出したAN語に、Maisin語、Magori語という言語があるのですが、この言語がAN語なのか否かをめぐって混乱がありました。 今ではこれらはAN語に分類されていますが、J. Lynchの言葉を引用すると、 「これらの(語族の)決定は、ほとんどすべての語彙を無視し、代りに文法システムの中核部分のみに着目する事により達成された。これらの言語でさえ、二つの異なる言語を同格の祖語に持つという意味での真の混合言語ではない。むしろ、これらの言語は、他の言語(パプアニューギニア諸語)からの影響があまりに強いために帰属の決定が非常に困難だった例である。」 (J. Lynch "Pacific Languages" p. 218; 強調と括弧内の補足は引用者による。) という事です。とすれば、更に検討を進めて「基礎語彙」の多くをAN語起源と判定できたとしても、日本語の帰属問題は解決しない事になります。 「文法システムの中核部分」とは具体的にどこまでを指すのか、明確な基準があるのでしょうか? 常識的に考えれば、「それ無しでは文が構成できなくなってしまうような文法要素」という事でしょう。日本語で言えば、人称代名詞・指示代名詞・疑問詞・動詞活用語尾・助動詞・助詞が「中核的文法要素」でしょう。 「基礎語彙」には入ってないのでここでは取り上げませんでしたが、AN起源と考えられる超中核的文法要素に、所有格「〜の」があります。今回の検討だと、「惜しい」と判断される語も含めれば、8語のうち3つがAN語起源です。これは「文法体系の中核要素」にどれくらい食い込んだ事になるのでしょうか? 「混合言語」の存在を否定する学者の主張の最大の根拠は「そのような言語は発見されていない」なのですが、日本語は世界に稀なる「混合言語」なのでしょうか?なんだか、それは信じ難い気がします。 別のページで「日本語はクレオール語とは思えない」と根拠を述べずに書いたのですが、今では、もしかしたら日本語は本当にクレオールなのだろうかとも思えてきました。 今まで、古代日本語に含まれるAN語を抽出する事で日本語の起源に迫ろうとしてきたワケですが、起源問題を解決するには、やはり、その他の文法要素、特に、動詞活用・助動詞・助詞の起源を本格的に検討する必要があります。 文法要素については、語順(AN語ではVSOだが日本語はSOV)の問題も含めて、いずれ本格的に論じるつもりです。まだこの問題を取り上げるには準備が整っていません。 今後の予定 とにかく、取り合えずは、最初の予定の通り「基礎語彙」にどれくらいのAN語が入っているのかを検討する基礎的作業を続けるつもりです。完了がいつの事になるか全く分かりませんが、気長に行きます。 とは言っても読む者にとってはタイクツ極まりないものになると思うので、以後は、「基礎語彙比較」(定期更新)と「チョット面白いと思った語彙比較」(不定期)の2本立てで進めていこうかと思っています。 2004年 7月31日 第一稿 作成 2004年 8月7日 「否定詞」の項を改変。但し「?」の判断は変わらず。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||